2019.3月 (50)海文堂最後の日々

(50)海文堂最後の日々
海文堂書店が店を閉めて、はや5年半になります。その後も次々と老舗と呼ばれるような書店が閉店し、またオープンからさほど経っていないお店も撤収し、本屋地図の書きかえは終わることがありません。個人の方が小規模な店舗を始めたといういくつかの情報がかすかな明るい材料ではあります。
その5年ほどのあいだ、どんどん過去になって行く海文堂のことをこの場をお借りして書いてきたのですが、私にとっての海文堂も次第に遠くなってきました。この切りの良い50回目で「海文堂のお道具箱」は終了します。なので閉店の頃のこと、さっとおさらいしますね。
2013年8月初旬、その日の朝礼は、曜日ごとの担当者ではなく社長が行うことになりました。何かお話がある時の常です。ただしこれといったお話はありませんでした。プリントが配られて、そこには2カ月弱の期間にどのように店を空にするかの日程表が書かれていたのです。私たちはその時初めて、9月末に海文堂が閉店することを知らされたのでした。平野さんの「何か他におっしゃることはないんですか」との質問に、少なくとも私たちが聞きたい知りたいことへの回答はひとつもなく、経緯も理由も真意も展望も何も分からないまま99年もの歴史に幕が落とされることになりました。この時の終わりの始まり方が、喉に刺さった小骨のように引っかかったまま長く私の内に残ってしまいました。
海文堂の閉店は倒産ではありません。会社は存続していて書店を廃業したのです。倒産であれば奇特な資産家の方がおられたとして、負債ごと買い取られて店を続けるなどという夢のようなことがあり得たかもしれませんが、土地建物が自己物件であり、売りに出されてもいない本屋はオーナーのなすがままに店を閉じるしかありませんでした。
それから閉店までの2か月足らずは怒涛の日々だったと言って良いかと思います。海文堂最後の日々が始まったのです。新聞社やテレビの取材が入り、ご近所からも遠方からもお客様がお見えになり、顧客の方も初めての方も久しぶりの方も一気に来店されました。出版社の方々も大勢ご挨拶に来てくださいました。それまで喧騒とは程遠いのんびりした海文堂だったのが一変し、急に「神戸市民話題のあの」海文堂になりました。
通常なら閉店や撤収は商売上の敗者がするわけですから、ひっそりと、時には憐みの視線を浴びつつ消えてゆくものだと思うのですが、なぜか海文堂には非常に好意的な同情の声が集まりました。多くの方が惜しい、残念だ、あんなにいい店なのに、すばらしい棚なのに、街の損失だと発信してくださったのです。それはあたかも真面目が取り柄の目立たない子が急に脚光を浴びるような経験でした。そんなにすごい書店だったとは、働いている我々ですら知らなかったことです。新聞記事の論調が大きく反映されたことを実感しました。
オリジナルのブックカバーが大人気となり、帆船の絵のしおりが突如お宝のような扱いを受けました。来店記念に鳥瞰図絵師の青山大介さんが描いてくださった『海文堂書店絵図』を買ってくださる方も多く、夏葉社さんが急遽出版してくださった海文堂の写真集も完売しました。フェアはいつにない売れ方をし、海文堂バブルは9月末の最終日まで大きくなり続けました。あまりに忙しくすべきことが多く、先のことなど考える余裕もありません。最終日の長蛇のレジ行列や最後のシャッター閉めを見守った方々の多さは想像をはるかに超えるものとなりました。
そして閉店、残務整理、スタッフのお別れ会、有志の方々によるお疲れさま会、有休消化。比較的若かったスタッフ4名は書店員として新たな環境で働き始めました。その他のスタッフの多くは順次仕事を見つけ、たぶん元気で今に至っているはずです。
最後の2か月の印象があまりにも強く、それ以前に私が海文堂で働いた10年間の記憶はすでに薄っすらしてきました。この「お道具箱」で海文堂の日常を書こうと思ったのは、海文堂ファンでいてくださった方々にお礼の気持ちを表明したかったのと、先に書いた「小骨」のせいかもしれません。平野さんが『海の本屋のはなし 海文堂の記憶と記録』(苦楽堂)を上梓したのも、私と似たような引っかかりがあったからではないかな。
閉店の経緯を語る時はいつも会社を非難しているような口調になってしまいます。見苦しくてすみません。私は前に働いていた書店が倒産し当日に突然の閉店を知らされた経験と、海文堂のように前もって閉店日を決定する形態の両方を経験したことになります。どちらの場合も、それまでお給料をくれていた人を批判してしまうような状況になったことが残念です。また、本屋の仕事や同僚たちのことが嫌いになって辞めた訳ではないので、しばらくの間は心が残りました。引き剥がされるような形で退職せざるを得なかった人が立ち直るのには割と時間がかかるのです。でもおかげさまで、たくさん書かせていただいて整理もつきました。もう元町商店街3丁目も歩けそうです。
ここからはこれまでの連載でテーマに挙げなかったことを。お道具箱拾遺です。
〈立ち読み〉
立ち読みはリアル書店の特権ですからね、どうぞご遠慮なく。手に取って手触りを確かめ、装丁を愛で、奥付を確認し、著者の略歴を見、目次にも目を通してください。任意の1ページを読めば読み通せるかどうかだいたい分かります。あ、これは書店員が本を店に出す時のやり方でした。そうでない方に立ち読みのルールはありません。売り物ということを念頭に置いてさえくだされば、どんな読み方をしても構いません。売り物だから丁寧に扱うということに関連してお願いがあります。立ち読みする時にスピン(栞代わりのひも)を使わないでほしいのです。
ある日、三国志を題材にした小説のシリーズの棚から、スピンのはみ出た1冊を見つけました。スピンは買った人が初めて使うべきと私は思っているので、はみ出ないように本の中に収納しました。翌日、同じ巻の少し進んだページからスピンがはみ出ています。また戻します。どうやら毎日少しずつ読み進んで行くつもりのようです。実際何日もかけて日々着々と進んでいる様子。こちらもスピンのページを一気に進めたりして対抗したのですが、結局何巻か分、読み終えてしまったようです。後にはすっかり毛羽立ったスピンのはみ出た本が……。私の負けです。スピンが毛羽立っていると、一気に古本っぽくなるのです。どうしてもというなら中に挟んである出版案内などで代用してくださいね。あと、本屋あるあるだと思うのですが、平台にあった本を手に取ったあと裏向けに戻す人が多いのはなぜなのか。何を読んでいたか知られたくないから? 余計にばれると思うのですが。
〈万引き〉
もうこれは言語道断。思い出すだけで悔しくて腹が立って……。私の今の職場が万引きとは無縁の業種なのでそれだけは幸いと思う。本屋には老若男女、誰が入って来ても違和感はありません。硬い人も柔らかい人もお金持ちもそうでない人もオッケーだし、買う気のない人でも入れます。お客様を選ばない業種だからこそ狙われるのです。売ってもたいした額にはならないでしょうに。
前の本屋の時、勇敢な女子スタッフが万引き犯を追いかけて地下街を走りに走ったことがありました。一時は対決して「返して下さい!」と言ったそうですが、無念、逃げられてしまいました。これってものすごく危険なことです。よく無事に帰って来られたと思う。海文堂でも男性スタッフが何人も捕まえました。でも捕まえることが出来なかった方がはるかに多い。棚の一部がぱっくり空いているのに気付いた時の焦り。スリップは?取り置きは?どちらもない時の衝撃。丹精込めて作った棚を破壊されるショック。それが一回ではなく、味を占めて何回も続くのです。泣き出す女子スタッフもいましたよ。盗られる方が悪いって? いいえ!盗る方が絶対悪いんです!
万引きの多さに多くの書店は疲弊しています。精神的にも経営的にも。書店員の心を蝕むこの犯罪が、街の本屋を減らす一因でもあるのですよ。
〈店頭販売〉
海文堂は店頭を業者の方に場所貸しして、ワゴンで何がしか販売してもらうことがありました。ほぼ常設のCD屋さんに次いで長かったのがフェアトレード品のワンビレッジワンアースさんです。女性お2人が交代でやって来て、大きなトランクから珍しい商品をワゴンに並べて売っておられました。東南アジアから仕入れた可愛らしい雑貨や細やかな手仕事の品は見ていて飽きないものでした。wさんとは海文堂の棚卸しでペアを組んでから親しくなりました。もうお一人のIさん共々、商品についての知識がとても豊富で、歴史的な背景などの詳しい解説にいつも感心していました。私はこんな風にお客様に熱心に説明できただろうか…と反省を促すものでもありました。ここで見つけた細かいクロスステッチのモン族の定期入れを、今も大事にしています。
この「海文堂のお道具箱」を読んでくれる人っているんだろうかと思いつつ書いて来ましたが、いつもコメントを寄せてくれるくとうてんのGさんとEちゃんにはとても励まされました。少なくともお2人は読んでくれている。その実感だけで続けて来られたような気がします。この場を提供してくださったくとうてんのみなさまにお礼申し上げます。
(三毛小熊猫 元書店員)
2018.12月 (49)サイン会

(49)サイン会
海文堂では月に1~2回、不定期にイベントが行われていました。それらはほとんどが2階のギャラリーでの開催だったのですが、サイン会だけは1階の中央カウンターで行われました。大手書店でよくあるように、整理券が必要だったり売り場とは別の会場で行われたりということはなく、当日たまたま通りかかった人もその作家の本さえ買えばサインしてもらえるという気軽なサイン会でした。
当日は、中央カウンターのいつも店長の座っているコーナーが作家さんのお席になるので、まずペン立てやメモ、セロテープなどを片付け、電話のコールをオフにします。受話器は店内各所にあるのですが、外線は中央カウンターが取ることになっているのを当日だけは切り替えて、奥にある平野さんのデスクで取るようにするのです。そしてすっきり片付いたカウンターに大きな白い布(私はシーツと呼んでいました)を掛けます。何となく仏事が始まるような感じと思いつつ、いらぬことを言わずに布を広げます。そこにいつも児童書Tさんが用意する小振りの可愛らしい生花を置くと、ぐっとそれっぽく、華やかな感じになっていました。
用意するのはサイン用のペンを数本と文庫サイズに切った半紙。これはサインのインクが本に付かないようにページに挟み込むもの。サインペンや朱肉はご自分で用意される作家さんが多かったですね。その作家さんの新刊とそれ以外の著作をワゴンに用意して、あとは店長がマイクを手にアナウンスを始めます。
サイン会の日程は急に決まることが多く、海会を使って告知することは他のイベント程なかったように思います。海文堂は当時としてもアナログな本屋だったので、作家の方が自ら発信されない限り、たまたま来られたお客様だけしかサインもらえなかったんじゃないかなあ。
作家さんはまず為書き(○○様などのあて名)を書いてから(間違うと悪いからと書かない方もいる)サインをされます。何かひとこと書いてくれることもあります。担当の編集者の方が同行されているのでその方が落款を押します。我々スタッフが半紙を挟み込みお渡しします。ファンの方はサイン後の一瞬が何かひとこと話せるチャンスです。
サイン会の多くは出版社からの依頼を受けて店長が決めるのですが、海文堂の性格のせいか人文系分野や神戸本関係の作家さんが多かったですね。文芸書担当の私が直接サイン会にかかわった作家さんは中島さなえさんお一人だけなので印象深いです。スタッフに中島らもファンが複数いたので、娘さんであるさなえさんの小説家デビューをぜひ応援したいねと話していたところ、双葉社さんからお申し出があり『いちにち8ミリの。』のサイン会が実現したのです。
さなえさんはバンドやお芝居もされていたので、当日にはお仲間の小劇場の役者さんが何人も来られてサインの列に並んでくださいました。こうして応援してくれる人がまわりにたくさんいるのってすばらしい。前年に、新刊エッセイの紹介を海文堂のブログに書いたことを知っていてくださったこともあり、初対面の時から気安くさなえちゃんと呼ばせてもらっていました。こういう親しみやすい作家さんは場をなごませてくれるので本屋としてはとてもありがたいです。列が閑散とした時に不機嫌になる作家の方がいたことを伝説として聞いたことがありますし。さなえさんは当時流行していたちっちゃい帽子を頭にのっけていたのが可愛らしくてよく覚えています。元町界隈では見たことなかったですもん。
トークや講演会、朗読会、原画展、写真展、サイン会などで多くの作家の方々が海文堂を訪れてくださいました。お礼の意味も込めて本当はみなさんを紹介したいところなのですが、それはやはり私の役割ではないと思うのです。この「海文堂のお道具箱」は、私の私的な印象記です。私が直接かかわって感じたことだけを書くべきだと思うので、それ以外のことはそれぞれふさわしい人に書いてもらいたい。海文堂の顧客のみなさんにとっては取り上げていないことだらけで、さぞ物足りないことだと思いますがどうかお許しくださいね。
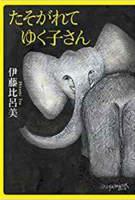
伊藤 比呂美・著『たそがれてゆく子さん』
2018年8月発行 中央公論新社
日々たそがれつつある私はこのタイトルの前で立ち止まらずにいられない。たまにしてしまうタイトル買いの、これは成功例です。私は詩が解読できない人種なので、詩人としての伊藤比呂美はちゃんと読んでいないのです。過去に読んだのは『良いおっぱい、悪いおっぱい』の頃の一連の子育てエッセイ以来かなあと思ったら、そうそう、『閉経記』を読んだぞ。海文堂の朝礼で「身も蓋もないタイトルですがすごく面白い」とかなんとか紹介したぞ。そしてこの『たそがれてゆく子さん』は、婦人公論連載のエッセイを書籍化したもので、『閉経記』に続くものなのでした。
カリフォルニア在住の著者は熊本との往復介護をしていた父上を亡くし、母上もその前に亡くし犬も2匹看取った。3人の娘たちは独立してもはや悠悠自適かと思えば次は年の離れた夫が弱り始める。還暦の著者に対して夫は87歳。病気持ちで関節炎のために常時痛みと戦っている。一人で介護をしつつ、犬たちを可愛がり、仕事で日本に出かける日々。
本書始まって3分の1で夫は亡くなってしまいます。その顛末をきれいごと抜きに綴る比呂美節。苦しくしんどく悲しいことなのに読む人を泣かせない潔さ。不謹慎ながら興味を引き付けられて止みません。
動作も排泄も自分でコントロール出来ず激痛にさいなまされる夫に、著者は訊ねる。「死を選ぶ気はないのか」と(オレゴン州は安楽死が合法)。夫の答えは、
「自分が戦っているのは『動けなくなった自分』に対してで、『死』ではない。まだまだ戦う余地はある」
さらに進行し夫の望みで自宅に帰って来ると
「昨日までは死にたいと考えていたが、この青い空を見たとたん、死にたくなくなった、いつまでも生きていたくなった」ああ、やっぱりこの男は、と呆れるとともに、死にたいと言われるよりずっと楽だ。便は臭くたって、生きてる方がずっと楽だ。
看取るということの著者の疑問は私の疑問でもあります。ひとはどんな状況でもこのまま生きたいと思うものなのですね。生きものは本来そのようにプログラムされているのでしょう。この夫も若い時は身体が効かなくなったら頭をズドンだ、と言っていたのだし。最晩年の人の感じ方を想像するのは難しい。そして看取ったあとの寂しさを想像することも。
長年新聞で人生相談の回答者をやってきた著者は既に人生のコツを体得していて、あとは応用だと言います。その奥義のシンプルな言葉に、私は大いに共感したのでした。たとえば、いい歳をしていても親に反抗していいんだ。あるいは意志とか意識とか、自分でコントロールしようとしないでいいんだ、とかね。
私より一歩先を行くおねえさんの位置にいる著者は、いろいろな、かなり激しい経験を積んでいて、それを私たちいもうとに教えてくれます。親を看取ること、夫を看取ること、そのあとかたづけにとどまらず、かつての夫や娘たち、自分の身体のこと、身の回りのこと、孤独とのつき合い方などを惜しげもなく赤裸々に語ってくれるのです。こんな風に書けば暗くて深刻な本かと思われるかもしれませんが、そこは伊藤比呂美ですから。この人の文章、面白いんです。軽快できっぱりしていて、とても信用できる芯がある。性格テストで外向性85パーセントと出た人らしく、開けっぴろげで明るい。読者を楽しませてくれるけれど無理はしていないと思うんです。文体と人物が一致しているタイプ、たぶん。
当人は「あたしは社会的な発言が苦手である。というより嫌い」と書いておられるけれど、仕事のお相手がなかなかの方たち。田中美津、上野千鶴子、瀬戸内寂聴、石牟礼道子の各氏が本書に登場しています。お友達はじゅうぶん社会的。上野さんの『女ぎらい』を読んだばかりだったので、「(上野さんの言葉を聞いた)その一瞬、何かがものすごくクリアになった。おそろしいくらい。これが上野さんだ」という一文にいたく納得。好きな本同士がつながった瞬間です。
前著『閉経記』のタイトルに「平家物語」と「義経記」の意味が込められていたとは今さらながらびっくり。戦記はたそがれても続いてゆくのかな。ラストの「今はすこーしも寂しくないわ♪」に安堵。我が行く末もかくあらんことを。
(三毛小熊猫 元書店員)
2018.10月 (48)ブックフェア

(48)ブックフェア
海文堂にはブックフェア専用に使う平台が3か所あり、年末年始用品の販売台として使う2カ月半以外はつねに誰かがフェアを開催していました。年間27回ものフェアは持ち回りでジャンル担当者によって行われます。1人につき1年に3回程度当たることになります。これらのフェアは、オリジナルであるがゆえに海文堂らしさの象徴であるとされていた(かどうかは知りませんが)ので、いきおい力が入りました。これは私だけかもしれませんが、結構毎回入魂していました。
毎年秋になると、翌年のフェアの担当表が作業場に貼り出されます。各自割り振られた月に何をするか考えて、担当の前月に企画書を提出するのです。企画書の内容は、フェア名とどんなフェアかの説明、メインとなる本を4~5冊。もともとは手書きで書いていたのですが、海会に載せるようになってからはワードデータで提出するようになりました。ということは店長や社長にではなくお客様に向けて書くようになったということ。こんな面白いフェアをしますからぜひ、と呼び込みをするように書くのはなかなか楽しかったな。
フェアが終わってからは報告書を提出します。売れた冊数と金額。フェアをして気がついたこと、反省点など。たいがい思ったほど売れなくて、目標未達の反省文ばかり書いていましたね。私が企画したフェアで一番成績がよかったのは、閉店が決まってからの最終フェア「いっそこの際、好きな本ばっかり」ですが、まあこれは特例ですね。閉店するからこそ売れた本たちですからね。桁違いの売れ方で追加が間に合わず、売る本が無くなってみすぼらしい程でした。
他に売れゆきがよかったのは前年に亡くなった人の本ばかり集めた時。高峰秀子さんの本がよく売れたなあ。楽しかったのは夏葉社『冬の本』ブックフェアで掲載の本を集めたこと。晶文社フェアで植草甚一Tシャツや缶バッジを売ったこと。雑誌編集会議の新人応援特集を応用させてもらったこと。あと、出版社の未知谷や自分が好きな向田邦子、クラフト・エヴィング商會のフェアが出来た時は、もう思い残すことはありませんと報告書に書いた記憶が。
他のスタッフのフェアも興味津々でした。自由に考えるフェアというのはなかなか難しくもやりがいがあり、その人らしさが発揮されて、フェア台は担当者のセレクトショップと化します。毎月1日に3つのフェア台を見て回るのが楽しみでした。
担当ジャンルに関係なく自分の信念をフェア化する店長。ファンが大勢やって来て賑やかな児童書Tさんのフェア。一糸乱れず行き届いた文庫Hさんのフェア台。学参Sさんは大人の実用に役立つフェアを。硬派で社会派の平野さんはもの言いたいフェア。実用Kさんはその時々の流行をうまく取り入れて。ゴットさんは他では入手しにくい船の本やグッズを。意表を突くテーマとこの並びでこの本置くのかのアカヘル氏。私のフェアはひとことで言うと、昭和の文化祭の展示発表みたい。
開催中の1か月間はフェアの売上げが気になって、1冊でも多く売れることを念じつつ過ごしていましたが、いつも熱意だけが空回りしていて…。書店員に最も求められる「売るセンス」が私には不足しているようでした(涙)。
これらの平台以外にも、急遽フェアをすることがありました。著名人が亡くなった時です。中島らもさんが亡くなった時、ミニフェア用にポップを作りました。サングラスの絵と共に、「らもさん、死んだらシャレになりませんがな」と書いて。この時店長がたいそう喜んで励ましてくれたのが、私がフェアに注力する原点になったのかもしれません。急遽フェアはほかに、人文の新刊台を大きく使った「激励の言葉より本を売る」があります。東日本大震災で被災した出版社荒蝦夷の全点フェアです。平野さんが書店員生命を賭けて(?)行ったこのフェアは大きな反響を呼びましたね。
海文堂で働いていてもっとも頭を使ったのが、オリジナルフェア開催の機会でした。自分ですべてを決定できるということが、仕事をする上でいちばん面白いことだと思うのです。本屋の業務は力仕事も事務的な仕事も多いけれど、知恵を絞って創造する仕事もわりとたくさんあるんですよ。

宇田 智子・著『市場のことば、本の声』
2018年6月発行 晶文社
この本の紹介記事を新聞書評で読んだ時には、あ、ウララさんだ、と思っただけだったのですが、実際に書店でパラパラ読んでみると止められなくなりました。内容もさることながら、なんというか、文章に惹かれるのです。なぜだか各所で鼻の奥がつんとするのです。
著者の宇田智子さんは新卒で入社したジュンク堂書店池袋店で7年働いたあと那覇店に転勤し、2年後に退職して第一牧志公設市場の前で古本屋を始めます。その名も市場の古本屋ウララ。1980年生まれの若い店主が綴った自分の店と店のある市場とさらに沖縄のこと。
宇田さんの文章は淡々としていて、対象との距離は必要以上に狭まることはありません。沖縄で古本屋をオープンして7年経っていても本土から移住してきた人らしい姿勢は変わらず、いきなり相手の懐に飛び込んだりするタイプではなさそうです。お客さんともご近所さんとも礼儀ありの淡き交わりに見えます。その距離感を文章にすると、なんとも言えず胸を打つのです。ちょっと離れているからこその、思いのかすかな揺らぎにリアリティがあるのです。
沖縄で知り合ったさおりさんが本土に帰ることになった。雑誌に哲学者か占い師のような店主、と書かれた宇田さんの店に、たびたび遊びに来る。
「ごめんねともちゃん、いつも聞いてもらうばっかりで」
聞くしかできないのだ。哲学者でも占い師でもない私は、どんなに声を聞いてもなんのご託宣も受けとれないのだもの。
さおりのソウルメイトであるたもつくんが彼女の乗った船を見送ったあと、ウララを訪ねて来る。
「こんなにさびしいとは思わなかった」
どきっとした。私に向けられたものとも言えない、放りだされた無防備な言葉。路上でこんな心からの言葉を聞くことはめったにない。歩く人も私も、紋切型を並べてこの場をやりすごしているのに。
T字路にある古本屋で聞く辻占。彼が聞いてもらいたかった一言を、ただ聞く。これも「市場のことば」のひとつとして、柔らかい心で受け止める著者。
あるいは独身女性について言及した1章。結婚しているか、子供はいるか、仕事は、友達は、と○×で判断し、×だと勝手に同情される風潮に対する疑義。「それ」を持っていないと不幸なのか。不幸とはだれが決めるのか。独身女性がまずその点で注目されるのだとしたら、なんと生きづらいことだろう。○×というチェックリストを、私も使っていなかっただろうか。わが身の身勝手を突き付けられた気がしました。本や本屋のことだけでなく、取り巻く環境や世相について考える著者のその真面目さが、私にはとても好もしく思えるのです。
エッセイを読んだ時、まったく自分のものとは違う視点に驚く場合と、似かよった考え方に共感する場合に魅力的と感じますよね。この本は私にとっては後者。この著者の本をもっと読んでみたいと思った時に、過去に2冊の本が出ている嬉しさよ。さっそくちくまプリマー新書の『本屋になりたい この島の本を売る』を求めました。新刊書店と古本屋の仕事が分かりやすく、具体的に書かれています。若い読者向けのシリーズですが、元書店員が読んでも大変面白いものでした。
思慮深い宇田さんが、大手書店から独立して自分の店を持つ、しかも遠き沖縄で、という大胆な決断にいかに至ったのか。これはひとつ前著に当たって解明せねばなりません。本はいつも待っていてくれますからね。
「あの店の棚はいいね」と言うとき、それは棚の材質がいいということではありません。本の選びかた、置きかた、その仕事をしている店員、そして店員にそうさせるお客さんが、いいと言っているのです。棚こそが、本屋の肝なのです。
これ、これですよ。このことばこそが、本屋を語る肝なのです。
(三毛小熊猫 元書店員)
2018.9月 (47)客注

(47)客注
私が新卒で入社した本屋の時代から、ずっとお客様に言い続けていたセリフが「お取り寄せいたしましょうか。2~3週間みていただくことになりますが」というものでした。2週間から3週間って幅があり過ぎだし、そもそも時間がかかりすぎ。洋服のお直しでも1週間ぐらいなのに、右のものを左に持ってくるだけでどうしてこんなにかかるのか。
それをね、お客様に説明するんですよ。出版社と直接取引しているのでは無くて書店と出版社の間には本の問屋である取次がありまして。取次に在庫がなければ出版社まで注文が行くので時間がかかってしまうんです。
それじゃ時間かかってもしょうがないね、とはなかなかならず、なんでそんなまだるっこしいことしてんねんとなりますよね。それでも納得して注文してくださった方の客注品が2日で届いたりすると、それなりにバツの悪いものがありました。「取次に在庫があったようですね……(汗)」というわけで客注に関しては叱られた記憶ばっかりで、海文堂に入社して客注以外の担当になった時は心底ほっとしましたよ。
海文堂では中央カウンターが客注コーナーでもありました。入荷のご連絡などは児童書Tさんと中央カウンター担当のYさんが行っていました。3枚つづりの客注用紙に記入して、お客様に1枚、発注用が1枚、控えが1枚なのですが、驚いたのは発注用をそのまま取次さんに渡していたことでした。以前いた書店では版元に直接ファクスで発注していました。これだと最悪の事態(品切れ、絶版等)の場合に結果がすぐ分かります。ただ取次在庫を生かせないというデメリットがありました。海文堂の客注は発注を取次任せにすることで早く入るものは早く仕入れ、その他の版元への注文も取次担当者が最速の方法で行っていたようです。
2週間を過ぎても入荷しないものは取次担当者さんに督促します。海文堂から徒歩5分のところに取次の神戸支店があったからこそできたことだと思うのですが、一番大変な客注を取次さんにさせるのは申し訳ないような気がしていました。
やがて神戸支店は無くなり、オンラインで取次の在庫が分かるようになると、一部パソコンを使って発注するようになります。その時点でほぼ何日かかるか分かるようになって、お客様にぐんと説明がしやすくなりました。これは画期的なことで、客注の夜明けとも言えますね。今の本屋さんはもっと迅速に対応できていて、客注トラブルが減っているといいのですが。
かつて入荷が遅くて叱られたり、うっかり店に出してしまったり、入るはずのものが入荷しなくて(追跡調査ができない頃は結構「事故」に泣かされました)胃の痛くなる思いをしたりしたのは、今思えば私のコミュニケーションの問題もあったかなとも思うのです。海文堂のお客様は気長に待ってくれたし、Tさん、Yさんや店長の説明に不服を唱える人はあんまりおられなかった気がします。結局はお客様ひとりひとりとの関係、なのかな。この点に関しては、私自身最後まで克服できなかった点ではあります。
客注と言えばつい発注のことばかり思い出してしまいますが、客注担当でない人にとっては受注の印象の方が鮮明かもしれませんね。広告の切り抜きを持って尋ねてくださる方はほんと、助かります。多くの方はあやふやな記憶をいくつかおっしゃって、時には正確な情報がひとつもないことも。そんなキーワードをつなぎ合わせて想像力を働かせ、検索したりジャンル担当者に問い合わせたりして正確な書名がわかった時のうれしさは格別です。わかりましたよ!って感じですが、悲しいかな在庫がない。で、「お取り寄せいたしましょうか。2~3週間みていただくことになりますが」というセリフになるのです。
一生懸命頭めぐらせて探したのを見ていたお客様の多くはそのまま注文してくださいました。元町周辺にはほかに書店がなかったこともあるのでしょうが、海文堂が頼りにされていたともいえると思います。ネットと戦わないといけない今の本屋さんの大変さを思います。みなさん、リアル本屋で注文して、書店員さんと知り合いになってね。しろやぎさんくろやぎさんのような熱心な人も大勢います。損はないと思いますよ。
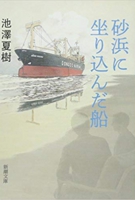
池澤夏樹・著『砂浜に坐り込んだ船』
2018年4月発行 新潮文庫
このタイトルでこの作者。東北の太平洋沿岸に無惨に打ち上げられた幾艘もの漁船を思い浮かべたのは私だけではないでしょう。著者がそのシーンを見て着想したのは間違いないと思うのですが、この短編集は震災を描いたものばかりではありません。冒頭の表題作も、北海道の港に嵐で座礁した外国船籍の貨物船を見に行った主人公と、現れ出てきた今は亡き友人との対話の物語です。友人と母との関係が哀切な心に染みる短編です。
2番目は「大聖堂」。無人島でピザを焼こうという少年たちの大計画。当日、舟の鍵を海に落として出港できず中止に。3月のその日の午後にあの災害が来た。
「あの日、俺たちが島に行ってピザを焼かなかったからああなった。(中略)、それ以前のどこかであれを回避する分かれ道があった。ただ、それがどこだかわからない」。
「やり直してみよう」ということで少年たちはピザ計画を一からやり直す。大聖堂のようなピザ窯でがんがん火を焚きつける。それが祈りとなって運命の軸が変わり……。震災を描かずに震災を描く、しかも軽快な文章の楽しいお話にして。
もうひとつ、「マウント・ボラダイルへの飛翔」。池澤さんとおぼしき主人公の眼前に作家のブルース・チャトウィンが現れる話。ブラッドベリが亡きヘミングウェーと対話する短編を書いたように、池澤さんは亡きチャトウィンと旅をして一緒に空を飛ぶ話を書いたのだ。チャトウィンを敬愛していたのですね。外国文学の棚に分厚いチャトウィンの本を差していたことを思い出して嬉しくなりました。
著者がこれらの短編を書いたのはほとんどが2011年3月以降らしいのですが、当時の池澤氏は東北の被災地に足繁く通い、新聞等に批評やエッセイを多数掲載し、同時に海外と日本の全集を個人編集するなど精力的に活動していたはず。この人はこんなに忙しくていったいいつ小説を書いているのだろうとその頃思っていたのですが、この本を読むと氏が乗りに乗っている気配が伺えます。経験したことが血肉となって作品化されていて、きっとこんな会話を実際にしたのだろうなというリアリティがあるのです。死者や被災者や心に痛手を負った人とのやり取りが心に深く残るような内容であるにもかかわらず、読者の負担にならないようなとも言うべきやさしい文章で我々を生死のあわいの世界に誘います。多くの短編に著者を思わせる人物が登場するせいで、読者が話に入って行きやすいのかもしれません。死者との対話というのがこの短編集を貫くテーマかと思うのですが、そのようなテーマであっても9編いずれの短編も実に「面白い」のです。
どの短編のことも書きたいのですが、とりわけ強く心を打ったのが「監獄のバラード」。大雪の中、元恋人の父親の墓参りをする話。かつて1度だけ彼女と訪れた墓に、線香を供えて「あなたの娘を捨てました」と報告をするために。墓の主から受けたことのある授業、オスカー・ワイルドの詩「レッディング監獄のバラード」を自らになぞらえ、雪の墓前でひとり語りをする主人公。別れるために周到に手を尽くし、時間をかけてなんとか彼女との関係を断ったのに今度は自分の気持ちが落ち着かない。切実で身勝手で真摯な男の、心の決着を付けるための墓参り。死者と対話することで内なる自分自身と対話する心の道程。
池澤夏樹様を密かに崇拝している私としてはこの場で氏を取り上げることには少なからず葛藤があったのです。でも下手くそな感想書くなよって突っ込んだのは他ならぬ自分だったのでま、いいかと。日ごろから「様」の敬称を付けている作家はお二方だけ。もうお一人は堀江敏幸様(時に苗字の後にモンを付けてしまうこともあるが)で、 なんとこの池澤氏の短編集に解説を書かれている! あまりに格調高くて私には感想 (理解?) 不能。お二人の名前が並んでいるだけで麗しい。
この本にはひとつ異色の短編があって「夢の中の夢の中の、」という今昔物語集を基にした楽しいお話。9月に新聞連載が始まった池澤夏樹『ワカタケル』も古事記から材を得ているそうで開始早々興味津々。池澤さんの幅広い仕事がいろいろな形で実を結んでいる様子を楽しめるしあわせ。当分朝刊で毎日読める!
(三毛小熊猫 元書店員)
2018.7月 (46)古書

(46)古書
海文堂は神戸新聞はじめいくつもの新聞で取材していただいたことがあるのですが、晩年の取材対象の半分くらいは古本に関することだったような気がします。新刊書店の中で古本を販売するというのは当時としては画期的なことだったようです。最近よく見かける書店併設のアウトレット本売り場ではなく、本物の古本です。当初取次さんが反対した理由は、返品の中に古本が混ざるのではないかと危惧したからということでした。
たぶん2004~5年頃、店長のラブコールに応えて穴門商店街のちんき堂さんが棚を作ってくださったのが最初ではないかと。オーソドックスな海文堂と超サブカルのちんきさんはあまりにも毛色が違うのですが、その落差を店長は楽しんでいたのではないかな。
常設棚は長らくちんき堂さんだけでしたが、2階のギャラリーを使って「海文堂の古本市」というイベントを何回も行っていました。これは数軒のプロの古本屋さんが、持参した本を区画割したコーナーでそれぞれ販売するという企画です。いつか自分でも古本屋を開業したいと、本気で考えていた(だから古物商の免許も持っていた)店長が推進したイベントなのです。何回目かに岡崎武志さんの『女子の古本屋』発売に合わせて行った「女子の古本市」が評判になり、海文堂のイベントとして定着したように思います。実はアカヘル氏はもともと古本市のお客さんだったんですよ。店長とも親しくなっていて、スタッフの空きができたら声かけてねっていう話になっていたらしい。かくて古本好きが2人になって、海文堂の古書店化に拍車がかかりました。
その後善行堂さん、トンカ書店さん、海文堂古書部(これはアカヘル氏が勝手に名乗って自分の本を売っていた)が1階奥の人文書近くに小さな常設棚をもちました。顧客の方の古本をお預かりして販売するといった、古本屋さんごっこもやりました。古本屋開業という夢をあきらめた(?)店長が、自分の本を処分したのもこの機会でした。
さらに2階に古書波止場という名の、これは棚というよりはもう書店内専門店とも言うべき常設売り場へと続きます。古書波止場は4軒の古書店さんがそれぞれの個性を生かした棚づくりをし、店番等は分担して行っておられました。ここに至ってもう海文堂の手からは離れていたことになります。古書波止場の品揃えはさすが本職。新刊書店とはまったく違う、私には近寄りがたい茶色い異空間が広がっていましたっけ。
以上のことを平野さんの著書『海の本屋のはなし』で確認したかったのですが、6月の震度6弱でわが本棚がぶっ倒れまして、本は段ボール箱行きとなりました。どの箱に入っているか探す勇気がありません……。
実は私は古本販売とはほとんど接点がなく、イベントの企画はおろか女子の古本市以外はのぞきにすら行っていないのです。奥が深くて未知なる世界に恐れを抱いていたということもあります。なのでここで偉そうに書く資格はないのですが、下で紹介する『神様のいる街』の中で著者が、「ひとえに〈海文堂書店〉が、どこか古本屋のような新刊書店だったからである。」と書いてくださったことに触発されたのです。照明が蛍光灯やったからちゃう?と憎まれ口をたたいてしまいそうですが、氏が言っているのは棚に入った本の並びのこと。実際に古本好きのスタッフがいたことが店づくりにも影響していたのかもしれませんね。
あー、私も古本入門しとけばよかったなー。新刊と古本の間の高い壁を乗り越えられなかったのは悔まれます。本を知ることもさることながら、処分することを考え始めた今になって古本屋さんの有用性を感じております。
晩年の海文堂の特徴のひとつであった古書売り場の併設。本屋業界の雲行きは怪しく、目覚ましい解決策など見つからない中で、店長が中心となって趣味と実益を兼ねつつ、少なくとも愉しく店を盛り上げようとしていた、っていうことですよね。
その試みは間違っていなかった、と思いたい。と同時に店長に、気難しくて屈託があって、心を許した人にはとことん尽くす、そんな店主を慕う人たちが集まって来る古書店を開いてほしかった気もするのです。

吉田篤弘・著『神様のいる街』
2018年4月発行 夏葉社
とても静かな気持ちで読みました。『京都で考えたこと』と『金曜日の本』が兄弟本だと以前に書きましたが、この『神様のいる街』も末っ子に加えていいですよね。ずっと物語作家であった篤弘氏が物語をいったん置いといて、内省して語る自らのこと。声高にではなく、かつての心の内をそっとすくい取ります。今思えばあの時はこうだった、ではなく、その時の雑然とした気持ちを壊さないように丁寧に。
前半は高校生の頃から専門学校生の時代。神戸に出掛け神保町に通い、どこにいてもひとりで行動しひとりで考えひとりで書きひとりで悩んでいた頃。神戸では小さな物語が街の至る所に並んでいるのを発見し、学校代わりに通った神保町では本の修行の日々。上林暁の本との出会いが著者に与えた影響を思うと、夏葉社さんの仕事を(なぜか私までもが)誇らしく思えます。
川のようだった。毎朝、大きな川のほとりに立って水の流れを見きわめ、魚のいそうな場所に見当をつけて、川の中に入っていく。 流れ動いていた。ときにゆったりと、ときに急流になり、川はまさに万感の書をたたえて、休みなく流れつづけていた。毎日が冒険だった。日々、発見があり、これは記録すべきだと、夜遅くに日記をつけた。
これは著者が通い詰めた神保町のこと。本も雑誌もコミックも、とどまることなく常に流れてゆくものであるというのは、新刊書店員の実感として私にもあったのですが、古書店を街ごと歩き尽くした著者には「どんだけ通ってんねん」と敬意を込めてつっこみたくなります。
後半は学校から紹介されたアルバイトをしながらやはり神戸に出かけ、神保町ではついに怖い古書店主から卒業の言葉をもらう。相変わらず行動し考え書き悩んでいたけれど、ひとりではない。自分と似た感受性を持つB (運命の人と言ってもいいかな)との、たからもののような青春の日々。
前半と後半の間に挟まれているのがグレーに縁どられた「ホテル・トロール・メモ」。ホテルに備え付けてあるメモパッドを自作し、そこに思いついた言葉や未完成の短文を書き連ねたものを編集したもの(の再現バージョン)。この、詩のようでエッセイのようで物語の一部のようでもある文章のいくつかは、篤弘氏名義の小説のモチーフとなり、いくつかはクラフト・エヴィング商會名義の分類しがたい本の一部分となり、残りはこれから使われるのを待っているのです。
他人は助けてくれないけれど、過去の自分が、いまの自分に、「書くことは山ほどある」と小さく叫んでいた。
困った時、悩んだ時には、かつての自分がどうすべきか教えてくれる。神戸・神保町時代に残したメモや日記の一部が、この1冊に結実したと思うと感慨深いものがあります。海文堂のことも、書き残してくれてありがとうございます。私が入社するずっと以前のスタッフにも、このような評価をいただいていたこと、知ってほしい。
『神様のいる街』を含めた3冊は、上林暁のタイトルそのままの、文と本と旅あるいは街についての本でした。来し方を振り返り真摯に内省を深めた篤弘氏はこれまでと違う一面を見せてくれました。この後、少し作風が変わるのではないかしら。Bさんもそう思われませんか? それは現在から想像する未来なので、「未来の著者」から見た答えはまた違っているかもしれませんね。
最後に。読むまでぜんぜん気付きませんでした。タイトルのこと。自分の愛する街に神様がいても全然おかしくないし、私や同僚たちが働いた神戸にも、さらに神保町にも神様いたっていいよねって。みなさん気付いていましたか? どちらの地名にも神という字が使われていることを。で思い出した。阪神大震災の時、外国メディアが神戸の意味を神様のドアと紹介していて驚いたのだった。この街が神戸と命名されたはるか昔から、神様、おられたんですね。
(三毛小熊猫 元書店員)
2018.6月 (45)取次

(45)取次
他の書店員さんや出版社の方と話していていつも驚かれたのが取次のこと。海文堂がTハンとN販のダブル取次だったことです。大手書店ならいざ知らず、海文堂の規模で日本の二大取次と契約しているというのは珍しいことだったのでしょうか。
私が海文堂以前にいた本屋はどうだったか。比重の小さな(今はなき)Y原書店や地図・ガイド本に特化したT図共販、学参のМ井書店等と取引をしていたものの、メイン取次はN販でした。だんだん書店の体力が無くなってくると、オーナーから小取次との関係を清算するように指示されます。まとめた方が取次に対して発言力も増すしバックマージンも増えるから、という理由だったと記憶しています。どうも実際は、支払いなどの問題があってN販が力を増し、自社以外の取次を排除するよう要請があったらしいのです。その後仕入れに関してはN販の意のままになってしまったのでした。ほどなく本屋は倒産。
そういう過去を考えると、大取次が2か所あるというのは書店にとって悪いことではないような気がしますよね。両社が競い合うことでいい条件を引き出せるかもとか。ただしメイン取次はTハンで補助的に使っていたのがN販でした。雑誌はTハン、コミックはN販。わが担当の文芸書と新書で言うと、K文社だけはN販で他はほとんどTハンだったけれど、明確な区別はあるようでなかったような。
いったいいつの時点でダブル取次になったのか。外商と店売の仕入を分けるためだったのかなという気はしますが真偽は分かりません。書店を立ち上げて取次から新刊書を配本してもらうには、莫大な (見当もつきませんが) 保証金が必要というのはよく耳にする話です。それを2つの取次に対して支払ったのでしょうか。100年という長い歴史のある海文堂なので、現代の常識とは違う時代に始まったことなのかもしれません。
いずれにしても、一冊でも多く欲しい新刊を両取次から仕入れることができるのは、ちょっと得した気にはなるものです。でも恩恵を受けたなあと思い出せるのはキムタクの写真集(古い話ですみません)と『1Q84』くらいかなあ。新刊の追加は減数されるのが当たり前なので、両方に発注したからといって満数入るわけでは無いですし。私は最後までせっかくのダブル取次をうまく使いこなせませんでした。
一番上手に使っていたのは児童書Tさんですね。この人はそもそも両社を競わせるなどという発想は持ち合わせていなかったと思います。業界に知られたTさんは版元の営業さんだけでなく、編集さんや両取次の倉庫の方まで味方につけて、必要な数の児童書を集めていました。どこに何が何冊あるかまで把握していたのではないかしら。すごい収集力です。販売実績に基づいて間違いのない冊数を弾きだせるのもすごい。
そういえば、2大取次以外に海文堂に納品していたのはJRCと学参のМ井書店しか思い出せないのですが、直仕入は積極的にしていたので支払先は何件にも分散していました。2階の港町グッズを担当するゴットさんはじめ、平野さんもアカヘル氏も地元の方の自費出版本を担当していた店長も、更に実用Kさんや文芸の私も直仕入の伝票をいくつか持っていました。ほかの本屋には無くとも、海文堂に行けば置いてるよと言える本を扱っていることをちょっと自慢にしていた気がします。
そして二段落目に書いた小取次を整理して行く話に戻るのですが、やがて晩年の海文堂でもまったく同じ現象が起きたのでした。つまり、まずはМ井書店を中止することから始まって、自費出版棚を廃止し、古書棚を止め、最後には港町グッズ以外のすべての直取引を解消するようにというお達しがあったのです。京都の編集グループSURE、周防大島のみずのわ出版、仙台の荒蝦夷、大阪の編集工房ノア、お隣のくとうてんの商品さえ置けなくなってしまいました。平野氏の落胆ははたで見ていても分かるほどでした。
かくて海文堂は終焉を迎えたのでありました。ダブル取次のメリットが生かされたのかどうか私にはよく分からないうちに。小回りの効く小取次や直取引をしてくれる出版社との関係が、面白い書店を作る可能性もあったけれど、ついぞ証明することが叶わなかったのでした。

松家仁之・著『光の犬』
2017年10月発行 新潮社
あー、堪能しました。441ページ。久々に分厚い単行本を読了しました。読み始めたらその世界にすっぽりとはまらずにいられない。長く付き合ううちに登場人物が他人とは思えなくなるというのも読書の醍醐味。奇もてらわぬこんなに淡々とした小説なのに、心を捉えて離しません。
松家さんがデビューしたのは2012年の『火山のふもとで』なので、まだ作家歴という意味では新人の部類に入るのかもしれません。ところがこのデビュー作で、いきなり読売文学賞を受賞してしまうんです。読売文学賞には、すでに定評のある作家に箔が付くようなイメージを持っていました。それがデビュー作品で受賞とは。ただしやっぱりなあという気もしたのです。松家さんは仕事を辞めて作家デビューするまで、新潮社屈指の敏腕編集者だったのです。今はWEBだけになりましたがあのかっこいい季刊誌『考える人』の編集長をされていた頃から、私はメールマガジンを購読しておりました。「腕のいい編集者は書ける」というのがそれ以来私の固定観念となっています。
さて『光の犬』。北海道東部の小さな架空の町枝留(えだる)に生を受けた一族の、明治から現代に至る大河ドラマではあるのですが、特別大きな仕事や歴史に残る事件にかかわった人たちではありません。どこにもいる市井の家族に起こる大波小波が、時に時代を遡りあるいは先に進んで綴られるのです。
添島家の眞蔵、よね夫妻に始まり、三姉妹(一枝、恵美子、智世)と一人息子の眞二郎に嫁の登代子。その子供である歩と始。彼らの100年余りの家族史に、私たちは立ち合い、自分の親戚であるかのように喜び、同情し、心を痛めます。あまりにも話が行きつ戻りつするせいで、先に登場人物の運命を知ることとなる辛さと言ったら。
わたしが大人になったら、いまのこの気持ちに、てきとうな名前をつけて片づけるだろう。それは絶対にちがう。だからわたしはこうして泣いている自分に勝手にのしかかってくるものを、ここに全部捨てるためにやってきた。誰にも拾わせないために。
これは少女の時代の歩の心象なのですが、この短い一文で、自意識過剰で繊細な少女像だけでなく、孤独な自分を知っている利発で多感な女の子であることが分かります。なぜか大人になると忘れてしまうこういう気持ち。誰にも拾わせない、けれど愛犬のジロだけはすべて分かってくれていると信じている歩。
『光の犬』というタイトルなので歴代の飼い犬が重要な役割を果たしてはいるものの、出番は人間たちと同じくらい。時代時代の主役と、関わりのあった人たち、その時々の北海道犬(どの犬も愛されていた)が平等に語られます。誰に対しても大きく感情移入しすぎないこういう書き方、好きだなあ。
『火山のふもとで』は建築士が主人公で、建築設計に関する専門知識が必要なほどの場面が何か所も出てきました。今回も同様で、よねの産婆の知識、歩の天文学、始の書物史等。読者にはいささか難しくとも、著者にとっては主役たちの頭の中に分け入らない限り、発言する一言さえいい加減に書けないという思いだったのではないでしょうか。
歩と始それぞれの若き日の切ない恋愛は瑞々しく、やはり恋は人生の花だなあと思うと同時に、その後の人生のなんと長いことよ。特に3人の老女を看ることになった始の諦念。犬たちであればこれほど長い晩年はなく、手もかからないのに…。著者の分身ではと思わせる、添島家最後の一人となるであろう始の晩年が、幸せであることを 祈るばかりです。
読み終わってもまた時間を遡って彼らに会いたくなる。昭和の文学を思わせる重厚な作風。早や大作家の貫禄です。新潮社辞めて小説書くらしいですよと、かつてアカヘル氏から聞いた時のびっくりと期待感。まったく裏切られませんでしたよ。
(三毛小熊猫 元書店員)
2018.5月 (44)朝礼

(44)朝礼
以前に新刊紹介のことを書きましたが、その紹介が行われる場である朝礼のことをまだ書いていませんでしたね。海文堂のあった元町商店街は朝が遅く、店の開店時間は10時半で平日のスタッフの出勤時間は一律9時半でした。早く出勤した人も私のようにぎりぎりの人も、9時半にはとにかく店なかほどの中央カウンターまわりに集合します。月曜から金曜まで、その日の担当者が中央カウンターの中から挨拶するのです。
まずは月曜日。朝礼担当はアカヘル氏。月曜は週に一度の新刊紹介の日なので、各ジャンル担当者が前週のめぼしい新刊を紹介します。最後にアカヘル氏が担当の雑誌、芸能書の紹介を兼ねて短い話をします。何の話をしてもいいのですが、本への愛情が伝わってくるような話題が多く、彼が「古書価」という言葉を使うたびに私の知らない古書の世界に思いを馳せることになりました。締めはいつも「では今週もよろしくお願いします」だったな。
火曜日は人文平野さん。プライベートないちびり話のこともあったけれど、基本は新刊紹介の増刊バージョン。一冊の本を丁寧に解説することが多かったですね。神戸の本とか編集グループSUREの本とか。熱が入って長くなるタイプだったような。
水曜は外商Hさんと海事ゴットさんが隔週に担当。ごっついHさんがご近所の猫の写真をコピーして配った時はびっくり。こういうのもありなんや。猫好きとして親近感を覚えましたよ。ゴットさんの日は全員2階に集合。この人も新刊紹介で紹介しきれなかった本やグッズを詳細に。水曜は私が定休日だったのでこの2人の朝礼は数回ずつしか聞けなかった。
木曜は7人の女性スタッフが持ち回りで担当。家族の話をする人、遊びに行った話をする人、こんなお客さんがいたという話、あっという間に終える人、笑わせる人真面目な人。それぞれ芸風がありました。
金曜は店長の日。翌週の予定をプリントし、それに沿って話を進めていました。当然と言えば当然ですが、意外と言えば意外? 店長の朝礼が最もいわゆる朝礼らしく、真面目で硬かった。時には売り上げや返品などの業務命令があり、スタッフへの要望(あるいは叱責)もあり、中間管理職の苦労がしのばれました。
私はと言えば…。7週に1回とは言えやはり苦手。できるだけ目立たないような話をしていたのですが、ある日偶然受けてしまって……。笑いを取るというのは魔物ですねえ。つい面白いネタを探してしまい、いやいやちゃうやろと自分に突っ込みまして本来の本に関する話題に戻れました。
お客様からのクレームがあればこの場で注意されてシュンとなり、お褒めのメールや手紙があればこの場で読み上げられて誇らしい気持ちになりました。当然、海文堂の閉店を突然知らされたのも朝礼でした。
上意下達だけの場ではなく、スタッフ全員が何らかの発言の機会を与えられるというのは、なかなかに民主的な職場ではあったのですね。そういう機会がありながら、危機感を全員で共有できなかったのが大いなる問題であり、海文堂の「あかんとこ」だったのでしょうね。
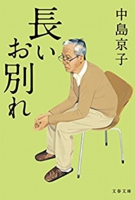
中島京子・著『長いお別れ』
2018年3月発行 文春文庫
単行本が出た3年前、いくつもの書評に取り上げられましたよね。文春さんだしこの作家なら文庫になるのは2年半から3年くらい先、と思っておとなしく待っておりました。時の経つのは早いもの。ほんと、文庫化という制度はありがたいわ。
『長いお別れ』というとやはりチャンドラーのロングセラーを思い浮かべますが、中島京子版はハードボイルドとは無縁の家族小説。認知症の始まった元校長先生の昇平をめぐる、妻と3人の娘たちの最後の10年間のおはなしです。長いお別れとは、文字通り時間をかけての少しずつのお別れ。「少しずつ記憶を失くして、ゆっくりゆっくり遠ざかって行くから」と孫のタカシは教わります。介護の場面は多いけれど、決して暗かったり悲しかったり辛かったりする小説ではないのです。女4人が初めての経験に頭を突き合わせてコミュニケーションを取り合う姿はユーモラス。ちょっと間抜けだったりしてそうそうこんな感じでものごと進んでいくよねと共感必至です。
ある日、昇平は毎年参加していた同窓会の会場にたどり着けなくて帰ってきます。次第に行動範囲が狭くなりぼんやりすることも増え、ちゃんとした応答をすることの方が減ってきます。最後まで手放さない感情は快と不快。この感情表現だけでも妻にとっては夫らしさのいとおしい名残です。
冒頭のエピソードがとてもいいのです。幼い姉妹がもらったチケットでメリーゴーランドに乗りたいのだけれど、大人と一緒でないからと乗車拒否されます。小学生の姉は「大丈夫。私が何とかしてあげる」と宣言し、ぼんやり見ていた見も知らぬ昇平に声を掛けるのです。昇平の膝に妹を乗せてメリーゴーランドに揺られる3人。幼子のぬくもりがもたらす幸福感。昇平に「快」の感情が呼び覚まされるシーンに胸を打たれます。
介護生活の根底にあるのは妻の強い決意です。私が看なくて誰が看るのという強い気持ちがあればこそ、ぶれない家での介護を実現させているのです。家族小説にありがちな、姉妹間や夫婦間の無駄な葛藤が無いのがいいな。 意地悪な人も登場しない代わりに、淡々と年月と認知症は進んでいきます。だれもがいつか経験するかもしれず避けようがないけれど、恐れていてもしょうがない老いと認知症。
何回言っても5分後には同じことを尋ねられ、機嫌の悪い時は薬を飲むことを断固拒否し、ものを失くし、さっきしたことを思い出せない。考えれば気が滅入りそうな出来事なのに、中島京子の手にかかるとなんだかコントのようで笑ってしまう。独身娘の見合いの心得や米国旅行中のパーティー、孫とのとんちんかんでシュールなやり取り、妻の網膜剥離など、家族のエピソードが面白おかしく中島節が冴えわたります。
『イトウの恋』以来の中島ファンなので早く読みたかったのですが、単行本発行時よりも今こそが私の読み時だったなと感じています。時宜にかなった、と言うべきかな。それは今の私がまさしく介護のとば口に立っているから。
どこにいても「そろそろ帰ろうかな」と言う昇平。彼が帰ろうとしているところはどこなのか。そもそも帰るとはどういう意味なのか。いつか私自身が望むことになるかもしれない帰りたい場所。
小説は確かに恵まれた状況での自宅介護だけれど、それを差し引いても後味の良い読後感にプラス実践例としてのお役立ち情報も。万人におすすめの良書です。
(三毛小熊猫 元書店員)
2018.4月 (43)招待・説明会

(43)招待・説明会
今でもあるんでしょうか、出版社の招待って。これは各版元に対する書店の売り上げ規模によって違ってくるので、本屋さんごとに答えは違ってくるでしょうね。海文堂入社以前にいた書店では、時代的なこともあるでしょうがたびたび大出版社からの招待を受けていました。もう20年も30年も前の話です。
当時はポスレジではありませんでしたから、スリップのうしろ側の方(売上スリップ)をちぎってまとめたものを各書店が各出版社に郵送していました。結構たくさんの出版社に分類していた記憶があります。月に一回、スリップ送付だけを請け負ってアルバイトにしている方がいたりするほど、なかなかに煩雑で面倒な作業だったのです。それによって出版社はどこの店がどれだけ多く自社の本を販売してくれているか判断します。大出版社は上位書店のランキングを公表していましたが、当時の上位書店さんでもその後残念ながら廃業されたお店は多くあるんじゃないでしょうか。
招待にもいろいろありました。遠方の書店は宿泊も込みで、東京の有名ホテルでの立食パーティー。作家さんを囲む会。新雑誌や新企画の説明会を兼ねた食事会。説明会だけの時はケーキのお土産が付いていたり。映画化された原作の版元は試写会のお誘い。時には海外旅行にご招待などという豪勢なのもありました。出版社の目的はもちろん販売促進だけど、それだけではなくて、いつもお世話になっている書店にお礼の機会を設けたいという意味もあったように感じます。そういう商習慣のまだあった時代というか。出版社と書店双方に勢いがあり、今よりはるかに大きなお金が動いていた頃のことです。
ポスレジが導入されてからは、出版社はポス導入書店だけのデータで判断するようになり、導入していない海文堂のような弱小書店は次第に相手にされなくなりました。某出版社からスリップ送付を謝絶されたこと、店長はずっと怒っていましたっけ。
もちろん海文堂の最後の10年にもいくつものご招待や説明会はありました。売上スリップの枚数ばかりではなくて、古くからのお付き合いがあったからこその招待だったと思います。毎年呼んでいただいたのは地元新聞社。私が一度だけ参加した時は映画を見て中華料理をいただいたような記憶が。こちらには平野さんが行くことが多かったのですが、参加者の多くはオーナーやその家族。現場の話の出来る雰囲気ではなく、ずっと場違いな気分でいたようでした。
実は私が店長に感謝していることのひとつが、ある食事会付き説明会に行かせてもらったことなのです。その名も「本棚の会」という素敵な名のI書店の会合です。買い切り版元ゆえ常備している店はそう多くありませんが、海文堂は昔から最後までコーナーを設けてI書店の本を販売していました。その長いお付き合いあってこそ、京阪神の大書店を差し置いて会のメンバーに入っていたのでしょう。
私が海文堂に入社して間もない頃、ここでやっていけるのか自信も無くて不安な日々を過ごしていたのですが、ある日店長が本棚の会に誘ってくれました。私でいいのかなと思いつつ会場に入ると、海文堂の中途採用新人が来たということで、版元の方だけでなく他の書店さんからも下にも置かぬ扱い。本屋歴が長いだけの私を丁寧に扱ってくれる場があるのだということに大変感激したのでありました。この職場で働くことによって自分が底上げされたのだと、気付いたのはずいぶん後のことでしたが。おかげでなけなしの自信が少し取り戻せたのです。あのタイミングで誘ってくれた店長には感謝です。
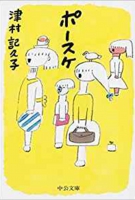
津村記久子・著『ポースケ』
2018年1月発行 中公文庫
津村記久子という作家について、お仕事小説を多く書いている人と紹介されることがあるかもしれませんね。いわゆるお仕事小説を私の定義で言うと、主人公が仕事を続ける中での様々な困難を経て、職場や社会の裏と表を知りながら成長するお話、って感じでしょうか。でもこの『ポースケ』に出てくるいくつかの職場は、そのようには描かれません。それでもその現場がどのような労働環境でどんな物言いをする人がいて、登場人物がどのように感じているのかは、痛いほど分かります。著者が心を寄せて書く主役は仕事ではなく働く人。その姿勢が私はとても好きなのです。
『ポースケ』は芥川賞受賞作である『ポトスライムの舟』から5年後という設定。ナガセ、ヨシカ、そよ乃、りつ子の4人にまた会えるのです。この、また会えるというのが好きだなあ。登場人物たちがある小説の中だけにいるのではなくて、今もその続きを生きているような気がするでしょ。なにかの折にご一緒した人たちの消息を知って安心するような気持。奈良に行けば本当にヨシカのお店「ハタナカ」があってみんなに会えるのではないかとかね。
はい、今度の舞台はスコーンと紅茶が美味しくて食事もできるカフェなのです。ヨシカが会社を辞めて自分で始めたお店。ここに出入りするスタッフやお客さんの群像劇でありつつ、店のイベントである「ポースケ」の発案から開催日までの記録でもあります。
ごく普通のカフェにやって来るごく普通の女性たちなのに、彼女らの日常はなんともさまざまです。珍しい職業やすごい才能の持ち主なんていないにもかかわらず。11歳から50台半ばまでの、実際に自分の身近にいそうな人たち7人の視点でそれぞれの章が語られています。職場の同僚に違和感を持つОL5年目や、パワハラで負った心の傷からまだ立ち直れない28歳。娘の就活に翻弄されるカフェのスタッフや、小学5年生が垣間見る大人の世界。そしてカフェの主人ヨシカが前職を辞めた顛末も。7つの短編がカフェで緩やかに繋がっているところが心憎い。
私が最も心打たれたのはゆきえとぼんちゃんのカップルの話。ゆきえに別れた男がこっそり付きまとっていて、決して暴力的なのではないけれど高圧的な手紙を置いていく。思わず書いたゆきえの返事。
『あなたは日常的に私にばかだと言っていたので、そういう対象がいなくなって手持ち無沙汰なだけじゃないでしょうか?』
この一文で2人の関係がよく分かります。自分が優位に立たなければ気が済まず、恋愛にすらそれを持ち込んで人前で貶めることが親愛の証のように思っている男。別れようとしても懐柔してくる男に、さらに傷つくゆきえ。激しい怒りで目の前のコップを割ることもできたけれどそれを我慢し、意志力を使ってコップを磨くことを選んだゆきえ。そのニュアンスを、新しい彼氏のぼんちゃんは理解できる人だったというのが私もうれしい。 「重要な事実は、苦しみではなく、屈辱である」。これは津村さんが日経新聞のコラムで引いていたシモーヌ・ヴェイユの言葉なのですが、これこそ津村記久子の核心なのではないかしら。働く場に限らずあらゆる場において、屈辱の中にいるべきではないと彼女の小説はいつも教えてくれます。その強い意志が、お仕事小説の範疇に入らないと思う理由なのかもしれません。
(三毛小熊猫 元書店員)
2017.12月 (42)作業場

(42)作業場
海文堂の店舗は自社ビルだったので、テナントとして借りている店舗とは違ってずいぶん余裕のある店の使い方をしていました。私がそれまで働いてきたテナントの店舗は面積のほとんどを売り場で占めていたのです。隅っこの小さな事務スペースは2台の机と棚だけでいっぱいで、カバーや紙袋の包みとデッドストックなどが積まれている大変窮屈な小部屋でした。
当然それらの店では書籍や雑誌の開梱作業を売り場で行っていたのですが、海文堂では売り場の後ろに広がるバックヤード、通称作業場が荷開けの場となっていました。向かい合わせにした机で大きな島を作って、その上に段ボール箱を載せて開梱すると断然腰が楽なのです。書店員を悩ませる腰痛の原因のひとつは、床に置いた箱を屈んで開けることにあると思うのですが、それしか知らない私にとって腰を伸ばして開梱できるというのは感動ものの作業風景でした。
そこで箱から出した書籍はジャンル別の仕分け棚に一時保管され、それぞれの担当者がそれぞれの台車に乗せて売り場に運びます。この規模の店(1,2階合わせて200坪余り?)で台車やブックトラックが人数分あることも、仕分け棚があることも机がいくつもあることも私にはびっくりです。
作業場は荷開けの時間帯以外はガランとしていて、中央カウンターに入るシフトじゃない時の店長がひとりで事務机に就いていることが多かったですね。店長はああ見えて、実は孤独を愛する人なのです。たぶんなかなか居心地のいい場所だったんじゃないかな。私はと言えば、できればお客様から声を掛けられずにスリップ整理がしたい時などに作業場の机を利用しておりました。まったく書店員の風上にも置けませんね。
この広々としたバックヤードがいつも広々としていたわけではありません。教科書販売の時期には余分な机を2階に上げ、そこにもぎっしりと段ボールが積み上げられました。思えばそのための広いバックヤードだったのかもしれません。
作業場での最大の思い出は、2度の慰労会に使われたこと。1回は棚卸しの後で。『みをつくし料理帖』の著者、髙田郁さんが海文堂の棚卸しにアルバイトに来てくださって、その打ち上げをした時。もう1回は2013年9月末で閉店してその片付けも終わり、正真正銘最後の慰労会をした時。
ゆかりの方々から「お疲れさまでした」との手紙と共にいただいたお酒やビールを広げて、作業場は即席の宴会場になりました。最後の最後まであたたかい応援メッセージをくださった方々のお心づかいに胸が熱くなり、今も感謝の気持ちを持ち続けています。その節は本当にありがとうございました。みなさまのことはちゃんと覚えていますからね。
バイトくんたちは送ってくださったカンパを元手にお菓子やおつまみの買出しに行ってくれました。激しい労働の後なので酔いも早く、すでに出来上がっている人もいます。外商Hさんはその辺に転がってぐうぐう寝てしまいました。売り場と違って作業場の床はコンクリート、いわゆる“たたき “です。何とか段ボールを下に敷こうと思ってもHさんはでかくて重い。冷えてどうかなってしまうのではないかとオロオロしていると、店長は言いました。「酔っぱらいは簡単に死なへんの」さすが、名言ですね。
思えばバイトくんも含めてスタッフ全員が一堂に会したのはこの時が初めて。くとうてん社長によるその時の記念撮影が、全員揃った最初で最後の写真となりました。みんなどこか晴れ晴れとした笑顔でしたよ。
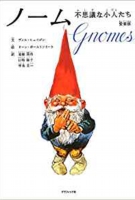
文 ヴィル・ヒュイゲン 絵 リーン・ポールトフリート
訳 遠藤周作 山崎陽子 寺地五一
『ノーム 不思議な小人たち 新装愛蔵版』
2017年8月発行 グラフィック社
私がよく利用するのはわりと広くてきっちりジャンル分けしてあるタイプの本屋さんです。たいていこれを買うぞと決めて出かけるので、目指す本が思っていた場所にあると大変気持ちがよろしい。そして私が読みたいと思いそうな本もその周辺に集まっていて効率もよろしい。思えば海文堂閉店から4年半のあいだ、私がこの書店で目にした本は文庫と文芸書だけではないか。ものすごく狭い範囲の本しか見ていなかったのですね。本の世界は限りなく多様で広いのに。かと言ってすべての棚を見てまわっていたら何時間あっても家に帰れない。
で、そんなに広くない、あるいはきっちりジャンル分けしていないタイプの本屋さんにごくたまに出かけます。そんな1軒で見つけたのが今回紹介する本。いつも行く店のいつものコーナーでは決して見つけられなかった本です。
実はずっとずっと昔、働いていた書店の美術書コーナーの面陳棚に常時この本があったのです。当時はサンリオ出版から出ていてもう少し大判でした。欲しいなあと思っていたのだけれど、いいお値段だしいつもあるからまあいつかねと思っていたら、ある日ぐんと値上がりした補充品が入ってきてショック。高くなってすぐ買うのはあまりにも悔しいと思いついそのままに。転勤し働く店が変わってからは見かけることもなくなりました。なので何十年ぶり!の再会を果たせ、しかもお安くなっていたのは実にうれしい。
ではようやく本の紹介を。B5判ソフトカバーの絵本『ノーム』は、北アメリカとヨーロッパに生息するノームという種族を文化人類的に考察したものです。ノームは身長15㎝で平均寿命400歳の、とんがり帽子をかぶった人型の妖精なのですが、人間にとっての彼ら、ではなくノーム自体の歴史から生態、生活、文化、社会に至るまで、彼らに取材したという内容がこれでもかという程詳細に書かれています。著者のヴィル・ヒュイゲンは医者でもあるので、身体の生理機能や病気の治療法、老化現象などの記述も科学的で、思わず信じてしまいそう。
私が一番好きなのは住宅についての項。松の木の根の下に建てられた住まいはほとんど人間の住宅と変わらないけれど、随所に彼らなりの工夫が施され、スカンク用の落とし穴があったりペットの野ネズミ用のかごがあったり。ちゃんと井戸やトイレや煙突の原理も描かれています。仲良しのモグラやウサギが建築を手伝ってくれるとは心強い。他の動物との関係はいかにもありそうで、人間の知らぬ世界の存在があってもいいような気がしてきます。惜しげもなく大量に精密に描かれた絵がリアルなんだけれどなんとも心地よいかわいらしさ。文字は多くても総ルビだし分類すれば児童書になるかな。少なからぬ児童書がそうであるように、この本も児童書コーナーだけではもったいない。私のような喜ぶ大人がいっぱいいると思うのです。まったく、ずっとこのまま浸っていたいような世界観なのです。
さて、本書との感動の再会を果たしたのは阿倍野を見はるかすビルに隣接する、本と雑貨が半分ずつの今どきのお店。翌日から始まる古本市の準備で忙しいだろうに、担当Kさんは私との会話に時間を割いてくれたのでありました。
全国の書店員さん。こんなふうに何気なく置かれた本が、お客の琴線に触れて勝手に感動を与えていること、きっとあるんですよ。手ごたえの見えなさにやる気を失うこともあるでしょうが、負けずにがんばって。
(三毛小熊猫 元書店員)
2017.11月 (41)ご近所

(41)ご近所
海文堂書店は元町商店街の中ほどにありました。元町商店街は1番街から6丁目まで徒歩15分ほど、1㎞あまりのアーケードが続く神戸屈指の商店街です。三宮センター街に賑やかさでは譲るものの、かつては新開地と並んで神戸随一の繁華街だったそう。わが母などは戦後すぐの元町がジュラルミン街と呼ばれて栄えていた頃を懐かしんでおります。ハイカラなイメージは保ちつつ、今はやや寂れ気味。そういう歴史を99年間見てきた本屋なのでした。
元町駅を南に下りて大丸さん前からアーケードに入るとそこは1番街。商店街の人通りも多く、このあたりは三宮に遜色ありません。そこから西へ進むにつれて、なんとなく道を広く感じてくるんですね。次第に空いて来るというか…。海文堂は3丁目まんなか辺、その空き加減のちょうど境目あたりに店を構えていたのでした。
神戸の名所のひとつ南京町広場は南東に5分ほど。春節などのお祭りの日は大変賑やかでした。獅子や歴史上の人物の行列が商店街を練り歩きます。独特のリズムで鉦や銅鑼を打ち鳴らし、ご祝儀を貰うために商店の前でしばし演技を行います。最後におひねりを獅子が口で捉えるまで目が離せません。あの音を聞くとワクワクしてつい店のウインドウ越しにパレードを見物したものでした。
冬の神戸のビッグイベント、ルミナリエ。阪神大震災の年の12月から始まって、今や全国でやっている光の祭典のさきがけとなりましたね。メイン会場は三宮なのですが、その会場にたどり着くまでのルートが決められていて、始まりは元町駅周辺。土日などはものすごい人出が行列をさらに長くして、最後尾が海文堂周辺まで来たこともありました。夕暮れが近くなると、トイレが混むわ混むわ。本屋としてはあまり恩恵のないイベントではありましたが、まだ見ていない人がおられましたら是非一度は経験してください。一見の価値はあります。美しいです。感動します。始まってすぐの平日がおすすめです。
元町駅近くにはJRAの場外馬券売り場が2か所ありました。JRで通勤していた時も神戸高速で通っていた時も、海文堂までの通勤路にJRAがありました。中に入ったことはないのですが、馬券を買いにやって来るおじさんたちのいでたちがあまりに特徴的なので、観察して一人で楽しんでいました。季節を選ばず、着ている服の色がくすんだ黒かくすんだ茶、くすんだグレー、くすんだ紺のいずれかなのですね。競馬のある日だけ海文堂にやって来て、編集工房ノアなどの渋い本を買って帰る方もおられました。競馬と文芸書は結構相性がいいのかもしれません。
商店街のご近所さんでよく来店してくださった方は、長くこの地で商売をなさっているお店の方が多かったですね。老舗の茶舗や和洋菓子店のオーナーの方、有名子供服のデザイナーの方、長くやっておられるお蕎麦屋さんや床屋さん。老舗ではないけれど、忘れてはならないのがお隣のビルのくとうてんさん。「一緒に何かやる」という種類のお付き合いができたのはほんとによかったと思います。こちらは廃業してしまったけれど、ありがたいことに今もこのような場所を提供してくれて何かとかかわってくれています。ご近所のご縁、侮りがたし、です。

吉田篤弘・著『金曜日の本』
2017年11月発行 中央公論新社
前回同じ著者の『京都で考えた』を取り上げたので、次はこの本を紹介しないわけにはいきません。同じ月に出版されて表紙は色違い。エッセイの後に短編小説がひとつ載っていてページ数も同じ。顔がそっくりで性格の違う双子本なのです。兄本は思慮深く行動力があり、弟であるこの本は一見クールで実は情が厚いと見受けました。
タイトル通り京都で考えたことを記した前者に対して、こちらは篤弘氏の幼少の頃の記憶の断片が短い章立ての中に簡潔に語られたもの。といってもいわゆる自伝的小説ではありません。ご自分のルーツがテーマのひとつだった『木挽町月光夜咄』がフィクション寄りのエッセイとも言える手の込んだ作風だったのに対して、こちらは正反対の淡々としてややぶっきらぼうな、これまでの著者とはまったく違う文章で書かれた記憶の点描なのです。
とびきり大きな邸宅に住む同級生K君の家で、持ち帰りピザを食べながら「どんな本を読むの?」と尋ね合った時の篤弘少年の答え。
「どんな本でもいいんだけど」とひとまず答え、それから言葉に詰まってしばし考えた。何と云ったらいいのだろう。
自分が読んできたいくつかの本を思い浮かべ、それらの本に共通するのは何かと考えて、「気持ちがあったかくなるもの」と答えた。
数えきれない本の中から自分で何冊かを選び、 ここではない場所に出かけて行き、さらにここではない場所に連れて行ってくれる本を読むこと。読書の醍醐味を教えてくれると同時に、自分と本との歴史をたどりたくなる幸せな1冊です。ラストの、著者が「小説家になりたい」と明確な輪郭を持つに至ったエピソードが素敵。この本も前作同様、篤弘ファンにそっと手渡されたかのような、心のこもった小さな本なのでした。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.10月 (40)いただきもの

(40)いただきもの
医療機関ならいざ知らず、本屋にいただきもののイメージってあんまりありませんよね。ところが海文堂にはしばしばいただきものが届けられました。いくつかの出版社は盆暮れに熨斗付きの進物を送ってくださり、営業さんは時に手土産を持って来られます。イベントや商品販売でかかわった方々がごあいさつ代わりにと何かしら持ってきてくださることもよくあり、またスタッフが旅先のお土産を買ってくることもあります。いずれの場合も中身はほとんどお菓子です。東京で行列の店からスーパーの袋菓子まで、時にはバナナから自家燻製チーズまで、いずれもありがたく頂戴しました。顧客の方が、美味しそうだったから買ってきたよなどと言われることもたびたびありました。
そういういただきものたちは、2階の食堂(食事室)のテーブルに置かれます。その日出勤している人で食堂に出入りした人が適当にいただくことになります。平日の第1陣は12時からの昼休憩組。このメンバーは取りっぱぐれがありません。ゴットさんやアカヘルさんのように甘いものを食べない人もいるので次の12時45分からの第2陣もまず大丈夫。1時半組や夕方からのバイトくんたちになるとちょっと怪しくなってくる。まったく食堂に現れない人はいただきものがあったことも知らないまま帰っていたのかも。
私は12時組だったので、お昼ごはんの後のデザートとして甘いしあわせをもれなくいただいておりました。お盆や暮れは特に、毎日のように続けて恩恵をこうむったものです。私同様12時組の中央カウンターYさんは、箱開けから棹ものやロールケーキの切り分け、生ものの保管、重複した時の順番決めなどを進んでしてくれていました。私は密かに菓子奉行とお呼びしていましたが、ここには鍋奉行のような揶揄は含まれていませんからね、念のため。
そのお菓子の件で、めずらしく平野さんがプリプリしたことがありました。この人の昼休憩は1時半からのことが多いのですが、食堂のテーブルに置かれた菓子箱を開けてみると中は空っぽ。自分の分がなかったから怒ってるんとちがう、最後の1個を取った人は箱を処分するべきではないのかと。いやあまったくその通り。誰やそんなことするのは! いつも穏和な平野氏が怒っていたのはマナーの問題なのでありました。ちなみにこの時のお菓子は、平野氏関連の方からいただいた氏の好物の阿闍梨餅だったのでした(ごめんねしょうもないこと覚えてて)。
いただきものが多かったのは、ほかならぬ海文堂だったからなんですね。店長や児童書Tさんをはじめ個人的にプレゼントしてもらえるスタッフがいたのは、その分彼らがどなたかのお役に立っていたからです。単なるビジネス上のいただきものという以上のメッセージを受け取りながら、私たちはご相伴に預かっていたのでした。

吉田篤弘・著『京都で考えた』
2017年11月発行 ミシマ社
クラフト・エヴィング商會の物語作家吉田篤弘氏による久々のエッセイです。さまざまなテーマを縦横に語るいわゆるエッセイ集とは違って、タイトル通り京都で考えたことに特化した本です。といっても京都の町がいろいろ出てくるわけではありません。篤弘さんの頭の中と京都との関係が綴られているのです。
これはやはり篤弘ファン必読ですね。むしろ、篤弘氏の読者にだけこっそりと差しだされた私家版の趣です。いつものようなサービス精神あふれる開かれた本ではありません。日頃から氏の文章に触れている身にこそ、より親密に感じられる「小さな本」なのです。
いまいるところから外に出ていくことーそれがつまり考えるということで、外に出ていくのは、これまでの自分の認識に「本当にそうか」と疑念を抱くからである。
その「外」はどこでもよく、自分のテリトリーや情報から距離を置くこと。二子玉川で、東京駅で、京都で、「アウェイの贈り物」を受け取り、歩きながら考え原稿を書く。書きながら考える。
篤弘さんの小説の多くはストーリーが波乱万丈だから人気があるのではないし、文体が斬新だから評価が高いというのでもないですよね。ならば何が良くてこれまで読んできたのかと自問してみました。そうか、主人公は行動するよりもいつもなにがしか考えていて(だからちょっと優柔不断で)、そのぐだぐだ考えたことを誰かに話しては時に共感され時に批判され、そのやりとりが私には心地良いようなのです。それはおそらく篤弘さんの思考にほかならず、小説家であることのモチベーションは彼が今考えているまさにそのことにあるのでしょう。そして考えている頭の中には巨大な怪物がいたのです。
(前略)、どうも自分にとって小説を書くという作業は、個別の獲物をひとつひとつ撃ち落として剥製にしていくのではなく、全貌の分からない巨大な怪物に無謀な体当たりをして、少しずつ怪物の一部分を採取しつづけているのではないかと思うようになった。
一生をかけて内なる怪物の全貌を明らかにしてゆく仕事。素晴らしいではありませんか。表現者はみな怪物を飼っていて、止むに止まれず我が身を削り取って創作しているのでしょう。作家の頭の中がちらりと垣間見えた気がしました。
中で「なぜ書店に行くのか」という問いが立てられています。篤弘氏の答を大雑把に言うと、世界という名の怪物が手に取りやすい形で並べられているから、というもの。本屋の側からいうと「なぜ本屋に来てほしいのか」という問いになりますね。答えはすべての書店員がそれぞれに持っているはず。多種多様な小売りがある中で、とりわけ商うものに誇りを持つ人が多いと感じる書店員のことです。その答えにこそ本と本屋に対する理想があることでしょう。あなたのお店を訪ねた篤弘氏が、あなたのメッセージを密かに受け取っているかもしれませんよ。
最後に「スリンク」という題の掌編小説がひとつ収録されています。京都で考えて生まれたこの短いお話、つまりこれこそ氏が京都に行く理由なのでしょう。京都の変わらなさの良さは、アウェイの人にこそよく分かることなのですね、きっと。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.9月 (39)年末商品

(39)年末商品
年末商品が書店のメインコーナーを占拠するシーズンとなりました。手帳、日記帳、カレンダー、家計簿、年賀状素材、暦、他にもあったかな。あ、百人一首も置いてた。年中置く商品ではないので特設棚に置くことになり、すると普段その場所で行っている企画フェアができなくなってしまいます。早いものは8月末から入荷し始めるものもあって、実に4か月余りも年末商品に占領されるのです。すぐに売れ始めるわけでは無いのに請求はその月に来ます。となるとまずは店頭に出さざるを得ないんですよね。
これが普通だと思っていたのですが、海文堂は違っていました。こんな年末商品まだ暑いような季節に売れるわけがない。だから取次さん、秋が深まるまで送って来んといて。それが無理なんやったら送っていい代わりに延勘にしてんか、と。これは私の想像上の会話ですが、とにかく年末商品の一部だか全部だかは入荷伝票を別にして「書き替え」をお願いしていたようです。商品は作業場に梱包ごとストックし、店頭に出す日は毎年11月1日と決まっていました。
手帳、日記帳、家計簿の担当は店長。東入口と階段下のフェア台で展開し、カレンダーは児童書Tさんが中央カウンターで、年賀状素材、暦は実用Kさんが実用書棚の一部と西入口フェア台で管理していました。
10月になると手帳はどこ?と聞いて来られる方もおられましたが、毎年のことなので割と周知されていたと思います。他の書店さんはもちろん文具店や百貨店、スーパーもそういったコーナーを作っています。決してすばらしい品揃えとは言えないアイテム数にもかかわらず、海文堂のお客様は毎年ここで買ってるから今年も、という方が多かったように感じます。レジIさんから100円ショップでも売ってるよと教えられ、ものが違うとはいえあまりの価格の差に、思わずそちらで購入してしまった私です(ごめんなさい)。
売れ方で気付いたこと。日記帳の複数年もの(3年日記や5年日記)はなぜか高齢者、または超高齢者の方が主な購買層であること。あと5年大丈夫ですかと言いたくなったりして。
他に、暦と家計簿は安い方から順番に売り切れること。暦は300円の、家計簿はB5のクロスステッチの表紙のが最安でした。中央カウンターで仕事をしていると、日に20回は「かわいー!!」の声を聞きました。岩合さんの猫カレンダーのせいです。でも買ってくださるのは顧客の方ばかりでしたね。
そして年始の15日にはすべて取っ払って、新たな企画フェアが始まります。やはりフェア台として使う方が海文堂らしいなと思っていました。いつもと違うものを売るのは楽しいけれど本当のところ、本ではない商品をなぜ本屋で取り扱うのかよく分からない。出版社が発行しているし古くからの慣習なのでしょうが、その規模は今後縮小して行くかもしれませんね。

角田光代・著『笹の舟で海をわたる』
2017年7月発行 新潮文庫
私は角田さんの良い読者とは言えないけれど、あ、これは読みたいなと思うものが時々あります。『ツリーハウス』しかり『笹の舟で海をわたる』しかり。共通するのは昭和の初めから現代に至る大河ドラマ的な要素がありそうな作品。話に聞いてきた両親若かりし頃の日本について、知識を補強したいと思っているのかもしれません。
『笹の舟で海をわたる』の主人公左織はある日、学童疎開先で一緒だったという風美子に声を掛けられ、記憶にないまま親しく行き来する関係になります。風美子が左織の夫の弟と結婚するに至って義理の姉妹となり、親族として深くかかわって行きます。料理家として成功した風美子は次第に家族同然の扱いとなり、左織と関係の良くない娘は風美子にばかり懐き、左織の孤独と違和感だけが大きくなって行きます。自分からすべてを奪っていったのは実は風美子なのではないか。
現在と過去が交差し、戦時中から終戦後、古いものが忌むべきものであるかのように見えた高度成長期、バブル崩壊と、その時代時代の世相を左織一家がやり過ごしてゆく姿に既視感を覚えます。その中で明らかになるのが左織の姿勢。あらゆることを自分で考えず、人の言うまま旧態の価値観のまま受け入れる、頑固というのではなくて常に違和感を覚えているけれど成すすべのない女として描かれます。パワフルで開けっぴろげで世渡りに長け、幾分胡散臭い風美子の方が俄然主人公に相応しい人物だとは思うのですが、そこが角田さんの小説です。風美子の嘘か本当か分からない手練手管を前に、神か鬼か天災に感じるような畏怖を抱くようになる左織の視線から描かれるゆえに、風美子の本心が明らかになることはありません。風美子が受けた疎開時代の絶望的ないじめさえ、左織は本心から信じていいのか判断しかねます。そこにミステリーを読むような怖さも潜んでいるのです。
キーワードの一つは記憶のあいまいさ。目立つせいかとことんいじめられた疎開中の風美子は、いじめた子供たちのその後を見てみたいと言い、微かに誰かのいじめに加担した記憶のある左織はそんな風美子を恐ろしく思います。ところが「同窓会」で再会したいじめっ子たちは、誰一人いじめのあったことなど覚えていないのです。
もう一つは母子の確執。弟ばかりを愛し新しい考え方について行けない左織を娘が拒否して出てゆく時、左織は全く理解できずまたも違和感だけが残されます。よくある娘から見た母との確執ではなく、母から見た娘との確執なのです。
まあたらしい団地はまばゆい未来のようだった。あのころまばゆかったのは未来だったのに、今、過去になった時間が光を放っているように左織には感じられる。
『対岸の彼女』で直木賞を受賞する前、何度か芥川賞候補となった角田さん。ストーリーの面白さだけで読ませるのではなく、このようにはっとさせる美しい文の書き手でもあります。『ひそやかな花園』にも通じる記憶と家族の歴史。最後までミステリアスな空気を残したまま二人の女の関係はまだ続いて行くのでした。ずっしりとした読み応え。過去を振り返ってみる年齢に達した方におすすめです。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.8月 (38)書くこと

(38)書くこと
海文堂が私の以前の職場と大きく違っていたのは、「書く」機会の多さでした。折にふれて短い文を書く機会を与えられ、書くことが平気な人も苦手な人も、大いに鍛えられました。
各担当が発案したオリジナルのフェアを毎月交代で行っていることは面接時に聞いていたのですが、その都度企画書を書き、フェアが終われば売り上げや感想、反省などの報告書を書いて提出することもセットで行われていました。それってフェアが、意義や思い入れや勝算を勘案したうえで決定したものであるかのように書く必要が生じるってことではありませんか。ただの思いつきにもかかわらず。ただ実際に書いてみると、企画書はそのままフリーペーパー「海会」に掲載されるフェア紹介原稿になり、上司に出す企画書というよりはお客様に向けて広告文を書くような楽しさがありました。短い文章でどんなフェアをするか、どの本が目玉かを書き、それが活字になってお客さまに配られる。私のようなワープロ以前の人種にとってそれは快感とも言える出来事でした。対してフェア後の報告書は……。反省と愚痴の報告文ばかり書いたような気がします。
月刊「海会」にはフェア紹介文のほかに店長、平野さん、ゴットさんが連載を経験しています。担当持ちでないスタッフやバイトくんが持ち回りでコラムを書いたこともありました。
入社して慣れた頃には店長から「海文堂に入社した感想を書いて」と言われ、生意気で偉そうで本音満載の、今ならとても書けないような作文を提出したことがあります。社長から丁寧なご返事をいただき、今読んでも赤面ものです。たいして若くはなかったですが、まあ若かったからということで許していただきたい。こんなふうに海文堂にはスタッフとオーナーがやり取りする風土があるのだなと思ったのですが、はて、他のスタッフも書いたのかな。
海文堂はいつ頃からか神戸新聞社といい関係を築いていました。何かにつけて取材してくださり、コラムやコメントを任せてくれました。最初は平野さんが、あとを継いでアカヘル氏が、他店の書店員さんたちとともに神戸新聞に連載した本に関するコラム。この2人は元々書ける人だったから長く続けることが出来たのですが、プライベートな時間を削って納得のいく文章を書くというのは「元々書ける人」という言い方だけでは済まされないなかなかに大変な作業だったことでしょう。でも新聞という場で公表したからこそ実力が証明できたのだからそれはとてもよかったと思いますね。平野さんはお笑い路線、アカヘル氏は私小説を思わせる作風でした。
私と文庫Hさんが他店さんと交代でコメントを書いたのは「文庫新書ベストセラー」。たった66字でベストテンを紹介できるんかいなと思ったけれど、結構書けるんですね、いろんなことが。これは削ぎ落して書く訓練になりました。
「ほんまに」では店長、平野さん、児童書Tさん以外にも、イシサカゴロウ画伯による似顔絵入りで、女性スタッフが短いエッセイを書いたこともあります。書くことへの抵抗感を無くし、下手なりに書かせてくれた店長や編集の方、そして下手なりの文を読んでくださった各位にお礼と感謝を申し上げます。

佐藤文香・編『天の川銀河発電所 Born after 1968現代俳句ガイドブック』
2017年9月発行 左右社
賢治やタルホを連想させるかっこいいタイトルですが小説ではありません。副題にあるように、1968年以降に生まれた54人の俳人の句を集めたアンソロジーであり、彼らの句の何がいいのか、どのあたりが注目されているのかを編者及び対談者の声で説明してくれる俳句入門書なのです。編者の佐藤文香さんご自身が1985年生まれで今年32歳。俳句というとイメージする高齢の俳人ばかりではなく若い方々もたくさん参入していて、これまでにない感覚の俳句がどんどん生まれている。それを多くの方に知らせたいという、佐藤さんの熱意がびんびん伝わってくる良書です。
編集の仕方がユニークです。54名を「おもしろい」「かっこいい」「かわいい」の3つの章立てに分類しているのです。それぞれの章に佐藤さんがこの人と思う12名の39句ずつと、特に今が旬と思われる9名の81句ずつが俳人別に掲載されています。これがちょうどよい数で、その人がどんな作風なのか何となくわかる分量なんですね。
この「おもしろい」「かっこいい」「かわいい」の分類について、「きれい」を加えることはあえてしなかったそうです。きれいなうまい俳句を書く以上の人こそ俳句作家と呼ぶべきであるという主張です。
「おもしろい」は文字通り面白くて、あ、こんな表現ありなんやと驚きの句がずらり。
広い田に引用されていく早苗 福田若之
日の春をさすがいづこも野は厠 高山れおな
姿見を飛び出す頭夏兆す 黒岩徳将
「かっこいい」は私には現代アートのようでちょっと難しい。
或るひとの今は生前竜の玉 藤田哲史
くろあげは時計は時の意のまゝに 高柳克弘
鶺鴒がとぶぱつと白ぱつと白 村上鞆彦
「かわいい」は、自分の形式やスタイルや自分自身を疑っていない人、のことらしい。
小鳥来て姉と名乗りぬ飼ひにけり 関悦史
たどりつくところが未来絵双六 津川絵理子
くすぐるのなしね寝るから春の花 長嶋有
海を出てゆく朝日のきわを見るように、枇杷の葉の擦れる音を聴くように、俳句を感じてもらえないでしょうか。細かすぎる話やどうでもよさには、ウケてください。高度な言葉の技術には、大きな拍手をお願いします。
まえがきもあとがきもコラムも対談も、佐藤さんの俳句愛があふれています。もうひとつだけ、このサイトに相応しい引用を。書店員さん、司書さんへ。
この本を、俳句の棚以外にも置いてみてくださいませんか。たとえば、サブカルのコーナーや、エッセイのコーナー、音楽の棚でもいいです、よろしければ「桜前線開架宣言」とセットで、紛れ込ませてみてください。
紫陽花は萼でそれらは言葉なり 佐藤文香
好感度の左右社さん発行だし装丁も素敵だし、売れるといいなあ。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.7月 (37)道案内

(37)道案内
商店街や地下街を歩いていて目的の場所が分からなくなった時、どこで尋ねますか? 駅や公共の建物を尋ねるなら通りがかりの人でよいけれど、このあたりにあるはずのケーキ屋さんだとか、オープンしたばかりの雑貨屋さんを探しているのなら、知っている人は限られますよね。おしゃれな服屋さんや飲食店にわざわざ入って尋ねるのはちょっと抵抗があるしな。私が尋ねるんだったら間口の狭いたばこ屋さんかな。地元のことをよく知っておられそうでしょ。
それがね、あたりを見回して本屋があったら、ここで聞いてみようと多くの人は思っちゃうようなのです。私が勤めた書店の中でも、百貨店やテナントビルの時はさほどではなかったけれど、地下街と商店街はお尋ねが多かった! あらゆることを尋ねられましたよ。そうと分かってではないと思うのですが本屋は正解です。必ず地図があるんですもん。
他の商店に較べて尋ねやすいのは本屋がお客さんを選ばない業種でもあるからですね。老若男女、買っても買わなくてもОK。ふらりと入ってふらりと出て来られる。入った途端に全スタッフの視線が集中するということはないし。私はあかんたれなので、そうでないお店には用事があってもなかなか足を踏み入れられません。
海文堂は元町商店街にあったので、道を尋ねるお客様がそれは大勢おられました。入ればすぐにレジカウンターがあるし、いつもニコニコのIさんやとにかく腰の低い平野さんがお出迎えするのだから、そりゃ気軽に聞けますよ。レジスタッフは他にもいたけれど、この2人が最強なのは中央区在住で幅広いネットワークを持ち、元町はもちろん地元に精通している点です。Iさんはバイクに乗るので近道も詳しかった。平野さんは元町商店街の「みなと元町タウンニュース」に今も連載しているほど、神戸の今昔に詳しい人です。
ご近所のことでよく聞かれるのは、南京町、宝文館書店さん、まちづくり会館、書道具屋さん、寝具店さん、仏具屋さん、元町ケーキ、コーナンなど。
住所番地や店名が不確かでちょっとしたヒントから推測することもあり、さすがの彼らでも即答できないことがありました。そういう時はレジ周りにある地図やガイド本が活躍します。売り物ではありますが、カウンターにばっと広げてそれならばここらへんかなと懇切丁寧に説明。2人ともほんと親切でしたね。
私は詳しくないからと、地元民の2人に任せっきりでした。方向音痴の私は、かつて反対方向を教えてしまったことがあるので自分を信用できないのです。でも道案内をするのは、書名の不確かな本を少しの手がかりから推測し探し当て、在庫する場所までご案内するのと似たことだったのかもしれませんね。探し当てた時は、同様にすごく嬉しいですもんね。本屋の中の棚は分かっても、やっぱり私は地図が苦手で店外の案内はできないままだったのでした。
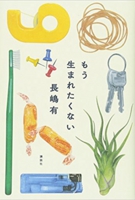
長嶋 有・著『もう生まれたくない』
2017年6月発行 講談社
日々いかに多くの「死」に囲まれて生きてきたのか気が付きましたよ、この本読んで。これまで「死」はいつも遠くにあり、身近な人が亡くなってさえ、我がこととして捉えていなかった気がします。訃報はいつも自分以外の人のものだから。
長嶋有さんの新刊を、どう説明したらいいのかな。大学を舞台にした群像劇なのだけれど、登場人物をつなぐキーワードが「訃報」なのです。すごく有名な人だったり何となく知っているだけの人だったりと、死者との距離はいろいろで、思わぬ場所で知ったその情報に対して登場人物たちはそれぞれが回想し、思索し、時には論評し、共有します。一人一人にとって「誰かの死」がどのように消化されるかについての小説と言ったらいいのかな。訃報だから悲しむ、といった紋切り型ではなくて、亡くなった著名人への思いは様々で追悼の仕方も様々。それを書き分ける有さんの筆は冴えます。
小説内の人物だけでなく、幾人もの実在した人々の訃報がもたらされます。落ちそうもない場所から転落して亡くなったミュージシャンと漫画家。「死」と「無傷」の二択しかなかった山岳での遭難事故。「すごく傷ついている」はずなのにそのことについては報道されない自死した政治家と学者。亡くなり方そのものや情報の届き方も含めて、うまく言えないけれど何か違うと感じる登場人物たち。その違和感を著者は適切な言葉で誠実に伝えようと試みます。インタビューで、知る必要のない死まで知るようになった社会だから、この小説ができたのだと有さんは語っています。
中でも後半、声優の内海賢二さんの訃報の取り上げ方がすばらしいのです。映画やアニメでなく、登場人物たちはみな通販番組を見ています。そこでゴルファーの声「この、飛び!」を吹き替えしているこの人が、ラオウや則巻千兵衛やミスターXの声として忘れられない内海賢二さんと気付きます。
「……亡くなったんだ、あの声の人」意外な言葉が出てき、素成夫はテレビの画面にまた目をやった。素成夫が知っているのは再放送で何度もみた『北斗の拳』のラオウの声だけ。それから視線を戻すと遊里奈は座り直し、すっかり敬虔な表情になっていた。
私自身も敬虔な気持ちで読んで来ましたが、ここでは著者のサブカル好きが存分に発揮されていて、これぞ長嶋有!と嬉しくなりましたよ。
書店員時代、訃報はフェアのためにもいち早く知るべき情報でした。本を出版したことのある人なら追悼フェアの対象です。著者が亡くなるという報道は読書のきっかけになるようで、追悼の仕方のひとつとして本屋に足を運ぶ方は一定数おられました。でも担当者だった私は、果たしてその人の死と向き合っていたと言えるかな。今さらながら薄っぺらだった追悼フェアに恥じ入るばかりです。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.6月 (36)ショーウインドウ

(36)ショーウインドウ
本屋のショーウインドウというものは、面白そうな本が飾ってあってもお店の人に声をかけないと手に取ることもできないですよね。するとどういう使い方をするのがベストなのかな。これから出る全集や大型企画の告知、予約受付中のポスター掲示ぐらいしか私には思いつかないです。もしかして海文堂の使い方はなかなかすぐれものだったのかもしれません。
元町商店街に面していた海文堂には出入口が2か所あり、ショーウインドウは西側入口の左横にありました。結構な広さのフリースペースです。店内から見れば、レジカウンターのレジがない方の背中の部分ですね。定期的に内容を入れ替えしていたわけではなく、当然ながら店内からは見えないので、我々従業員でさえ今何を飾っているのか把握していないことがありました。
模様替えの担当者は店長。ウインドウの後ろの戸は木製で、開け閉めするたびにがらごろと音がします。作業のために店長がウインドウにすっぽり入って戸を閉めると、たちまち行方不明者に(商店街からは見えているわけですが)。
「店長見た?」「いや、知らんよ」「どこ行ったんや」「あ、ここに靴がある!」なんてことも。
出版社の企画もの(広辞苑の新版とか)の時もありましたが、もっとも多く使われたのは船の絵の展示でした。 2階で販売していた帆船や戦艦の絵葉書の原画の展示です。壁面に掛けたりイーゼルに置いたりして、海洋船舶画家の高橋健一さんの作品をよく飾らせていただきました。帆船だったか客船だったか、色鉛筆で描かれたとても大きなサイズの迫力ある新作をお預かりした時、ショーウインドウで除幕式というのを行ったことがあります。こういうことができるのは海文堂ならではかもしれませんね。
海文堂は週に何日か、店頭をアウトレットのCD屋さんにお貸ししていました。ワゴンがずらりと並ぶのでショーウインドウは目につきにくかったように思います。そのせいかまだ朝早い出勤時、開店前の広々とした店頭にたたずんで、船の絵を熱心に鑑賞しておられる方を何度もお見かけしました。その方にとって海文堂は、紛れもなく「海の本屋」だったのでしょう。こうして船や海や港の様子を描く画家さんが作品を発表し、船や海や港が好きな方との出会いの場となり、作品が売れたり発表する場が広がったりするきっかけを作っていたのですね。いつのまにか街の本屋の役割を果たしていたのかもしれません。神戸開港150年の今年、海文堂とゆかりのあった彼ら画家さんたちがさらに注目されて、さらに活躍されていますように。
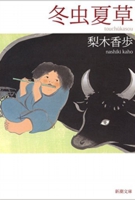
梨木香歩・著『冬虫夏草』
2017年5月発行 新潮文庫
単行本が出たのが2013年10月。海文堂が閉店してすぐだったので、あーこれからこうやって違うカバーを掛けてもらうんだなとしみじみしたのを覚えています。文庫になったのを機に、じっくり再読してみました。
これは『家守綺譚』の続編で、正編と同じく物書きの綿貫征四郎が執筆したという設定です。前作が植物を章立てのタイトルにした連作短編集だったのに対して、今作は途中より鈴鹿の山に向かう紀行文の趣となります。その旅の目的はいなくなった「友人」であるゴローを探すこと。
綿貫征四郎は亡き友人の高堂から託された家に一人住まいをする身。異界からやってくる高堂はじめかかわりのある人は結構多く、好奇心を持って人の話を聞く能力のある愛すべき人物です。ゴロー探しに出発してからも、徒歩に次ぐ徒歩なので各所で道を尋ねまた泊めてもらわねばならず、次々と人(時に異類や異界のもの)と出会います。そのやり取りが実に面白いのです。雨乞いを頼まれ、滝の由来に思いを馳せ、不幸な乙女の幽霊に会い、河童少年の行く末を案じ、イワナの夫婦の宿に泊まり、異類との距離の取り方も学びます。森羅万象に五感を働かせた名文は丸暗記したくなるような美しさで、心地よいリズムとくすっと笑えるユーモアにあふれています。私は梨木果歩さん作と分かっていながらも綿貫征四郎のこのエッセイが好きなのです。彼が書いているという竜の話や菌類と植物の異類婚の話をぜひ読みたい。スピンオフで出版してほしい。
ゴローはどうやら竜王の手伝いをして鈴鹿の一大事のために働いているようなのですが、これは推測の域を出ません。この小説は綿貫の視点で書かれているので、彼の知り得たことしか読者には分からないのです。村々が将来人為的に沈められることに対しての何か、なのですが、ゴローが見つかっても答えは得られません。
『家守綺譚』をご存じない方及びこのサイトで私がお世話になっているゴロウ氏にもお知らせしたいのは、ゴローが犬だということです。ゴローはそんじょそこらの犬ではありません。
体軀は大きからず小さからず、色は茶。尻尾はふさふさとして目元涼しく、人を見て恐れず、それらを侮らず、己が必要とされればその役割に応えんと誠実の限りを尽くす。(中略)威張らず、威嚇せず、平和を好むが、守るべきものがあれば雄々しく立ち向かう。友情に篤く、その献身は、かけがえがない。
賢くて凛々しくて人望厚いゴローでもいかんせん人語を話せない。だからこそ、帰ってさえ来ればいい。ラストの再会の場面は素晴らしいです。駆けてくるゴローの姿がはっきりと見えます。あー、絶対この後の展開知りたいですよ!
時代設定は明治末か大正あたりでしょうか。歴史や民俗学、植物、神話など専門的な要素もありながら、おばあちゃんがその親から聞いていたような不思議なお話もたくさん。ちょっと昔の、人と異類が明確な区別なく暮らしていたころがうらやましくなりました。山里の子たちが旅人から聞く話を心待ちにしたように、私もこれに続く梨木作品を気長に、期待して待つとしましょう。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.5月 (35)木の本棚

(35)木の本棚
みなさんは行きつけの本屋さんの棚の素材が何か覚えていますか? 素材どころか色さえ思い浮かばないのではないでしょうか。本が主役だから、棚は機能的であればいいだけで、存在を主張するものじゃありませんよね。あんなに壁面も空間も棚だらけなのに、スタッフのエプロンの色ほども印象に残らないのが本屋の棚なんです。
私が最初に勤めた書店の棚は緑のスチール棚でした。本屋の棚はそういうものかと思っていたところ、転勤先の本店で使っていたのは凝ったデザインの木製棚。その時最先端だったショップに特注で作ってもらったとか。おかげで両方の使い勝手を比べることができました。
海文堂の本棚は珍しいグレーの木製。黒の棚板はどっしりと厚く、全体に質実剛健といった印象。悩みはセロテープで貼ったポップをはがす時、下のペンキが一緒に取れてしまうこと。文芸新刊台はかなりみすぼらしい姿になっていました。
木製棚のいいところは、(不精者なので)積もったほこりが目立たないことと、(がさつなので)角が鋭利でないから手を切らないですむことですね。欠点はストッカーがゴロゴロ重いことと、棚の高さを変えるのが難儀なこと。ねじ穴の部分も木なので、棚を外すためにガンガン叩いて力尽くで移動させることもありました。もともとは木だったのだから、本との相性は木製の方がよいような気がします。お値段については別にして、ですけどね。店長は「この棚高かってんで」と言っていました。
ありがたいことに海文堂亡きあと、いくつかの本棚は有志に引き取っていただけました。岐阜の徒然舎さんでも元気に余生を送っている様子。グレーなのですぐわかりますね。もとは人文社会の棚だったので、ちょっと重めの本が似合っています。ぜひいつかお伺いしたいです。
ついでにストッカーのことも。海文堂の東側壁面に沿って文芸書の棚がありました。平台つきの棚だったので、その下にはもれなく引き出しが。海文堂は原則ストックを持たない方針だったから無用な空間がたくさんあったわけです。するとどうなるか。展示期間を過ぎたパネルや販促物、束見本、ポップ立て、フェアで使えそうな厚紙やきれいな函、なかでもがんばって作った自作のパネルやポップはなかなか捨てられず、引き出しにどんどん入れてしまう。そういうのが私だけでなく歴代の文芸書担当者の遺品としてストックされて……。実はこれお宝ちゃうんというような物もあったりして、退職時にはどうしようと思いつつ見ないふりをしていました。でも閉店が決まり、最後には悩むことなくすべてきれいさっぱり処分出来て、この時ばかりは気持ちよかったですよー。

奥野修二・著『魂でもいいから、そばにいて3・11後の霊体験を聞く』
2017年2月発行 新潮社
霊なるものがいるとかいないとか、まして私がどう思っているかなんてどうでもいいことですよね。少なくとも体験した人たちにとっては実際にあったことなのだから。本書は東日本大震災の被災地で、津波によって家族を亡くした人たちが経験した「不思議な出来事」を聞き取りしたもの。
奥野修二さんは『心にナイフをしのばせて』の著者として有名ですね。ノンフィクションライターである奥野さんは、霊体験を取材するなんてUFОを調べるようなもので受け入れがたいと思っていたのだけれど、宮城県の被災者である医師に薦められ、次第に考えを変えてゆきます。「怖い」霊体験ではなく、死者との再会によって安らぎや希望や喜びを与えられた物語を聞いてみたいと思うようになってきたのです。
亘理郡で介護職をしていた男性は妻と1歳10か月の次女を津波で亡くします。遺体はなかなか見つからず、やっと3月下旬に火葬にすることが出来たその日、不思議な体験をします。2人が目の前に現れ娘が手を振っている。夢かと思ったが目を閉じれば同じ光景が見える。そののち瓦礫の中から大事な記念の品があり得ない状況で見つかったり、結納記念日に現れた妻が「戻りたい」と言ったりと、死者と今もつながっている感覚に励まされます。その後「急がないから。待っている」という声が聞こえてきて。
私にとって何が希望かといえば、自分が死んだときに妻や娘に逢えるということだけです。それには魂があってほしい。(中略)それがなかったら、何を目標に生きていけばいいのですか。
最愛の家族を失って生きていく気力も失せた人たちは、死者との交信によって、彼らが身近にいると感じることで生きる力を与えられたのでした。
著者にこのテーマを薦めてくれた医師は、この震災で出現した霊体験について「人間が予測不可能な大自然の中で生きてゆくための能力かもしれない」と言うのです。今の科学は特殊な現象に対処していないのだから、と。かけがえのない家族である死者と交信することが、遺された人たちにとって自らを守る術となったのかもしれません。
本書では16編の霊体験が聞き取りされています。被災者でない者が実証的なデータのないテーマで書くということには、一歩踏み込めないラインがあったのではないかと思います。それでも著者は勇気を出して、被災者に代わって伝えることを選んだのでしょう。ためらいつつも犠牲者の背景を丁寧に描くことで家族に寄り添っていて、不思議な体験も違和感なく受け入れることができました。
阪神淡路大震災ではどうだったのでしょう。死者行方不明者6436名の遺された人たちの悲嘆があり、おそらくは霊体験もあったことでしょう。それら心にとどめ置かれた体験の代表としての役割も、本書は担っているのではないでしょうか。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.4月 (34)長期休暇

(34)長期休暇
まずはこの場を借りて、くろやぎさんにお祝いを。ご出産おめでとうございます! くろやぎさんにとっては初めての子育て。赤ちゃんにとっては初めてのこの世界。ともにびっくりに次ぐびっくりの日々でしょうね。そのドキドキでもたもたできらきらのさなかにいるパパママベビーに最大級の敬意を表します。
出産育児休暇中の棚のこと、ご心配でしょうね。私の長かった書店員生活の中で出産休暇を取った人はいたかなと考えてみたのですが、該当者はいませんでした。働く女性が当たり前のように所帯をもって子供を持つという理想に今、少しは近づいていると思いたい。くろやぎさんが今後憂いなく復帰して前にも増して楽しく働かれますように。
あんまり役には立ちませんが、海文堂最後の10年間に、長期休暇を取ったスタッフの棚をどのように他のスタッフがフォローしたか(あるいはしなかったか)という話を書きます。
ジャンル担当者の裁量が大きく許されていた海文堂ですが、本人が休んだ時に誰かがフォローするというシステムはありませんでした。棚は担当者のもので、チームでかかわるものではなかったのです。新刊や補充は、公休日にはそのままだったり誰かが新刊だけは出したりとばらばらで、主に善意にゆだねられていました。そのまま置いておかれることも多く、お客様に尋ねられてあわてて仕分け棚を探すということもありました。
さて長期休暇。岩波担当が(落ちて)けがをして入院した時、新刊はデスクに積まれてどうなったっけ。岩波だけの棚があったし注文品のみの入荷だから、他の人でも比較的棚出ししやすいジャンルではありましたね。海事書担当が(すべって)けがをして入院した時、これは2階のよしみで学参担当が全部補ってくれました。出勤日も増えて大変だったと思う。海事担当は学参担当に最後まで頭が上がらなかったことでしょう。外商担当が(こけて)けがをして入院した時、もう一人の外商担当が代わりに取引先に出向いたのだろうか。これは不明。
人文担当が風邪をこじらせて入院した時、結構長かったので新刊がたまりにたまって大変でした。出すのはいいけど返品の見極めがつかず、ついにはすべて段ボール行き。その段ボールも積み上げるほどになり、どこに何があるかなんて全く分からない状態に。復帰後いつの間にか片付いていました。さすが仕事が早い。
雑誌・芸能担当が体調悪くして検査入院した時、これは困った。この人の棚は他の誰にもまねできないし。雑誌はみんなで手分けして出したけど、芸能書はそもそも新刊の時点で置く本かどうかも分からない。休み中に最も棚が変わったのはここだと思う。
以上はすべて男性スタッフ。海文堂女子はお産休暇も病気も事故も無し。いつも弱っちい男性陣のフォローに(まあできることだけですけどね)努めたのでありました。
こんな体たらくを読むとくろやぎさんは不安になっちゃうかな。いえいえ、こんなアバウトな会社は他にはないでしょうからご安心ください。私自身は他の担当者の棚を(無責任に)触らせてもらうのが結構好きでした。その人の「並べ方のクセ」をまねしたりして。他のスタッフもそうなのなら、ちゃんとシステム化しとけばよかったですね。

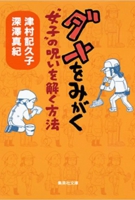
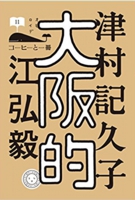
津村記久子・著 『これからお祈りに行きます』2017年1月発行 発行 角川文庫
津村記久子・深澤真紀・著 『ダメをみがく″女子”の呪いを解く方法』2017年1月発行 発行 集英社文庫
江弘毅・津村記久子・著 『大阪的』2017年3月発行 発行 ミシマ社
本屋さんに行って、久々におお!と心動かされたのでした。私の住まいに近いJ堂は基幹店ではなくとも品ぞろえは良いほう。ただいつもなんかおとなしいなあと思っていました。買いたい本がしかるべき棚で見つかるのは気持ちが良いものだけど、それ以外の「これもどうですか」的なアピールをほとんど感じたことがない。それがこの度、オリジナルポップを発見したのです。曰く、「三度の飯より津村が好き」。出たばかりの「大阪的」と一緒に2冊の文庫を紹介していましたよ。その熱いポップを見て、私も好きなんですよと対話している自分がいました。この本屋さん(のポップ)との対話って、結構重要な気がするのです。
『これからお祈りに行きます』には二つの中編小説が収録されています。1作目の主人公は高校生男子。2作目は大学生男子。私とはかかわりのない年代の彼らなのにぐいぐい読めてしまうのがすごい。けっしてお祈りがテーマの小説ではないのだけれど、やはり印象に残るのはその場面。2作とも、今どきの若いぐだぐだの男の子が地元のカミサマに、また嵐山の寺で、願い事をします。その内容は自分のことではなく、友人や幼なじみや文通相手の悩みごとのこと。自分がそれら悩みに対して何もできないことに傷ついてもいて、問題が解決するようにただ祈る祈る、本気で祈る。その無償の行為がなんともすがすがしいのです。津村さんの、真面目に書いているのに面白いところ、あらゆることに対する誠実さ、押しつけがましくない心優しさ。身に沁みるいい小説です。
『ダメをみがく』は津村さんと深澤真紀さんの、自己啓発本とは対極にある対談集。文庫が付箋だらけになりましたよ。単行本で読んだ時は生活編の、家族のありかたの話に大いに共感し励まされたものですが、文庫になって読み返してみると、今度は仕事編をより身近に感じました。その時々で、きっと至言金言が見つかります。
深澤
だから、「相性の悪い人間関係は逃げた方がお互いのためである」と言いたいんです。向き合った りがんばったりしても、解決するどころか悪化させることがありますからね
津村
理由を探す時間が無駄ですからね。
深澤
そう! そうなんですよ!
働く女子に、家族に悩む女子に、大いにお勧めいたします。
『大阪的』は津村さんと江さんの対談とそれぞれのエッセイ。私は大阪的な人間ではないなとひしと思う。ただ津村さんのしゃべる(書き起こされた)言葉はまさしく私になじみ深く、ずっと聞いてきた大阪弁です。だからというのも変だけど、すごく信用できる気がする。知らんけど。
津村さんのありがたいところは、芥川賞作家なのにばんばん小説やエッセイを書いてくれるところ。4月には『まぬけなこよみ』、5月には『エヴリシング・フロウズ』の文庫化。惜しげもなく書いてくれるのがうれしい。太宰賞や芥川賞のころはちょっと内向的な暗めの人かと思っていたのですが、話し好きでくよくよしいのいかにも大阪のおねえちゃんでありました。大阪的でないはずの私なのに、つい無理せんときやなどとおせっかいを言ってしまうのでした。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.2月 (33)海会(カイエ)

(33)海会(カイエ)
神戸港海港150年イベントのひとつとして行われた『2日間だけの元町「海の本屋」復活スペシャル』。海文堂サポーターの方々のご活躍に頭の下がる思いです。3月19日の講演のテーマは「海文堂書店紙誌史」。元スタッフの平野さんと小林元店長のお話は聞いてくださいましたか? 私は1階で店番をしていましたので内容は知らないのですが、閉店直前まで続いた「海会」に連なるフリーペーパーの歴史が語られたことと思います。
99年続いた海文堂がいくつものPR誌やフリーペーパーを発行してきたことについての意義や、出さずにおれないといった熱意は大いに語られたと思うので、ここでは海会を配布したスタッフとして書いてみますね。
海会創刊第1号を見た時の感想は、まず「わ、かっこいいやん」でした。クリーム色のA4版うらおもて、タイトルは筆記体でフランス語のCahier(カイエ)。漢字の海会が先に決まったのか、Cahierに漢字を当てたのか、命名のいきさつは存じません。店長が往年の映画好きだったことを考えると、カイエ・ドゥ・シネマが頭にあって海という漢字と結びついたのではないかしらん。
海会は毎月1日発行だったので、月末になると出来たての海会の包みがくとうてんのどなたかの手によって作業場に運ばれてきました。まずは店長が取り置きなどの必要数を取り、残りをレジに運びます。そこで半分に折るという作業。レジIさんがバサバサと大量に折ってゆく手つきが印象に残っているというスタッフがいます。そして帆船柄の青い手提げポリ袋に入れて、本や雑誌を買われた方の手に渡るというわけです。袋に入れない方にはさらに半分に折った海会を本にはさんでお渡しすることもありました。
「本屋の眼」をまず読むというスタッフが何人もいましたが、面白いからだけでなく自分のことが書かれていないかチェックするという意味もあったかもしれませんね。もう一つの連載「本の生一本」の著者である千鳥足純生さんについて、当初どなたのペンネームなのか聞かされていなかったため、千鳥足と言えばそりゃ店長のことに決まってるよねと思われていたようですよ。お客様の野村さんのことだと知って驚いたそうです。
全部で122号まで出た海会のメインの記事は原則としてイベント告知と月替わりのオリジナルフェア紹介。担当持ちのスタッフは、このフェア原稿で「書くこと」を鍛えられたと思います。自分のフェアの紹介を、お客様に活字で読んでもらえるということが私はとても嬉しく、拡大コピーしてフェア台に掲示したりしたものです。
2013年7月、月末になっても新しい海会が届きませんでした。遅れて8月5日に届いた見出しにびっくり。スタッフに知らされないまま閉店のご挨拶が海会に掲載され、連載していた人たちはいきなりの終了を余儀なくされました。終えるなら終えるで、スタッフもそれなりの言葉を添えたいものです。海会は私たちのフリーペーパーなのですから。
最終号を出したいという思いはサポーターの方々にも伝わり、くとうてんさんほか、周りのみなさんのご尽力で閉店に間に合わせることができました。千鳥足純生こと野村恒彦さん(現うみねこ堂書林店主)が最後の編集長を務めてくれたと聞いています。おかげさまで連載を持つ人は最終回の挨拶をし、お世話になった方々から送辞もいただき、私は9月の最終フェアの告知をすることができました。
海文堂書店誌紙史の掉尾を飾った海会。これにて終わり!と思ったら、どっこいまだありましたよ。もともと海会の別冊として発行されていた「ほんまに」。閉店後は別冊という表記を無くして今も元気に刊行中。フリーペーパーではない「誌」としてしばらくは海文堂の息のかかった紙面づくりが続くかも。そして海文堂なんて知らんでという時代になっても、広く読み継がれる冊子として続けてくださいね。
 吉田篤弘・文 フジモトマサル・絵 『という、はなし』
吉田篤弘・文 フジモトマサル・絵 『という、はなし』
2016年12月発行 発行 ちくま文庫
電車内では少数になったけれど、本を読んでいる人の面差しはいいですねえ。車内にいることなど忘れて集中している様子。何読んでんのかなと覘くと時代小説と自己啓発書が多かったような気が。書店員時代、棚の前で心ここにあらずといった表情の方をたくさん見かけました。本の中の世界で登場人物の一挙手一投足に、あるいは著者の巧みな語り口に心を揺さぶられているのでしょう。私も本屋さんで立読みを始めると一瞬にして入り込みます。文字通り目を奪われているのです。
前置きが長くなりました。この本『という、はなし』は1枚の絵に3頁の短いお話が付く超短編集なのですが、絵がすべて擬人化した動物の読書の風景なのです。
まずフジモトマサルの絵があって、それを見て吉田篤弘がお話を書くという普通と逆の趣向。篤弘さんは謎解きをするように絵からお話を紡いだようです。たとえばトラが日本家屋の縁側で読書する絵には、虎野先生が巻物状の手紙をひもとく話「虎の巻」。窓辺で本を前に寝落ちしたキツネの絵には、夜の読書の時間を心待ちに、すべての用を片付け満を持して迎えた俺の話「眠くない」。
一番好きなのはレッサーパンダが病室で本を読みながら点滴を受けている絵の「読者への回復」。
愚かしさにつける薬はないにしても、とりあえずきりりと口を結んで活字の点滴を打ってもらう。すると、そもそも自分が何者であったのか、ようやく思い出す。「読者」であること。肩書きはそれだけでいいのだ。
ひゃー、かっこいい!
篤弘ファンの私ではありますが、フジモトマサルファンでもあるのです。この本は好きな二人のユニット作品を、好きな出版社の筑摩書房が発行するというトリプル本! 装丁はもちろんクラフト・エヴィング商會で小ぶりのB6変形ハードカバーというサイズも好き。でも今後、この夢のコラボが再び実現することはありません。フジモトさんは2015年秋に46歳の若さで亡くなってしまわれたのです。
本に関する冊子を編集発行しているМさんは、クリスマスにこの本をプレゼントとして使われたそう。そうです、プレゼントとしてぴったりなんです。長編小説だと好みがあって読んでもらえないかもしれないけれど、この本なら絵がかわいい上に文章も短くとてもとっつきがいい。その上で絵の細部のこだわりと、ちょっとシニカルな表現やまさしく箴言といった言葉に気付いてほしいな。文庫になってさらに買い易くなりました。『村上さんのところ』で初めてフジモトさんを知った方にもぜひ。
(三毛小熊猫・元書店員)
2017.1月 (32)パタパタさん

(32)パタパタさん
その方は、世の中面白くないことばっかりと思っているように見受けられました。気難しいところがありちょっと怖い印象でしたが、必ず中央カウンターにやって来て人文系の良書を依頼されました。
ご病気の後遺症なのか、狭い歩幅の速足で歩く靴音が、パタパタと音を立てていました。中央カウンターに近づいて来られると、姿が見える前に足音で分かりました。「あ、あの足音は。○○さん来られましたよ」と店長に報告したりしていました。
新聞の切り抜きの本を私たちに探させると、パタパタさんは丸椅子に腰かけてじっくりと内容を吟味されました。「この本は面白いけど索引がないからだめやな」と評されることや、「わしはもうあかんねん」と体調の良くないことを思わせる日もありました。
元町商店街までタクシーでやって来て、3丁目の海文堂で本を買ってから一番街の老舗珈琲店でコーヒーを飲み、そこでタクシーを呼んでもらって帰る、というのが定番のコースだったようです。買われた本を珈琲店に何度か届けに行きました。珈琲店の方は海文堂の袋を見ただけですぐにどなたの用事か分かってくれました。
パタパタさんが、焼き増ししたばかりの写真をスタッフに見せてくれたことがありました。当時よりも若い姿で写っているパタパタさんが登山をしている写真です。その中に奥さまと一緒に写っている写真がありました。
「奥さまもご一緒にいらしてくださいよ」
「奥さまなあ、もういてないから来られんのや」
私の不注意な発言です。でも僭越な言い方ですがパタパタさんの人生の一部を垣間見たような気がして、この件をきっかけに親近感を抱くようになったのでした。奥さまと一緒に写った写真の中のパタパタさんは、実に楽しそうにニカッと笑っていたのです。私たちには見せたこともない満面の笑顔でした。
1年ほどのち、パタパタさんは姿を見せなくなりました。定期書籍担当のHさんに聞くと、パタパタさんの定期はすべて完結して今は何も無いとのこと。本が残っていれば電話で確認することもできたのですが。
パタパタさんが買われた本を、児童書Tさんがあえてプレゼント包装したことがありました。リボンシールも貼って。ちょっとしたいたずら心だったのですが、「なんやそんなことせんでええのに。いらんことして」と叱りかけて、「まあええわ」と声を落とされました。そんな茶目っ気も受け入れるやさしさを、Tさんは見抜いていたんですね。気難しい仮面を被っておられたパタパタさん。足音と声を今も覚えていますよ。
 宮井京子編『本と本屋とわたしの話11』
宮井京子編『本と本屋とわたしの話11』
2016年10月発行 発行 宮井京子
このB6サイズで30頁足らずのかわいらしい小冊子は、ISBNや雑誌コードを背負って日本中を流通している本ではありません。発行人である宮井さんが書き手の一人となり、企画・編集・製本・営業をして置いてほしい書店に販売委託をしています。
その人が本と出会ったとき、それはいつ、どんな場所で、周りにどんな人がいたのか。という記憶を文章に留めておきたいというのが冊子をはじめた動機です。
これは宮井さんからいただいたメールに書かれていた文章です。本屋に限定せず、「本とわたしと、その仲立ちをした誰か、あるいはその出会いの場」について寄稿されたコンパクトなエッセイ集なのです。
11号には三つのエッセイと、あの人の本棚という連載の第6回が載っています。第一話は退職して古本屋から図書館通いに変えた男性の本を巡る近況。第二話は神戸で市民図書室にかかわる女性の、幼少期の部屋の引っ越しの思い出。連載は、本に出てくる本についての話を3人の書き手が紹介しています。
第四話は編著者である宮井さんによる、地元阿倍野の私的本屋史。すべての本屋が地べたからビルの中に移ってどこも大差なくなったと思ったけれど……、意中の棚を発見。ああ、この先はしろやぎさんにぜひ読んでもらいたい。もう1人アカヘル氏にも(もう読んでるかな)。
あの店からここに移ってきたスタッフがいるという噂を、わたしはこの一冊で確信した。あたりまえだが、本棚の後ろには、それを作った人がいる。
さあて、アカヘルさん、どの本のことか分かりますか?
真っ当に働く者が評価される嬉しさ。自分のことでもないのに誇らしく思えてしまうのは、書店員時代誰に対して発信しているか分からなくなることが多々あったからかな。こうやって見ていてくれる人がいるということは書店員にとって、すごく励みになることなのです。
第二話には海文堂児童書コーナーで見つけたワーズワース詩集のことも書かれています。本好きの方々が3年以上も前に閉店した本屋のことを記憶にとどめてくれているとは。
宮井さんが一人で年に2回の発行を続けるのはさぞ大変だと思うのですが、表紙が毎号美しく、丹精込めて手作りされているのがよく分かります。11号は微かに水玉の浮かぶ真っ白な紙に、広げた本と淡い雪の結晶の絵。奥付頁の検印代わりに貼られた鳥のイラストシールも楽しい。
古書善行堂と文の里・居留守文庫では間違いなく入手可能のはず。こういう場合は通販で購入というのもありですよね。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.12月 (31)ラッピング

(31)ラッピング
1年で一番売り上げの多い12月から年始にかけて、書店員のみなさん無事に乗り切られましたでしょうか。この度初めて大晦日に新刊が出ることになったとのこと。仕事が増えたとは言え、新年早々棚に新刊を並べられるのは嬉しいですよね。運送の方は大変でしょうがそのような変化は客としても喜ばしいです。
かつての海文堂は元旦と二日を休業していました。シフトはAチームが大晦日、元旦、2日と休みならばBチームは元旦、2日、3日が休みとなり、1年おきに交代しました。平等に最低3日は休めたのです。大晦日に入った新刊を私も3日に初売りしたかったな。気持ちも棚も新たになって新年の「仕事始め」を実感するのではありませんか。
本屋の12月が忙しい理由は本のプレゼント需要があるからです。海文堂の児童書売り場は業界にも顧客の方々にも定評がありましたので、クリスマスプレゼントやお年玉用に大勢の来客がありました。
児童書Tさんが審美眼にかなった本を切らさず発注していてすごいと思っていたのですが、そこにはTさんならではの揺るぎない信頼のパイプがあって、取次、版元ともにうまく活用していたからでした。
私たちはレジや中央カウンターで児童書や絵本のラッピングに励み、バイトくんたちにも包装を覚えてもらいます。幸いレジの後ろにはまさに包装台ともいうべき広いスペースがあり、余計なものを取っ払えば広々とラッピングすることができました。レジの背中側というのがミソで、お客様に注視されずに包装できるのがよかったなあ。
海文堂のオリジナル包装紙は白地に帆船が並ぶカバーと同じもので(というか、包装紙を半分に切ってカバーを折っていたのですが)、それに加えてクリスマス用の包装紙も用意されます。他には児童書の版元さん提供のかわいらしいラッピング用紙が何種類か。児童書Tさん秘蔵のピーター・ラビット包装紙もありました。
ただ包装紙って大きいので高くつくしクリスマス用は枚数限定です。バイトくんたちにはお弁当包みで失敗するくらいならキャラメル包みでいいからという指令があり、わら半紙で練習してもらったものです。
当然ながら一番ラッピングが上手なのは児童書Tさん。一目で必要な包装紙の大きさを判断し、手早く美しく包んでリボンシールを貼る位置も的確。丸かったり持ち手があったり違う大きさの組み合わせでも完成すれば違和感なし。百戦錬磨の名人わざに当たる方はラッキーでした。
クリスマスが近づくと、私は張り切って包装紙やリボンの準備をしたりして、腕まくりしたくなる様な高揚を感じたものです。同類の書店員さんに、緊張感から解放されるこの時期お疲れさま!と言いたいです。
 花田菜々子・北田博充・綾女欣伸編『まだまだ知らない 夢の本屋』
花田菜々子・北田博充・綾女欣伸編『まだまだ知らない 夢の本屋』
朝日出版社 2016年11月発行
昨年6月に処女作『これからの本屋』を上梓した北田さんが早くも次の本を出されました。本仲間のみなさんと作ったこの『夢の本屋ガイド』は、前作の中で1章を割いていた「くうそうする」に触発された書店員の方々が、それぞれの夢の本屋を描いたもの。
みなさん嬉々として書いている様子が伝わって来て、北田さんいい仲間に恵まれているなとこちらもうれしくなりました。
「GOKUCHU BOOKS」は編著者北田さんが自らガイドする夢の書店です。獄中にいる人から注文を受け、希望に沿った本を届ける仕事。店主と本のかかわりは、やくざだった父の遺した趣味の良い蔵書を読むことから始まり、取次とその関連書店で働いて、別の書店に移り独立。今は書店経営の傍ら受刑者を対象とした本の差し入れサービスを行っているというもの。店主が気付いたのは高尚な読書だけが読書ではないということ。日用品やジャンクフードとしての本、といった多様な求められ方もあるし、本屋に足を運ばなくても本を求めている人はいるはずで、その人たちに必要な本を届けたい、と。北田さんの本への考え方の変遷と今後の氏の活動をも彷彿させる印象深い1篇でした。
本の価値は求めている人が決めるべきこと。売りたい本と売れる本とのギャップは本屋の宿命、と分かってはいるのですが、私自身は最後まで達観できない書店員でしたね。
「本屋列車おくのほそ道号」は、芭蕉が徒歩でたどったルート2400キロを列車とバスで走破するツアー体験記。1号車が丸ごと本屋になっていて名著や稀覯本がずらり。2号車では句会や読書会が行われ売店にはオリジナルグッズも。お話は松島までだけど、最後の大垣まで続きが読みたいなあ。
ホラー短編の味わい「陽明書房」、本を売らなくても本屋を実践する「STREET BOOKS」、海文堂を重ねてぐっと来た「北光社」、文士の時代への愛にあふれた「BUNSIMURA!」。他にもさまざま。ほんとにいろいろ集めましたね。「本屋村」のこのセリフがすべてを言いあらわしているかも。
本屋って、誰でもなれると思うんです。だって本って、この世の中にあるすべてのものにつながっているから。
ここに書かれた本屋に行ってみたいと思った方は、まずその本屋をガイドした書き手のいる書店を訪問してください。きっと夢の片鱗が感じられるはずですよ。
先日日経新聞で、「米国で紙の本が盛り返している」という記事を読みました。「他のエンターテインメント空間に負けない魅力的な書店が現れれば、日本でも変化は早い」とのこと。新しい本屋のありかたを考えるこの本が、新本屋時代のきっかけになるかもしれませんね。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.11月 (30)女子更衣室

(30)女子更衣室
更衣室に案内されて、縦長のロッカーを自分一人で一台丸ごと使えると聞いた時は驚きました。それまでに働いた店舗は地下街やショッピングビルのテナントだったためバックヤードは狭小で、キャスターの付いたハンガーラックを全員で使っていたからです。かばんや私物もその辺の棚に適当に置いていて、お昼に財布を取り出すのには便利でしたが不用心ですよね。唯一、百貨店のテナントだった時だけは専用のロッカーでしたが、巨大なロッカー室の中の数台を店舗が借り賃を支払って使うというシステムでした。
海文堂の、ちゃんと入口に鍵の付いた更衣室と個人用ロッカー。自前の店ってこうなんや、バックヤードも余裕やなと感心し、ゆったりと制服に着替えることができました。
鍵を開けて女子更衣室に入るとそこは4畳くらいの小部屋。10数台のスチールロッカーと鏡を立て掛けた机とクッションの効いた椅子がひとつ。奥には靴を入れる棚。クリスマスや年末年始の飾りつけグッズもここに保管してありました。
それぞれのロッカーの扉には犬や猫や世界遺産や似顔絵など、思い思いの写真やシールを表札代わりに貼りつけていました。男子更衣室に入ったことは無いけれど、きっとこんな風じゃないんでしょうね。
更衣室の机は本の貸し借りをする際の交換場所として使われ(私は中央カウンターのYさんに『しろくまカフェ』を貸してもらった)、座り心地の良い椅子に腰掛ければ体調の悪い時の医務室代わりとなり(食欲がない時うつらうつらして昼休みを過ごしたことがある)、着替える以外にも役に立っていました。幸い女子高生ではないので更衣室をしくしく泣く場所として使ったことはありません。たぶん誰も。いや、あるのかな。
お世話になった更衣室ですが結構悪口も言いました。とにかく暑いのです。窓もエアコンもない部屋で小さい扇風機を回しても全然涼しくなりません。夏場の朝、駆け込んで来て汗だくで制服に着替える時は辛かった。ベストスーツなのでストッキング着用です。これがべったり張り付くんですよ。その間の挨拶はタオルハンカチで汗拭き拭き「暑いねー」「ほんとに暑いですね」「たまりませんね」となんとも語彙の少ない会話しかできなかったですね。
密室という特性を生かして密かに愚痴り合ったりしたことも。日ごろほとんど接点のない総務のYさんと一緒になり、飼い猫のピッチの話を伺ったのもここです。海文堂の女子スタッフの中でただ一人今も新刊書店で働いているHさんは、どんな新たな女子更衣室ライフを過ごしているのかな。あのゆったりした広さを再確認したのじゃないかしら。
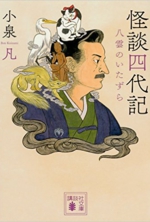 小泉 凡『怪談四代記 八雲のいたずら』
小泉 凡『怪談四代記 八雲のいたずら』
講談社文庫 2016年7月発行
怪談好きの友達が、この本面白いよと教えてくれました。薦められた本をめったに読まない私が、これは是非読もうと決めたのには訳があります。この夏松江に一泊旅行に出掛けた折、小泉八雲記念館にも立ち寄ろうと思っていたのに休館。なんと翌日がリニューアルオープンの日だったのです。中を覗いたら関係者でわさわさと賑わっている様子。なんだか心が残りました。代わりにこの本でも読んでみたらという、これが八雲のいたずらだったのかもしれません。
著者の小泉凡さんは、ラフカディオ・ハーンと妻セツの曾孫にあたる人。民俗学の学者で記念館の館長でもあります。四代目の凡さんがハーンの故郷を巡る旅の中で出会った不思議な巡りあわせと、曾祖父、祖父、父のそれぞれの著作に書かれた、怪異と言わないまでも偶然がもたらしたご縁や奇遇が描かれています。私が怪談という言葉で思い浮かべるおどろおどろしいお話は少なく、ちょっとした奇譚や不思議話、またハーンのルーツであるアイルランドとギリシャ、マルティニークやニューオーリンズなどのお話も。かつて海文堂でアイルランドの翻訳小説をお預かりしていた恵光社さんは、芦屋から松江に拠点を移されましたが、松江とアイルランドはハーンによって深い関係があり、当地で仕事をする必然性があったのですね。よく分かりました。
ハーンの長男一雄氏の交友関係や因縁話(如意輪観音を置いて祟りのあった話など)も興味深く読みました。また、昭和天皇を戦犯として裁くことから守ったボナー・フェラーズについての章は必読。その思想にハーンの著作が深くかかわっていたとは。
私が好きな話は「勝五郎の再生」です。八歳の勝五郎が自分の前世を覚えていて、前世の育ての親に再会し実父の墓参りをする話。勝五郎は自分が六つの時に疱瘡で死に甕に葬られ、仏壇に牡丹餅が供えられたことや生まれ変わり先を指定されるさまもリアルに覚えているのです。すごいのは勝五郎が実在の人で、八王子に生まれ平田篤胤の門人になり亡くなった日まで特定できていること。昨年は生誕200年記念展が日野市で行われたそう。もう信じるしかない?
ハーンといえば『怪談』の作者、くらいの知識しかない私ですが、著者の凡さんも曾祖父が何をした人なのかほとんど知らなかったそう。大学院の時にハーンについて書かれた論文を偶然翻訳することになり、自分が民俗学を専攻した見えざる理由に目から鱗が落ちたそうです。
著者お住まいの松江市にはハーンの書いた怪談の舞台がいくつもあり、さらに新旧の怪談を採集すると126話も集まったとのこと。怪談収集家の木原浩勝さんが松江を「怪談のふるさと、聖地に」と提唱されています。実に面白そうではありませんか。フロッグマンのアニメで鷹の爪吉田君が紹介する平成松江怪談をたくさん動画で見たけれど、もう一回松江に行って記念館を見学しゴーストツアーにも参加してみたい!
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.10月 (29)ノーベル文学賞

(29)ノーベル文学賞
候補に挙がっていたとは知らず、今年の発表はびっくり!のノーベル文学賞でした。ボブ・ディラン……。こんなんありなん?とも思ったけれど、書店員なら文句は言っていられませんよね。ただちに手配しなければ。ディランについての本と同時代の音楽の本、アメリカのポップス史とか。全国の(世界中の?)本屋さん、いろいろ工夫をなさっていることと思います。
もし海文堂が今でも存在しているとすればちょっと面白い受賞記念フェアになったと思うのです。文学賞なので普通なら文芸書担当が受賞者の著作を中心に書目と冊数を決めて発注するのですが、ディランはミュージシャンですから音楽書担当がフェアを仕切ることになります。本人の著作が手に入りにくい状況でしょうし単にボブ・ディランという人物のみならず、社会に与えた影響も含めて、文芸書フェアとは切り口の違う受賞フェアを展開しているはずでした。音楽書の担当者はアカヘル氏だったんですもん。きっと、わーこれ置くかー思いつかへんかったわーというフェアだったはず。見たかったですよね。
さてノーベル文学賞といえば毎回話題になるのがこの人。村上春樹氏の候補が噂されるようになったのはカフカ賞を受賞した2006年頃からでしょうか。その後出版された長編『1Q84』(2009~2010)と『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013)の発売日には、世界的に有名な村上春樹氏の最新刊がどのように読者に迎えられるかということで、海文堂にも新聞社の方が取材に見えて大きく掲載されたこともありました。新刊を待たれる作家が多いほど本屋が活気づくので歓迎とか何とか適当なことを答えたような気が…。
秋のノーベル賞発表の時期になると店長や平野さんに、もし受賞が決まったら何かコメント書いてくださいねという依頼が来ていたようです。それが年中行事のようになって、本の手配以外の緊張を生んでいたのでした。いったい世界のハルキ受賞に何をコメントすればいいの?
かつて熱心に読んでいた作家さん(しかも地元出身)がそんなすごい賞を授賞されるのは大変喜ばしいことなのですが、私が文芸書担当をしている間は何としても取らないでねと願っていたことを告白します。どんなフェアをすればいいのか。難しすぎです。
たびたび取材に来られ何かにつけて海文堂を取りあげてくださった神戸新聞社のH記者も、ご自分が別の部署に移動になってから受賞してほしいとひそかに言っておられました。大きなニュースがあった時の記者さんの苦労、推して知るべしですね。来年以降の受賞時には書店員のみなさん、頑張ってね。『村上ソングズ』も置いてくれると嬉しいです。
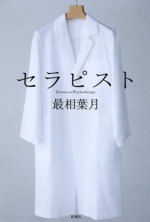 最相葉月『セラピスト』
最相葉月『セラピスト』
新潮文庫 2016年10月発行
めずらしくノンフィクションを選んでしまいました。精神的な悩みや疾患を抱えたクライエント(患者だけでなく家族や相談者の総称)に、治療や助言を行うセラピスト。日本における心理療法の歴史と変遷、河合隼雄の著作からの考察や直系弟子への取材、いくつかの具体的なケース、そして著者自身が受ける絵画療法など、ぎっしり詰まった文庫本です。
いくつもの資格があり、一口にカウンセラーといっても出自は様々らしいのですが、著者が密室で行われるカウンセリングなるものに感じていた多くの疑問がこのテーマを選んだ動機の一つになったようです。
私が最も興味を惹かれたのは、著者が中井久夫先生から絵画療法によるカウンセリングを受けつつ取材した場面の逐語録です。中井の垂水区にある自宅を訪問し四つの絵を描いてゆくのですが、ゆったりとした時間の中で緊張していた著者の気持ちも次第にほどけてきます。そして自らが描いたものに対しての中井の言葉に、自分自身を直視せざるを得なくなるのです。
一枚の紙を仕切って色を塗る色彩分割で、著者は不均等な二つに分割し、小さい左側のみ色を塗ります。それに対して中井は、今までこのように分けたのは一人の修道女だけであり、半分は神に捧げる身だから自分のことは見せたくなかったのだろうと話します。著者はこれまで自分が無意識に取ってきた行動に対して腑に落ちると同時に、次々と思い当たる節があることに気付き、むしろ開放感を覚えてゆきます。クライエントが自分で気付くような短い言葉を選ぶ中井は、興味を持ってそばに寄り添い見守るという姿勢を貫くセラピストでした。
私も知りたかったのだ。心について取材しながら、自分の心を知りたかったのだ。私は、自分のことなら知っていると思い込むことで、自分を直視することを避けてきた。他人に話をしてもどうせ分かってもらえないだろうと決めつけることで、人に心を開くことができない人生を生きてきた。中井久夫はそれを私に伝えようとしたのである。
著者の思いは、人はなぜ病むのか、ではなくどのように回復するのかということでした。箱庭療法と風景構成法を窓口にして、心理療法の歴史をたどることで見えてくるものがあるのではないか。ただ、逡巡もあったようです。取材先はカウンセラーや精神科医やかつてクライエントであった人など心の専門家ばかり。自分自身の思惑や心の弱さを見透かされてしまうのではないか。実際、取材の終了間際には著者自身が体調を悪くしてメンタルクリニックを訪れて病名を得ることに。
今、この世界の取材が必要だった。たぶん、これからも生きるために。
なぜセラピストを題材に選んだのか。さまざまな理由とは別に、著者が心深くに思い至った確信を率直に語っていて胸を打ちます。小説にしろノンフィクションにしろ、著者とテーマとの関係は、きっと意識無意識にかかわらずこのように必然のものなのでしょう。私にはなかなか手強いノンフィクションでしたが読んでよかった。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.9月 (28)バイトくん

(28)バイトくん
ここでいうバイトくんは海文堂でアルバイトしてくれた皆さんの総称です。男子学生が多かった訳ではなく、スタッフにいしいひさいちファンが多かったのでバイトくんと言っているだけです。様々な業種や職種がある中で、本屋 (他でもない海文堂) でバイトしてみようと応募してくれたみなさん、感謝です。時給は安く顧客の年齢は高く、閉店時間が早いので長時間働くこともできず、時には肉体労働もあったりして。
募集はいつも、「アルバイト学生募集 詳細は担当○○まで」と書いて店頭に貼り出すだけでした。こんなに情報の少ない求人、普通なら怖くてスルーするところでしょうが、そこは本屋の強み。親も反対しないような安心感があるのか、たいていすぐに応募がありました。
最後の数年間は平野さんがアルバイト採用の担当をしていました。彼の持論は来てくれるだけでありがたい、というもの。何人も面接して厳選するなんてことは申し訳なくてできず、条件さえ合えば来た順に決まって行きました。同時に希望者が来てしまい1人をお断りした時には、悪いことをしたとずいぶん気にしている様子でしたね。
以下は思いつくままに。私が入社した頃にいたバイトくんたち。どんな仕事もこなし『ほんまに』に連載もしていた長身のK君。大学のミステリー研に所属し閉店するまで顧客でいてくれたT君。新人で不安だった私の支えになってくれた主婦バイトのWちゃん。
私より後に採用になったバイトくんたち。中央カウンターの仕事を落ち着いて果たしてくれたYさん。インターンシップでやって来て、あまりに優秀なのでバイトになってもらったKさん。『誰が「本」を殺すのか』に海文堂のことが書かれていると教えてくれた北田君。
カバー折りが上手で安心してレジを任せられたHさん。一時は雑誌も担当してくれたH君。「ほんまに」表紙のモデルを務めたNさん。国立K大生で塾のバイトを辞めて来たK君。
М女子大の3人娘で初日からレジが完璧だったTさん、竜馬フェアのポスターを描いてくれたIさん、成人式に晴れ姿を見せに来てくれたもう1人のIさん。
そして最終メンバー。バイトくんをまとめてくれた剣道家で酒豪Aちゃん。理系なのに理系っぽくないK君。テディベアが好きなGさん。最終日レジでフル回転だった2人のМさん。そして海文堂最後のアルバイトとなった狂言ファンのEさま。この人の海文堂勤務はごく短かったけれど、なんと今、このサイトを運営しているくとうてんで元気に働いているのです。いつも感想ありがとう!
これは一部の人たちです。全員書けなくてごめんね。海文堂のバイトくんたちは総じて真面目でいい子で、しっかり先のことを考えていました。わがバイト時代を振り返るとえらい違いです。年齢が上なだけの私のことをちゃんと立ててくれました。彼らが何かの折にバイト時代を思い出す時、それがいい記憶でありますように。そして願う人生を歩めていますように。
 北田博充『これからの本屋』
北田博充『これからの本屋』
書肆汽水域 2016年5月発行
やっと入手しました!海文堂のお客さまがよく言っていらした言葉、
「この本は海文堂で買わなあかんと思ったんや」の気持ちがよく分かりました。本書は置いている店こそ少ないものの取り寄せは可能です。ただ私としては、こんないい本置いてるねんで!と思っている書店で買いたい。悩んだ末帰省時に、著者ゆかりのマルノウチリーディングスタイルで求めました。レジ前のメイン平台に積んでありましたよ。
著者の北田君はかつて海文堂のアルバイト学生でした。フェミニズムを勉強していると聞き、『東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ』について熱く語ってしまったことを思い出しました。当時彼が絶賛していたのはたしか恒川光太郎著『夜市』の中の一編だったと。北田君が本を出版したことと当時の記憶が結びついて、普段なら選ばないだろう文庫、恒川氏の『金色機械』をつい買ったのだ、私。本を選ぶ時のきっかけってそういうものですよね。
さて本書は、これからの本屋のありかたについて真摯に取材し考えた本。ほんまに日記(5月14日付)で紹介しています。構成は4章に分かれていて、まず著者の考える「本屋である人」への取材で本屋を定義し、次にこんな本屋もありかもという空想上の本屋を提示します。続いて著者が過去に企画した本の売り方の実例。最後は雇われ書店員から自らの店を立ち上げた人へのインタヴュー。
第一章で海文堂を取りあげてくれています。書店を退職してなお「本屋であり続けている」と著者が思う福岡元店長への取材。店長になる前の、自分の担当の棚のことだけを考えていた頃が一番楽しかった様子。売り上げについてのプレッシャーは管理職と平スタッフではさぞ次元の違うものであったことでしょう。久しぶりに店長節を聞けました。私の良く知っているシニカルな懐かしい店長でしたよ。店長の話もさることながら、北田君のコメントにこの本の主旨が集約されています。
本好きだって、にわか本好きからちゃんとした本好きに移行すると思うんです。そこを深みにはまらせていくのが本屋の仕事というか、僕がやりたいことなんです。
著者はこの使命を果たすべく、模索を続けます。それは本を額縁に入れて雑貨として販売することだったり、お客さんの症状に合わせて本を処方薬として選んでもらうことだったりと、過去に彼が実践したフェアがすごい。お金も手間暇もかかる大変なイベントではあるけれど、面白い発想に驚きます。さらに、どうしたら日頃本屋に足を運ばない人たちに本の面白さを知ってもらえるだろうか、と。
第四章の、独立を果たした三者三様の中で、フリーランス書店員の道を選んだ久禮亮太さんの「後出しジャンケン方式」に共感しました。
自分が提示したいテーマとか文脈とかストーリーをもとに選書するのは正直苦手で、日々新刊書店をまわしてきた身としては、そういう選書の仕方をじっくりやったことがないわけですよ。
だからお客さんが買ってくれたものを追いかけていく。この発言に勇気を得た本屋さん、大勢おられると思います。文脈棚はかっこいいけれど、それがすべてじゃないですもんね。
10月発行予定の北田君による新刊『夢の本屋ガイド』(朝日出版社)を見れば、彼がどんな解答を見つけつつあるか、もっと分かると思います。私たち書店員は本屋の中でできることだけ考えて行き詰まっていたのかもしれません。もはや旧来の本屋頭では思いつかないようなまったく自由な発想が、「新たな立ち位置」から出現し、業界を低迷から抜け出させる光明となるかもしれません。そうあってほしい。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.8月 (27)天井

(27)天井
本屋さんに入ってわざわざ天井を見上げることってないので、はたして海文堂の天井が普通だったのか変だったのか何とも言えないです。ただたくさんの蛍光灯がずらりと天井一面に取り付けられておりました。直管型というのでしょうか、長い蛍光灯(LEDじゃない)が数え切れないほど整然と並んでいたのに、なぜかほの暗い印象の店でした。
スーパーや量販店がすごく明るいのは単にワット数が違うのか、それとも電灯の種類が違うのでしょうか。海文堂の「明るくなさ」は、民家の延長というか個人商店かくやと思わせるものがありました。
あまりにたくさんの蛍光灯が稼働しているため、毎日のようにいずれかが点滅を始めます。すると男性スタッフの出番となるのです。
一番多く出動したのは間違いなく平野さんでしょう。いつも目につくところにいるからか頼みやすいからか(たぶん両方)、面倒がりもせずに引き受けてくれました。一番大きな脚立を肩に掛けて現れると、あ、どっか切れたな、と分かります。海文堂出入りの電器屋さんに雰囲気が似ていたため、こっそり、ヒラノ電器さん登場、とか言っていました。
もう一つ天井にあるものと言えばエアコンです。海文堂は2階にギャラリーがあったのですが、夏の間はイベントを行いませんでした。アンペア数が足りないのか、売り場とギャラリー両方の冷房を強めるとブレーカーが落ちるからです。危うくなると警告の音が鳴ります。大音量のビー音が鳴り響くと作業場に走って行き、貼られた指示書に従って解除して、冷房をいったん止めなくてはなりません。あのいかにも非常事態発生といった警報音には、ついぞ慣れることがありませんでした。
そして結露です。夏場、天井のエアコンから水がぽたりぽたりと落ちてくるのです。文芸新刊の上、女性誌の上、文庫の上がひどく、特にハヤカワ文庫のアガサ・クリスティは毎年赤い表紙を濡らしていました。応急処置としてエアコンに、水を溜めるためのポリ袋を取り付けます。文庫Hさんは果敢に脚立に上って三角のポリ袋を貼り付けていました。
電灯替えの時もそうでしたが、脚立に乗って作業していると目立つのか、必ずお客さまに本を尋ねられるのです。今ちょっと手が離せません状態で、しかも上から応えるのはなかなか至難の業です。最も手の離せない人ほどお客さまに声を掛けられるというのは、書店員ならみなさん身に覚えがありますよね。
そんな困ったちゃんなエアコンでしたが、「涼みに来たで」と言ってくださる方も多くおられました。そこそこ涼しくて長居が出来てトイレもある。真夏の本屋って結構役に立っていますよね。
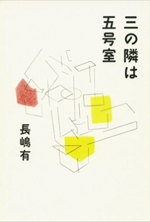 長嶋有『三の隣は五号室』
長嶋有『三の隣は五号室』
中央公論社 2016年6月発行
新刊が出た時に、好きな著者が自作について語るのって聞きたいと思いませんか。実はインターネット放送の「真夜中のニャーゴ」をライブで視聴したのです。長嶋有さんが出たての『三の隣は五号室』を持ってゲスト出演した番組です。深夜に見た甲斐がありましたよ。有さんは文章の面白さとご本人の面白さが一致する作家さんなんですよね。
この本の主役は横浜市郊外に1960年に建てられた第一藤岡荘というアパートの5号室です。歴代の5号室住人のテーマ別紀伝体というか、時間軸を行きつ戻りつしてその時々の住人の心情を定点観測したもの。初代住人でオーナーの息子である藤岡一平、2代目の二瓶夫妻、3代目は三輪密人、4代目の四元志郎から最後の13代目諸木十三まで、名前を見ればいつ頃住んでいた人か分かるようになっていて、有さんのサービス精神と遊び心がたのしい。
それぞれの住人同士には接点がなくても、同じ障子を開け閉てし停電やうるさい雨音にものを思い、同じホームセンターで道具を揃え、時には同じ動作で急須の茶葉を捨てたりする。それを俯瞰して見られるというのが何とも面白いのです。著者と読者だけがお風呂の水漏れの原因を知り、ガスの元栓にゴムホースが短く残されたいきさつを知っているのですから。
7代目七瀬奈々の話がぐっときます。奈々がいつもは乗らないタクシーに乗ったのは、高校時代の友人がラジオ番組にゲスト出演するのを聞きたいから。友人が人気漫画家になった、そのことが自分のことでないのに無闇にうれしい。風呂に入って居住まいを正して聞きたいしシャンパンも用意した。運転手さんに尋ねられても、そのことで嬉しいのは自分一人でいいから教えない。奈々は傷心を抱えていたけれど、「経年」によって回復し日当たりのいいマンションに引っ越してゆきます。嫉妬など微塵もないただうれしいという奈々の気持ち。男性である有さんが丁寧に描く真っ当な女心に、私はいつもまったく違和感を覚えません。
かつてこの部屋で過ごした者たちが十三に対して放った言葉は一様に「懐かしい」だ。なんて簡単になるんだろう。誰もかれも、すべての人が、簡単に生きたはずないのにな。
これは13代目諸木十三の感想。彼は素敵な送別会を経て仕事をリタイアし、のちに5号室で1人亡くなります。対象との時間的な距離が大きくなるにつれ、いろんな出来事もまとめて「懐かしい」という言葉に収斂されるのでしょう。おそらく、海文堂もその一言に。一文一文に発見がありエピソードがあるあるで、何度読み返しても面白いのが長嶋有さんなのです。この小説に関して著者は、小説にならなかった捨てアイデアをひっくるめて使った、と話していました。まさにアイデアの宝庫。捨てられなくてよかった!俳人でもある有さん。このタイトルは俳句の中七下五? 上五は秋の季語にして13代目にちなみ「障子貼る三の隣は五号室」なんてどうでしょうか。真面目すぎるかな。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.7月 (26)階段

(26)階段
「エレベーターかエスカレーターはないんですか?」
「はい、階段だけなんです」
「じゃあ上は見れないね」
海文堂で2階の売り場に上がっていただくには階段を上り下りするしかありませんでした。レジのIさんは荷物を預かるなどして手助けをしていましたし、手すりにつかまりながら一段一段上がって行かれる常連さんもおられました。けれど2階を見ていただくことができないお客さまもおられ、せっかく来店されたのに、とスタッフとしては大変残念な気持ちでした。
我々の中にも階段で苦労したスタッフがいました。ゴットさんが通勤途中に足を滑らせ骨折入院し、店に復帰したものの担当売り場は2階。日に何回も上り下りせねばならず、さぞ難儀したことでしょう。私自身もひざを痛めていた時期に、駅の階段との微妙な高さの違いを実感したことがありました。
この階段を上がりきった地点から、左手に踊り場、右手に2階売り場を見渡した絵が、「新・神戸の残り香」(神戸新聞総合出版センター)に掲載されています。故・成田一徹さんによって「頬打つ微かな潮風━海文堂書店」と題された切り絵です。成田さんは階段の赤い手すりを気に入っておられ、海の雑誌や港湾新聞、大漁旗、操舵輪などを入れて海の本屋を表現してくださいました。切り絵のもとになる写真を撮るために、ご自分で什器を動かしたりなさったそうです。平野さんの『海の本屋のはなし』のカバーをはずして見てください。本表紙の装画として使われています。在りし日の海文堂が切り絵作品として残されたというのはうれしいことですね。
階段の踊り場の壁には各所からお預かりしたポスターやチラシを貼っていました。チケットを販売していた美術展や映画、各種イベント、図書カードの柴犬くんも。日曜日の午前中、店長の姿が見えないなと思ったらたいていここにいて、熱心にレイアウトして貼っているのでした。
海文堂にはバックヤードにもう一つ階段がありました。タイムレコーダーも更衣室も食堂も2階にあるため、全員が使うスタッフ用の階段です。春の教科書販売を前に男性諸氏が重い机を2階に移動させた時のこと、腰をギクッとやってしまったのがあわれアカヘル氏です。彼はそのせいで最後の年の教科書搬入に参加できず、外商Hさんに借りを作ることになってしまったのでした。
お掃除のNさんが一段一段モップをかけていた姿も目に浮かびます。たかが階段ですが、結構ドラマがあったんですね。
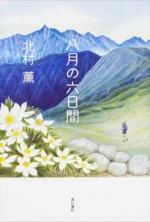 北村 薫『八月の六日間』
北村 薫『八月の六日間』
角川文庫 2016年6月発行
単行本で出たのが2014年5月。海文堂はもう無くなっていたけれど、しろやぎさんくろやぎさんはじめ、この本を高く評価する方々の声は届いていました。元顧客のバンドワゴンファンОさんもしかり。機会があれば、くらいに思っていたらもう機会が巡ってきました。文庫化、ちょっと早くないですか? これがとにかく噂にたがわず面白くて、予定していた本を中止してこちらで感想文を書きたくなったのですが…。
お話はいたってシンプル。出版社で編集の仕事をしている主人公の「わたし」の、5回に渡る山行の前日から下山までの行程を詳細に記録したもの。思索しつつ、会話しつつひたすら歩く山は「わたし」に乗り越える力を与えてくれる。などと要約するとあまりに単純すぎですが、ここはひとつ「しろやぎさん、くろやぎさんの往復書簡」7通目を読み直してみてください。この本の良さがよく分かります。なので今回は本文からの引用を中心に。
だが、今、手の中にあるのは《何か》の部品だ。自然に生まれ出るものではない。うちの中の何かから、それが欠け落ちたのだ。それでも、日常は何とか動いている。
その部品をどこに納めるか、あるいは納めないか。
空は、機嫌よく晴れ上がり、北アルプスがずっと見渡せる。山々に向かって、手を挙げ挨拶する。
私もかつて焼岳に向かって手を振ったこと、思い出しました。
そうだ。与えられたわたしだけが嬉しいのではない。偉そうな意見ではない。ごく自然に、与えられることによって、わたしも与えたのだ。喜びは、片方にあるのではない。その間にある。
giveとtakeのあいだにある、うれしいという気持ち。
「本持って来てるんですか!」「本ないと気が狂うんです」「だって重いじゃないですか」「心の安定には代えられません」
確かに心の安定のために持ち歩いているような気がします。
目を逸らせば、後悔する。これは、何か大きなものがわたしに与えてくれた機会だ。ひと言でいい。逃げずに、わたし達という物語に、時の句点を打とう。
この「ひと言」の、何げなさが持つ力。感動的です。集団行動が苦手で単独行を好む主人公は、人嫌いというよりは人との距離の取り方に繊細で、むしろ長所によく気がつく人柄。数年前に友を亡くし、また恋愛で大きな痛手を追っているのですがその経緯について読み手は知らされません。深い淵から脱出するためにただ山に登ります。話の持って行き方がうまくて泣かせるというのではない、もっと何か誠実な心根を著者に感じ、たいそう心地よい読後感となりました。全5回の山行のうち4回が近くを歩いたことのあるルートだったのもうれしく、私にも宝物のような山の記憶があることを思い出させてくれました。まったくの蛇足ですが「わたし」に言わずにおれない。夏山でも午後4時に山小屋に入るのは遅すぎ。天気変わって危険ですよ。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.6月 (25)自分の棚

(25)自分の棚
この「海文堂のお道具箱」は、典型的な街の本屋であった海文堂の、典型的ならざる面を知っていただきたくて書き始めました。変わっていたり、独自だったり、時にはちょっと恥ずかしかったりした記憶を書いています。もし、もしもですが、書店員の方でなにか仕事の参考になるかと思われた方がいらしたら、ごめんなさいね。棚作りや発注の奥の手、アンテナの張り方などについてはしかるべき人が書いてくれるといいのですが。
私は海文堂では文芸書と新書を長く担当していました。自分の担当していた棚について書くのは実は大変気恥ずかしいことです。不思議なもので、一人でも多くのお客さまに自分の棚を見てもらいたくて、こんなことやってますよとアピールしたりする反面、来られた方が同業者と分かった途端に穴があったら入りたい状態に陥ってしまうのです。まったく自意識過剰です。書店員としての底の浅さを見破られてしまう恐怖というのでしょうか。書店員さんならその気持ちわかってくれるかなあ。
文芸書が本屋の花形だった時代の面影を残していた海文堂は、結構広いスペースの文芸棚を持っていました。それを小分類して管理するのですが得意な棚、苦手な棚というのが出来てしまいます。苦手な棚は次々出る新刊書を入れ替えるだけの棚になってしまうので、そのジャンルを好きな人にはなんとも物足りない棚に見えるはずです。私は新刊の多すぎるエンタテインメント(ミステリ・SF・ファンタジー等)というジャンルが苦手で、ついにいい棚を作ることができませんでした。それでは新しい作家を見つけたいお客さまに来てもらえませんよね。
一番好きな棚は外文の棚でした。翻訳ものの書籍は装丁もかっこいいものが多く、クレストブックスやエクス・リブリスのシリーズは置いているだけで格が上がる気がしました。棚は手を加えれば育って行くものです。この棚が好きと思えたら、それはすでに棚と担当者の心が通い合った証拠かもしれません。自分の棚の完成形が見えてきたということなのではないかと。うふふ、もう見られる心配がないので偉そうなこと書いています。
他のスタッフが自分の担当棚についてどう思っていたか、そんな話はしたことがなかったなあ。うれしいことに、唯一アカヘル氏が作っていた棚の進化した形だけは、今も見ることができます。きっと凝りに凝った面白い棚を作っていることでしょう。スタンダードブックストアあべので、8月までやっているイベントの名は「本棚編集術」。こんなテーマで閉じられていないワークショップを思いつくなんてすごい。私も教えてもらいたかったよ。まじで!
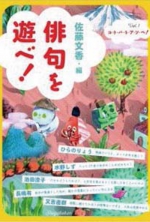 『コ・ト・バ・を・ア・ソ・ベ!vol.1「俳句を遊べ!」』
『コ・ト・バ・を・ア・ソ・ベ!vol.1「俳句を遊べ!」』
小学館SJムック 2016年3月発行
これ、ムックなんです。ムックというのはマガジンとブックを合わせた造語で、雑誌扱いの書籍のこと。これが雑誌売り場に置かれていたら私は出合えなかったと思う。必ず覗く文芸書の詩歌俳句棚に面陳していたから発見できました。ムックは新刊情報に載っていないことも多いので、見つけられたのは偶然ですね。
俳句初心者向けに編まれたこのムック、俳人の佐藤文香さんが、俳句はまったく初めての若い2人(アイドルの水野しずさんとアニメ作家のひらのりょうさん)に教えるところから始まります。まずは自己紹介句を、次は季語と3音と5音の組み合わせの面白さだけで俳句を作ってみる。その時の注意は自意識を織り込まないことととりあえずたくさん作ること。初心者が作ってみて、先生が添削や説明をし、生徒が納得したり質問したりする構成が、私にはとても面白いのです。大変お恥ずかしいですが私、海文堂のお客さま関連で知った俳人の方のお誘いで、句会にお邪魔したことがあるのです。先日の句会は15人参加で、三句投句の三句選句だったのですが私の句は見事沈没。全然俳句のセンスがわかっていないんですね。
という理由でこのムックを手に取ることになったのでした。俳句入門者向けの本は数々あれど、こういう臨場感のある本なら一緒に学べるかも、と。ここに登場している生徒さん2人はめきめき上達し、ツボを押さえた面白い句を次々詠んでいきます。作句や鑑賞のゲームをし、池田澄子さんや長嶋有さん参加の上野動物園吟行句会にも同行して堂々と渡り合って。この本を選んだ理由のひとつは俳句する長嶋有さんの言葉を読みたかったからでもあるのです。有さんの動物園での一句。
獏の池に冬日差し込み獏は留守
こういうツッコミのような俳句好きです。
以下、気になったポイントを箇条書きに。
★季語にはその言葉以外の広い世界が内包されている。
★選句しあうということは人を評価しあうことである。
★言いたいことはたくさんあっても諦めてしぼる。
★視点の有る場所を明らかにする。
★写真は漫然と撮ると退屈なものになる。俳句も同じ。
ほかには公開俳句イベントの様子や又吉文豪と佐藤文香さんの対談、早わかり俳句の歴史も掲載。超初心者向きとはいえ俳句の難しさがよく分かりました。そろそろ一歩進んだ俳句の本を読んでみようかな。最後にここで一句。それは俳人よーまる氏にお任せしますね。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.5月 (24)書評棚

(24)書評棚
書評に載った本を一か所にまとめている本屋さんって助かります。この本をこの店ではどのジャンルに分類するのだろうと推測するのは楽しいけれど、広い店内を探すのは大変。人文系の本は特に、担当者によって収める棚が違うことありますよね。書店によっては切り抜いた書評のファイルを置いていたりして、いろいろ読めてうれしい。
実は海文堂にも新聞書評に載った本を集めた棚がありました。なじみのお客様から店長に、「探しにくいからどっかに集めてえな」と提案があったようで、人文新刊台の奥の方、岩波書店新刊棚の隣に2段設けることになったのです。私が担当に指名され、神戸、朝日、日経の3新聞の日曜書評を対象にすることとなりました。ただ在庫が掲載書の半分くらいしかないこともあり、やや貧弱な棚ではありましたね。
神戸新聞は店で購読していたのですが、朝日と日経は書評掲載情報をネットで集めなくてはなりません。頼りにしていた某サイトの更新が掲載の翌日中だし、担当の私は隔週日曜休みで月曜は図書館納品優先。なので遅いかなあと思いながらも、書評棚は毎週火曜日に更新していました。待ちきれなかったのはお客様ではなく平野さんでした。私が日曜休日のあと月曜に出勤してみればすでに書評棚は入れ替わっており、手間が省けて助かるものの、何か私の立場ないよなあとぼやいたものでありました。
書評棚がお客様に好評だったという印象は残念ながらないのですが、書評担当としては本を知る良い機会になったように思います。書評をよく読むようになると、どの本が売れているかよりも、どの本の評価が高いか(もちろん書評子あるいは掲載紙にとって、です)が分かるようになります。複数の書評に載る本は問い合わせも多く、店に入荷していなくても、タイトルが不正確でも特定できるようになりました。新聞書評の書目と海文堂のお客様は親和性が高いように感じます。
掲載は本の発売直後のこともあれば2カ月以上経ってからのこともあり、売れ始める時期を左右する力を持っています。載るか載らないか、また何に載るかは版元にとって大変重要な問題でしょう。市場での評価を知るという意味で、私は新聞書評に大きな信頼を寄せていました。
書評棚とは別に、自分の担当ジャンルで活用していたのが日経新聞水曜夕刊の星取り書評でした。4つか5つの星を取った文芸書と新書の書評を切り抜いて、厚紙に貼りポップとして使いました。自分でキャッチコピーを書くのは苦手だし、はるかに説得力があったのではと思っています。
書き手の皆さんには、買ってでも読みたくなるような書評を書いていただきたい。クールな本の紹介ではなくて、熱く推薦してほしいですね。本選びの指標として本好きを導いてくれ、本屋に足を運ばせ、ついでに他の本も一緒に買わせるような書評を、是非。とはいえ書評に取りあげられる本は出版物のごく一部。それ以外の優れた本とは、やっぱり本屋に足を運んで出会ってくださいね。
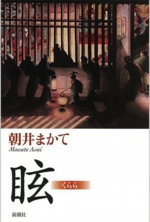 朝井まかて・著『眩(くらら)』
朝井まかて・著『眩(くらら)』
新潮社 2016年3月発行
本に関する情報量が本屋で働いていた頃より断然少ない今、読んだことのない作家の単行本にはなかなか手が出せません。もともと保守的で慎重な本選びだったのが更に。でもこの本は刊行前から買おうと決めていました。『眩(くらら)』の主人公に興味があったからです。
『次の本へ』のきっかけ別インデックスだと「一冊目に出てきた人のことが書いてある本を読みたくなって」に当たるでしょうか。その一冊目は杉浦日向子の漫画『百日紅』で、主人公は葛飾北斎とその娘で浮世絵師の応為(本名は栄)。『百日紅』のお栄は23歳で未婚。『眩』のお栄は結婚して3年で離縁して以降。後日譚が読めてうれしい!と思うけれど、書き手が違うのだからまかてさんにとっては不本意な読まれ方なんでしょうか。ともあれ、北斎と応為の作品をめぐる形で章立てされたこの評伝小説、たいそう面白いのです。日経新聞夕刊書評の星取りで、早々5つ星(満点)を獲得しています。
お栄のキャラクターは両者共通していて、ぶっきらぼうでめんどくさがり。身づくろいや部屋をきれいにすることには興味がなく、ひたすら絵を描きたい。そのためには手間を厭わず顔料作りに精を出し、光と色の関係を思い詰める。密かな想い人が善次郎(のちの渓斎英泉)とはびっくりだけど、この善次郎、遊び人の色気と言うか、たいそう格好いいのです。英泉の描く遊女って下唇がつき出ていて変な顔だし指は不自然に曲がっています。これがいいのか?と思っていたらお栄が替わりに言ってくれました。
「ちっとも、いい女に見えないけどね」
「しゃらくせぇ。お前ぇに女の色気がわかってたまるか」
はは、確かにそうかもしれませんね。
超一流の絵師である北斎がなぜ一生長屋の貧乏暮らしだったのか。絵の話の出来るただ一人だった善さんとの別れ。「御改革」の横暴。終わりに近づく江戸で、お栄の暮らしも変わって行きます。
有名な応為の肉筆画「三曲合奏図」を描くシーン。
画面ではなく、彼女らの人生の束の間、その場面を描こう。そうしたら三人は琴や三味線、胡弓を弾きながら溜息を吐き、泣き、笑うことができるだろう。
琴の遊女、三味線の芸者、胡弓の町娘。架空の3人なのに三者三様の人物像がお栄の頭の中には出来上がっていて、思いや野心や恋愛経験まで、まるで長い付き合いの友人のように知り尽くしています。小説も同じ。すべての登場人物の発言や行動には必ず合理的な理由がある。だからこそ、優れた作家は彼らの人生の一瞬を切り取り、場面を描くことができるのでしょう。
北斎が絶筆「富士越龍図」を描く場面は心に染みる美しさです。北斎が、続いてお栄が老境に差し掛かり、齢を感じさせるくだりに胸を突かれます。若き日の彼らは(私が読み始めたほんの4、5日前は)あんなにいきいきと元気だったのに。本の時間は容赦なしに主人公に歳を取らせるのですね。
さて、またもや『次の本へ』的には、「その著者の別の本が読みたくなって」ということになるのでしょうか。朝井まかての直木賞受賞作『恋歌』から読んでみましょうっと。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.4月 (23)外商(公共図書館編)

(23)外商(公共図書館編)
お道具箱⑪に教科書販売のことを書きましたが、今回はもう1人の外商担当者による図書館への納品について。海文堂は神戸市にある公共図書館のうち6館に本を納品していました。毎週末、学参Sさんの手によって切り分けられ分類された注文短冊が、ジャンル担当者のボックス(個別のポストのこと)に入れられます。ジャンル担当者は店の棚や平台から本を集め、短冊をはさんで段ボールに詰めて行きます。店になかった本の短冊は取次行きの封筒に。集められた本は2階の一室でコーティングがほどこされます。これが結構むずかしいのだそうです。素人がすると皺になって取り返しがつかないとか。専任のN子ちゃんたちが上手に仕上げてやっと各図書館に納品できるのです。もっと工程があるのかもしれませんが私が知っているのはこれだけです。
ちなみに、外商のスタッフであるN子ちゃんは大変美しい人でしたが、店頭に立つことがないのでお客さまにその美貌を知られることもなく、あの部屋に閉じ込めておくのはもったいないなとずっと私は思っておりました。
毎週たくさんの書籍が図書館に運ばれていました。私の担当ジャンル(文芸書と新書)だけでも3~4箱はあり、ブックトラックで棚前を行きつ戻りつしたものです。この作業、私わりと好きでした。分厚い短冊を効率よく分類して片付けてゆくという感じが。ただ10年前と比べたら少しずつ注文数が減って来ていた感じはありましたね。辛かったのは、店で売りたい本も納品すること。やっと重版分が入荷したというタイミングで、図書館からの注文が来るんですよね。反対に海文堂で売れにくい若手の作家の本などは、納品することで過剰在庫にならずに済みました。
何らかの奥の手を使って外商Yさんが入手した売れ筋の本を「これ余ったから店で使って」ともらえることもあり、その時はとても助かりました。
図書館分と店売分を足した冊数が取次から配本されるわけですから、注文が来るまでの数日間店で平積みできるのはありがたいことでした。外商のおかげで海文堂の店売は、版元から実力以上に評価されていたかもしれませんね。
私たち海文堂スタッフの手を経て図書館に届けられた本たちが、今も神戸のみなさんに貸し出され、また棚で手に取られるのを待っていると思うとなんだかうれしくなります。本の命って永い。今さらながら、永く可愛がられるんだよと声をかけたくなりました。
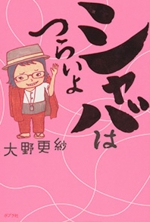 大野更紗・著『シャバはつらいよ』
大野更紗・著『シャバはつらいよ』
ポプラ文庫 2016年2月発行
海文堂の社会福祉の棚(平野さん担当)は店の東側の壁に沿って歩くと一番奥にあり、私が担当する詩歌・俳句の棚と並んでいました。自分の棚を整理しながらお隣をちらちら見ていると、布団から顔を出しているメガネの子が描かれた本が、ずいぶん長い間面陳されていました。福祉の棚にはめずらしいイラストの表紙に著者の名前も学者っぽくない。帯には“絶賛生存中”と。その後書評やインタビューで幾度も取り上げられたノンフィクション、大野更紗・著『困っている人』 (ポプラ社、現在ポプラ文庫も)でした。
ミャンマー研究のために大学院へ入ってすぐに原因はおろか病名さえ不明の病魔に襲われ、休学を余儀なくされた更紗さん。病院をさまよった果てにわかったのは自己免疫疾患系の、日本でも稀なる難病でした。本書『シャバはつらいよ』はその続編にあたり、困っている難病女子が1人暮らしをせんと9カ月間の入院生活を終えて退院する日から始まります。新しい住まいの鍵を開けることやドアを開くことにさえ全力必要な更紗さんが、自立することはできるのか。
東日本大震災時、東京の住まいでは食べ物も手に入らず清拭のためのお湯も出ない。著者は福島県出身で両親やおばあちゃんの心配も。そんな時でもヘルパーさんや区の相談支援員さん、つぶやけばさらりと手伝いに来てくれるボランティアさんなどさまざまな人の手を借りて、命の崖っぷちを越えてゆきます。
現実的に、難病体なので、力仕事で震災のお役に立つのは無理だ。わたしにできることは、どんな状況にあっても、絶望しないで生きていける社会のシステムを作ることを「考える」ことくらいだと思った。
震災時に、健常者以上に命の危険にさらされた人たち、つまり生命維持のために医療的ケアが常時必要な人たちに対して、自分なら何ができるか考えた更紗さん。ホームページを起ち上げて「見えない障害」バッジを作り、なんと社会保障のシステムを研究するために、ふたたび大学院生になるのです。社会に役立ちたいという強い欲求を持って。
病気を力にするたくましさ。でもいつも前向きなわけでは無くて、生きていることに疑問を感じたり、難病つながりの彼氏との齟齬に悩んだり。若い女性の感受性も随所にかいま見え、共感せずにいられません。
電動車椅子を手に入れて研究生活をおくる彼女が、自身の考えたシステムによって、他の難病の方々と共に生きやすく暮らしやすい日々を取り戻してくれることを期待しています。健常者は見えない難病を抱えた人がいることを忘れずにいなくっちゃね。彼女の今後に要注目です。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.3月 (22)3.11

(22)3.11
2011年3月11日、店頭で立ち働いている私たちが地震に気づくことはありませんでした。神戸は震源地からあまりにも遠く離れていました。その日は昼過ぎに岩波書店の営業Yさんが来られて店長が応対していました。Yさんにたぶん本社から連絡が入ったのでしょう。作業場に入った私は店長から声をかけられました。「地震があったらしいで。津波警報が出てるって」「津波って警報出てもいつも10センチくらいですよね」とバカみたいに答えた私に営業Y氏は蒼くなって言いました。「映像では家が流されてるみたいです…」
東京は大混乱らしく、新幹線も止まっているようでYさんはどのように帰社されたのだか。被害の大きさを知ったのは夜、家に帰ってからのことでした。
こんな取るに足らない当日の記憶を書いたのは、被災していない自分が被災者や被災地を想い続けることの難しさを感じるからです。阪神・淡路大震災の時、神戸から遠く離れた地の方も同様だったことでしょう。心を寄せてはいても、痛みを伴う体験がなければ震災の記憶もつい途絶えがちに。たぶんその後のフェアと販売がなければ、私には当日の店での記憶とテレビの残像だけしか残らなかったかもしれません。
そのフェアとは被災した仙台の出版社、荒蝦夷の大規模なフェアのことです。荒蝦夷の土方さんからの電話に、「既刊を全点送ってください。平台空けて待ってます」と答えた平野さんの働きで、本を売ることが何より被災版元の助けになるという当たり前のことが実行できました。海文堂晩年最大のフェアが震災関連だったことで、私の震災の記憶と本屋の仕事がつながりました。このフェアが大きな反響を呼び新聞等に取りあげられたことは、2年半後の閉店時に多くの方々が惜しんでくださった遠因になったのかもしれないと感じています。
もうひとつは、被災し、しかし唯一残った蔵にあった着物をほどいて作られたブックカバーを販売できたこと。気仙沼ほどーるのお2人による心のこもった丁寧な手仕事はとても評判がよく、何度も追加をお願いしました。荒蝦夷のフェアにしてもほどーるのブックカバーにしても、買ってくださる方があってこそ。海文堂のお客さまはやはり震災に敏感でした。
その荒蝦夷代表土方正志さんの著書が先ごろ発行されました。タイトルは『震災編集者』(河出書房新社)。この5年間、仙台在住の編集者として小さな出版社の経営者として、また被災者の1人として東日本大震災と向き合った記録です。
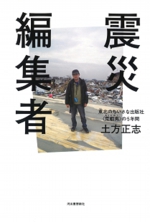 土方正志・著『震災編集者』
土方正志・著『震災編集者』
河出書房新社 2016年2月発行
さて、震災からの「復興」とは何か。たとえば、阪神・淡路大震災から一五年を経た神戸は復興したように見える。だが、今私たちが目にしている神戸は、けっして震災以前の神戸が「復旧」や「復興」を果たした姿ではない。むしろ、似て非なる神戸だ。〈復〉なる神戸ではなく、〈新〉なる神戸なのだ。
被災地の〈旧〉がどのようなものであったかも知らない私たちが、天気の話でもするように「だいぶ復旧しましたか?」などと尋ねることの愚かしさ。失われた風景抜きの、流され壊された住まい抜きの、亡くなった人抜きの〈復〉でしかないのですね。震災5年目の節目に、改めてその日とその日以降について考える機会をいただきました。多くの人に読んでもらいたい。土方さんたちがとにかく無事に活動を続けておられることを嬉しく、心強く思います。
本書では海文堂との接点に多く紙面を割いてくださっています。平野さんの本が出た時もそうでしたが、書籍を商っていた海文堂のことが活字に組まれ、書籍という形になって目の前にある。そのことに大きな喜びを感じます。海文堂は本屋の落ちこぼれではありますが、働いてきた証が本になったことの意義を思わずにいられません。感謝!です。
3.11と共に、3.11を忘れずにいさせてくれる人たちのことも、大切な記憶として留めておきたいと思います。
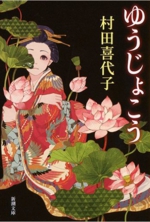 村田喜代子・著『ゆうじょこう』
村田喜代子・著『ゆうじょこう』
新潮文庫 2016年1月発行
青井イチは硫黄島から熊本の大きな遊郭に売られてきた15歳の少女。島の言葉しか知らないけれど平家の落人系の美人顔と海女育ちの締まった身体を持ち、遊郭一の花魁付きになって女郎修行を始めます。
舞台は明治36年。江戸時代の廓と違って女紅場(じょこうば)という学校で修身や読み書き、裁縫などが学べたのですね。没落武家から売られ年季を終えた鐵子先生のもと、イチは学校に熱心に通います。客に誘いの手紙を書くべく教えられた文字を使い、朋輩の病死や逃走、花魁の出産、親の追借金など、様々な経験を書き続けるのは鐵子先生という読み手を得たから。鐵子先生は島言葉の素朴な作文を読んで、イチや若い娼妓の気持ちに寄り添います。
時代は救世軍や県議会が勢いを増し、楼主は娼妓の廃業を受け入れざるを得ない状況になってきていました。やがてイチの遊郭で35人もの娼妓がストライキに加わって……。
娼妓にとって遊郭は仕事場です。親が受け取った借金を返すため、日夜稼ぐところ。イチが花魁から心構えや手練手管を教えられ、遣り手婆から“精緻精妙微妙凄絶な技術”を実地で習うのは新入社員が仕事を習うのと同じこと。そう、「ゆうじょこう」は働く女の職場小説であり、客を取ることを労働として描いている点が面白いのです。
著者の目は鐵子先生の目となって、福沢諭吉の文章に対してどこが人の上に人を作らずだと批判し、娼妓解放令が別名牛馬切りほどき令と呼ばれるその言い草に憤ります。遊女の現状や明治政府に異議を唱える賢い女性として鐵子先生が描かれることに著者の姿勢を強く感じます。
遣り手婆による実地訓練の描写はとてもリアルで、びっくりするほどドライです。あくまでも女の目から見た廓なのです。遊女小説につきものの客と娼妓のロマンスなどありません。著者はベールに包まれた遊郭など書くつもりはなく、男の客の視点を徹底して除いたのではないかと思うのです。
「時間がすぎれば、客は帰って行く。後はさばさばと寝床をかたづけるだけ。その他の時間は、誰のものでもない、自分の体でありんす。あちきが思うに、世に娼妓ほど自由なおなごはいない」
と言っていた遊郭一の花魁東雲太夫は、ストライキの果てに楼主に向かってこう言います。
「それでも」と東雲さんは顔を上げて茂平を真っ直ぐに見た。「それでもお前様は、人を売り買いしなさんした」
東雲楼は大きな遊郭で、娼妓にしては比較的恵まれた環境だったかもしれません。それでも「人を売り買いする」と言う一点に置いて許せないと感じたそのことが、著者の執筆の動機となったのではないでしょうか。
遊郭の描写は杉浦日向子の絵が目に浮かび、状況がすっと頭に入りました。私はこういう小説が読みたかったんだ!と思える大満足の読書体験となりました。
(三毛小熊猫・元書店員)
2016.1月 (21)ベストセラー

(21)ベストセラー
新聞の読書欄の片隅に載っているベストセラー。各地でどんな本が売れているのか、その本屋さんがどんな傾向なのか分かりますよね。ビジネス書が強かったり実用書がいつも上位だったり。掲載されたベストセラーを見て憧れていたのが東京堂書店さん。発売されたばかりの純文学作品がずらりと上位に。こんな本がこんなに売れる本屋があるのか…かっこいいー!といつも感嘆符付きで見ていました。
海文堂も店内掲示だけでなく、いくつかの新聞社や週報にベストを発表していました。各ジャンル担当者がよく売れた本の冊数をスリップに記入して、取りまとめ役の文庫Hさんに提出。Hさんはきれいに清書して各社に送信していました。締め切りは毎週水曜日ですが、祝日と重なると締め切りが早まり、予想数でもいいから出してねと。予想と言われてもねえ。いつもすごく売れる本があるわけでは無く、時にはこんな冊数でベストと言っていいのかというほど不作の週もありました。
他書店のベストデータはたぶん、ポスレジから取っておられるのでしょうね。何が何冊売れたか一目瞭然ですもんね。海文堂はもちろん違いました。どの本が何冊売れたか把握しているのはジャンル担当者だけ。海文堂はスリップですべてを管理するというアナログな店でしたが、集計の方法は人それぞれ好き勝手なやり方でした。私は新刊台帳で単品管理していたけれど、みんなはどうやってベストを把握してたんだろう。謎です。
ベストセラーから見た海文堂はどんな本屋か。取次発表のベストテンとはかなり違っていました。まずは地元密着型書店。神戸や地元に関連する本なら版元がメジャー、マイナーにかかわりなく上位に。店として売りたいという心意気の感じられる、誇れるベストだと思います。続いては文芸系標準型書店。大手版元から出た著名作家の新刊も上位に。こちらは店からはあまり売れていなくても、公共図書館納品分をプラスするのでベスト入りすることがありました。時に知る人ぞ知る児童書の新刊が1位になることも。これは児童書担当Tさんの営業力の賜物です。と言うよりは人望や信頼感と言った方がいいかな。児童書あっての海文堂という面がありましたしね。
ということは、地元本や児童書などに強みがありつついわゆる”売れる”新刊も売れる、神戸元町に根を生やした街の本屋ってとこでしょうか。東京堂書店さんのようにかっこよくはないけれど、海文堂のベストは体を表す、でしたね。
 岸本佐知子 三浦しをん 吉田篤弘 吉田浩美・著『「罪と罰」を読まない』
岸本佐知子 三浦しをん 吉田篤弘 吉田浩美・著『「罪と罰」を読まない』
文藝春秋 2015年12月発行
『罪と罰』はロシアの文豪ドストエフスキーのあの世界的名作のこと。ここで“あの”と言ったのは、私を含めた大方の人が『罪と罰』を(少なくとも何となくは)知っているという前提があるからです。じゃあどの程度知っているのかと聞かれたら、私の場合、
「えーと、ドストエフスキーが書いた世界的名作のひとつで、新潮文庫に入ってて分厚いの」
ぐらいしか言えません。こんなに何も知らなかったんだ!
この本は『罪と罰』を読んでいない4人が、もれ聞いて知っていた情報を持ち寄ってどんな作品なのかを推測して鑑賞するという、「仲間うちのお遊びを本にしちゃった」本です。これが面白いのです。
とにかくこのメンバーがいい。しをんさん小説家、岸本さん翻訳家、吉田夫妻はクラフト・エヴィング商會で作家、装丁、デザインなど。ふだんから仕事に遊びにと仲良しの4人。読んだ人と読んでいない人に内容を尋ねるとほとんど変わらない(読んだ人でも内容をよく覚えていない)ことが分かり、ならば読まずに読書会をしてみようということになったそう。
まずは冒頭とラストだけを頼りに内容を推測。ヒントをもらいながらあてずっぽうに1ページだけ読んでみたり。過去に読んでいて、しかもしっかり中身を覚えている人のひんしゅくを買うかもしれないほど自由に、想像力豊かに語り合います。
何となくお人柄は知っているけれど、4人の座談会となると役割分担というものが発生しますよね。しをんさんの推理がすごい。時に暴走し岸本さんも加担して言いたい放題。篤弘さんは軌道修正係で文学的に推理。浩美さんは短い発言ながら癒し系。自分ならだれの役割に近いかなと考えながら読みすすめました。
そして最後には『罪と罰』を読んでからの合評会。著者の心理分析や文芸評論といった堅苦しいものは一切なく、とことん感想に徹しているのが愉快。
篤弘 ルージンがスティーブ・ブシェミなら、スベはだれだろう。
三浦 ヴィゴ・モーテンセンはどうでしょうか。
岸本 あ、いいかも。
浩美 ああ、ヴィゴ、ぴったりだね。
三浦 うふふ、超素敵! ほら、もうみんなスベの虜ですよ。
読書は一人でするものだけど、みんなで読んでみんなで語り合うのもいいなと思わせる、個性あふれる賑やかな座談会でした。
思えば読んでいない本の話をするということは、書店員にはよくあることなのです。注文数を決めるために読まずに判定し、お客さまにも紹介します。不遜ですよね。あとで読んでびっくり。全然違ってたやん!てなこともありました。でもこの本のように敬意さえあれば許されますかね。同じ“本を使った遊び”でも勝ち負けのあるビブリオバトルに対して、未読読書会は最後に読んで答え合わせをして平和的。図書館等で流行るかも?
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.12月 (20)中央カウンター

(20)中央カウンター
海文堂ってどんな店?の問いがあったとして、中央カウンターに特長があったねというのが答えのひとつかもしれません。仙台の書店員だった当時の佐藤ジュンコさんが「ひらかれたきもちのよいテーブルのよう」と描いてくださったおかげで、海文堂の中央カウンターの値打ちがぐっと上がりました。書籍検索や客注品の取り置き場所というだけでなく、顧客の方々がくつろいで本の話をされる場でもあったからでしょう。腰かけが2脚あり、常連さんはまずその席に着いてから用件を切り出されました。店員とお客さまが対面して座る、店長自慢の腰かけでした。
客注の多さは常連さんの多さに比例するような気がします。他店で見つけても、わざわざ海文堂で取り寄せしてまで買おうとしてくださる顧客の方が、結構いらしたのです。
「ここをまっすぐ行かれた所にあるご案内カウンターで係のものが承ります」
これが、即答できない本の問い合わせがあった時の、レジ要員の定番の答えでした。人数がぎりぎりでレジから出られないこともあって、とにかく問合せに応えるのは中央カウンターの仕事だったのです。
新聞の切り抜きやデータの揃った問合せならよいのですが、お客さまの記憶の断片だけでお探しの本を推測するのは至難の業です。パズルがかちりとはまって書名がわかり、しかもそれが店に有った時には何とも言えない達成感がありましたね。
カウンター内の実務は主に専任のYさんと児童書Tさん、文庫Hさんの3人で行っていました。専任Yさんは学生時代に海文堂でアルバイトをしていて、その後子育てが一段落して復活した出戻りスタッフです。入荷しない客注品の再手配や、受け取りに来られないお客さまに督促の電話をかけるというようなしんどい仕事も果敢にこなしていました。『海の本屋のはなし』の中の彼女の語りを読んで、実はこの空間が最も海文堂らしかったのだ、とぼんやりの私は教えられたのでした。
児童書Tさんから聞いた話。中央カウンターの背中側にはご自由にお持ちくださいの棚がありました。そこに「ちくま」や「波」などのPR誌も並べていて、月末から月初にかけての発行時期に何人もの方が入手せんと来店されます。男性が多く、その方々はなぜか一人ずつ順序良く、黙って一人が選んで取って、次の一人が選んで取ってと、決して同時に来られることがありませんでした。集中と閑散を繰り返すレジとは大違いです。
「棚陰で待ってはるのかな」
「暗黙のルールがあるのかも」
などと言い合ったものです。この方たちもきっと、海文堂閉店を惜しんでくださったことでしょう。
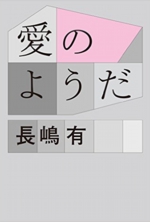 長島 有・著『愛のようだ』リトルモア 2015年11月発行
長島 有・著『愛のようだ』リトルモア 2015年11月発行
長嶋有さんの小説は、是非2回読んでください。1回読んだだけでは味わえない滋味があるのです。ストーリーを追って行くタイプの小説ではないので、じっくり文章を読んで言葉の綾を楽しんでほしいのです。
この『愛のようだ』、プロローグが「俺」の免許取得の話で、それ以外は全部「俺」がそれぞれ違う目的地に向かうドライブの話です。けれど語り手の「俺」にとって、数日間の旅でも印象に残っていることは一部分だけ。その部分だけがクローズアップされる、「俺」の記憶の物語、なのです。
目的地は伊勢神宮に始まり、群馬県草津温泉、富山県氷見、岡山の街、そして軽井沢。そこへ行くためのドライブなのに、ついに目的地に到着しての場面は出てきません。車で移動し、車内で会話し音楽を聴き、たまに過去を回想し、サービスエリアでくつろぐ。それぞれの道行きのハイライトは、琴美が帽子と一緒にかつらをばっと取るシーン。十二指腸のようなくねくね道を命がけで峠越え。葬式に出る水谷さん(女性)を男3人でからかいつつ内省する「俺」の女性論。メールで突然振られた神山が、トンネル内で車から出ようとする場面等、心打たせたり笑わせたり。
ハイライトのシーンの前後には、車あるあるや薀蓄や、ぐっとくるセリフや至言名言が満載です。貼った付箋が邪魔になるくらい。有さんっぽい表現を見つけると、あーこれなのよと再会できた喜びを感じます。
ある種の女は、からかうことは異性への親しみの表現だと思っている。からかいは、相手が明らかにそれを望んでいるときか、そうでなければ、からかうことで相手にむしろ立つ瀬が生じる時の助けとしてのみするべきだ。
ずっと斜に構えて生きてきて、気づいたら、大事な人に大事なことを言いそびれて、そしてこれからもずっと、言いそびれたままだ。
控えめながら、これは(からかいの意味ではなく)四十男の「俺」の失恋の物語なのです。有さんの小説の主人公が「変な気持ち→恋に落ちた」を自覚してくれてうれしいよ(えらそー)。この通奏低音が男たちのホントっぽい会話(時にバカ話)をちょっと切ないものにして、ハイライトの面白さを際立てます。
長嶋有氏は72年生まれ。同時代の人ならピンとくるであろうキン肉マンや北斗の拳、トラック野郎、奥田民生等たくさんの歌が車内で流れます。それらの曲を知らないで面白かったなんて言うなと言われそうですが、如何せん世代が違う(もちろんこちらが上)。全部知っていたら彼らと一緒に歌いたかった。車の中でさびの部分を合唱するところ、大好きなシーンなんです。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.11月 (19)ギャラリー

(19)ギャラリー
私が入社した当時、その数年前まで常設のギャラリーとして使われていた海文堂2階の広い部屋は、什器や備品の保管庫になっていました。やがてそこをスポット催事で使うようになり、スタッフはギャラリーと呼んでいたけれど、イベントスペースとして使われることが多くなりました。数多くのイベントが行われましたが、最も話題になったのはやはり一連の古本市でしょう。残念ながら私はこれらの催事にはかかわっておらず、ここで何も書けません。古本者の皆さん、お許しください。
ギャラリー利用で私が印象に残っている筆頭は池澤夏樹氏の朗読会です。お客様から「なんで海文堂(なんか)で?」という声があったほど、確かに海文堂には似つかわしくないビッグなゲストですね。新潮社の凄腕営業Iさんの計らいで実現しました。著者本人の声で読まれる朗読の素晴らしさ。なごやかないい会でしたね。
もうひとつは、長嶋有さんにインタビューする場所として使っていただいたこと。タウン誌の関係者Yさんが店長の友達だったことで実現。有さんはギャラリーで開催中の「記憶のなかの神戸」展をご覧になって、在廊していた著者から画集も購入。律儀でとても感じのいい方でした。
私がかかわったギャラリーのイベントは数少ないけれど、直接幾人かの作家さんと接したことは本屋時代の大事な記憶となりました。その方たちの著書を棚や平台で“優遇”することはもうできません。ただ、ご本人のお声やまとう雰囲気を、作品とひっくるめて読むようになりました。それはやはりお会いする前とはずいぶん大きく違うことなのです。
あと忘れられないのは、有志の方々が開いてくださった海文堂お疲れさまパーティーですね。忙しいみなさん方が時間をやりくりして私たちスタッフを招待してくれました。それがギャラリーでの最後のイベントとなりました。
催事のない時、私たちは通過するためだけにギャラリーに入室するので電灯は付けません。明るい店内から一歩足を踏み入れると真っ暗で、ぶつからない様に手探りで歩くことになります。恐くて摺り足で歩いていた私ですが、この闇を走って通過する人がいました。
内線で呼ばれた休憩中のゴットさんや学参Sさんが駆けつける時の近道がギャラリーの通り抜けなのです。コの字の形の部屋は曲がり角もあり、大きな鏡にギョッとしたりもするのですが、彼らが暗闇を駆け抜けて2階の売り場と食堂を往復する姿はまるで忍者のようでしたよ。
画家さんをはじめ、長い歴史の海文堂ギャラリーとかかわってくださった方は大勢おられるでしょう。みなさんにとっての大切な思い出も、私のこんなささやかな記憶も、海文堂と同時に消えてしまわないようにすべて小箱に入れて空想のギャラリーに展示しておきましょう。
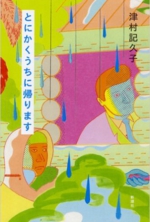 津村記久子・著『とにかくうちに帰ります』新潮文庫 2015年10月発行
津村記久子・著『とにかくうちに帰ります』新潮文庫 2015年10月発行
エンターテインメントとは違った描き方で働く日々を小説にする津村さんは、登場人物と私の住んでいる世界が近いことを実感する数少ない純文学作家です。仕事の段取りから人間関係や日々のやりとり、会話の機微まで、目の届きにくいところに繊細な視線を向けているのが魅力です。労働は、大人になってからの人生の中で睡眠の次ぐらいに多くの時間を占めるものなのに、なぜか恋愛ほど多くの小説が書かれていませんよね。あまりにも日常的でドラマチックとは無縁の仕事でも、丁寧に描写すればこんなに面白くなるのです。
連作短編の「職場の作法」と、同じ職場を舞台にした「バリローチェのファン・カルロス・モリーナ」、そして中編の「とにかくうちに帰ります」が収録されています。
表題作は、大雨によって別々に帰宅困難になった会社員2人の話が同時に進行し、さながら実況中継のよう。大阪湾と思われる埋立洲から本土に渡るバスに乗り遅れてしまい、工場や倉庫群の中をとにかく歩く歩く。それぞれが思いもよらない相手と道中を共にすることになってしまい、会話をすることで自分自身をかえりみることに。雨と風は強く日は落ち、濡れた足もとから冷気が這い上がります。すっかり文中の境遇に同化してしまい、読んでいる私の指先まで冷え冷えとして、ひざ掛けをしても足もとは寒く。4人の一刻も早い脱出と、とにかくうちに帰りつくことを願いつつ読み進めました。
家に帰って食べたいものを、マッチ売りの少女のように数える。玄関についてレインコートを脱ぎ、化粧を落として床に座ったら、自分はしみじみ泣くだろう。そこにいることに、傘をささなくていいことに、屋根があることに。
「職場の作法」などは、私の今の仕事に照らすと思い当たる節が多くあります。その微妙な感情は自分で言語化するよりも、津村さんに書いてもらいたい。きっと的確に表現してくれて、私が言いたかったのはそれだったんですよ!と膝を打つでしょう。(全員がそうだったわけでは無いでしょうが)私は海文堂時代にさほどストレスを感じませんでした。ちょっと厳しさの足りない、(同僚も含めて)脳天気なところのある労働環境だったせいかもしれませんね。辞めたおかげで津村さんの面白さがわかってきた、というわけです。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.10月 (18)戦記のおじさん

(18)戦記のおじさん
本屋に足繁く通ってくださる顔なじみのお客様でも、定期購読や客注を受けない限り、お名前を知ることはほとんどありません。本の好みだけでなく、時には職業や出身校や家族構成まで知っていても、連絡先やフルネームは知らないことが多いのです。元町周辺にお住まいの方やスタッフ個人と親しいお客さまが多かった海文堂でもそうでした。最近来られないなあと思っても、理由を知らないままついにお目にかかれないこともありました。
「戦記のおじさん」は海文堂のお客様でした。小柄な方で、いつも女物のつっかけを履いているのでサンダルのおじいちゃんとも呼ばれていました。いたずら小僧がそのまま歳を取ったようなその人は、海軍の少年兵だったそうなので、出会った時はすでに80歳に近かったのでしょう。
午前中にやって来て、まず文芸書の戦記文学の棚を見に行かれます。
「ええのないか。夏になったらまた出るんやろが」
とつぶやいてからスタッフに声をかけます。指の輪っかで眼鏡を作り、
「来とらんのか?」と聞くとそれは平野さんのこと。
「いつもおる女の子は?」とは私のこと(すみません、この方にかかったらいくつでも女の子です)。
レジIさんがお休みの日は「寂しいのう」と。
耳が遠くなられていて、こちらの言うことはほとんど聞き取ってもらえないのですが単語や身振り手振りだけで何となく通じました。レジIさんとだけは不思議と会話が成立していましたね。平野さんが肺炎で入院した時は「どこに入院しとる。見舞いに行かな」と、本気で心配してくれました。
元町商店街のどこかで調達してきたお菓子やミカンをよくいただきました。行きつけのお店が何軒かあり、各所でお店の人と親しくなって愛嬌を振りまいていたと思われます。
光人社の海軍ものや坂井三郎関係の新刊はほとんど買われました。他店で見つけた本も海文堂で買ってくれました。戦史に詳しく、名前だけで「誰それの部隊におった人や」と博識でしたが、「戦争ものを読んどると広島の姉に破られてしまうから隠しとくんや」とも言っていました。週に4、5回は来店し、しばらく見ないなと思っていたら「姉のところに行ってたんや」ということも。のちには行く前に知らせてくれるようになりました。
閉店の年の初めには、戦記のおじさんの姿をまったく見かけなくなりました。ずいぶん長く来られへんねと噂したころには閉店が決まりました。9月末に閉店した時も、閉店してからも、おじさんに廃業をお知らせできなかったことが心残りです。
おじさんがお姉さんのところから戻り、あるいは元気になって、また海文堂にやって来るシーンを空想してしまいます。見慣れないお店に入って大きな声で言うでしょう。
「なんや、本屋はどこへ行った。ここにおったみんなはどこや。どうなっとるんや! わしは夢を見とるんか」
夢じゃないんですよね、お名前も知らない戦記のおじさん。
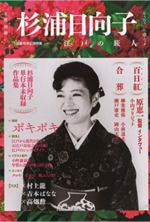 別冊文藝『杉浦日向子 江戸の旅人 没後10周年特集』河出書房新社 2015年9月発行
別冊文藝『杉浦日向子 江戸の旅人 没後10周年特集』河出書房新社 2015年9月発行
杉浦日向子没後10年の節目に、漫画のアニメ映画化と実写映画化が1本ずつ立て続けに。この機会に新たな日向子ファンがぐんと増えたことと思います。何を隠そう、私も今頃になって杉浦日向子(1958~2005)を発見した一人なのです。
京都朝日会館にあったJ堂で、訪れた記念に何か買おうと思って平積みされていた『百日紅』を手に取ったのが出会いの瞬間です。世の動きに疎くなってしまった私はカラーのアニメ化帯にも気がつかず、
「なんで今頃これ積んでんねやろ」
などと思いながらパラパラめくってみたのでした。そして即決。これってリアル書店で本と出会う!という経験なんですね。やったー。
この『百日紅 上・下』が面白いのなんの。葛飾北斎と娘のお栄が主人公の連作短編漫画で、登場人物のキャラクターも選び抜かれたセリフも「皆まで言わぬ」終わり方もすごいのです。日向子さん、絵がうまくないなんて言われるけれど、微妙な表情を書き分けてこんなに読ませるとは。
というわけですっかりはまり、次々買い求めました。筑摩さん、たくさん文庫にしてくれてありがとう。でもね、すでに書かれたものは読み尽くせばおしまいに。未刊行のものがあるなら読みたくなりますよ。なのでこの別冊文藝は、私にとって誠に時宜を得た嬉しい刊行となりました。発売当日にいそいそと買いに行きましたよ。
評論が多いのかと思いきや、新人の頃の編集者氏と写真家である兄上の寄稿、映画化関連の項目が2つあって作品論はなし。あとは全部単行本未収録作品で、エッセイ、イラスト紀行、漫画、講演・インタビュー、傑作漫画・絵詞、対談と盛りだくさん。対談のお相手は森毅、吉本ばなな、高畑勲、天野祐吉、村上龍の各氏です。
杉浦日向子全集は持っていないので、呑々まんがが23話も読めたのがうれしい。あとはやはり5歳違いの兄上による少女の頃の日向子さん像。今でいうオタクなお兄さんの影響をもろに受けて育ったよう。子どもの頃から車に怪獣、長じて洋楽、落語、映画に歌舞伎に絵画と、超多趣味で仲の良い兄妹だったことが根っこにあったのですね。
江戸文化は東北を親とし、上方を兄や姉として成長していったのです。自分一人で大きくなって親のことを忘れている反抗期の子どものように、とかく江戸は地方を軽視しがちです。実は江戸の背後には奥深い北の文化があったということを見直すべきではないでしょうか。
これは’94年の談話ですが、この江戸風俗研究家は当時から東北のことをこのように捉えていたのですね。
別冊文藝を読み終えてももっと読みたいという気持ちは募るばかり。一番読みたいのは新作なんですよね。せっかく2作品が映画化されたのだからせめて映画でもと思うのですが、観る勇気はまだありません。アニメ「百日紅」のお栄のこの眉はちがうやろ、とかね、原作のファンは絶対言っちゃうんですよね。観るならちょっと熱が覚めてから、と思っています。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.9月 (17)棚卸し

(17)棚卸し
業種によって違うのでしょうが、本屋の棚卸しは通常1年に1回決算月に合わせて行われます。海文堂の棚卸しは9月末ごろ。店にあるすべての商品の価格を棚卸し用紙に手書きします。いつも7月には実施日の発表があるのに、2013年はなかなか日が決まらないなあと思っていたら、9月末でまさかの閉店!ということで棚卸しは行われませんでした。
棚卸しはとにかく人数に頼らざるを得ない作業で、以前いた本屋では取次さんや懇意な版元さんから大勢の助っ人が応援に来てくださっていました。
海文堂も同じと思っていたら違いました。毎年9月になると、店頭に棚卸しスタッフ募集のポスターが貼り出されます。1日だけのアルバイトを求人するためです。この求人で約20名を集め、海文堂全スタッフと取次からの2~3名で作業するのです。
棚卸しは読み手と書き手の2人一組で行われます。ペアを決めるのは店長の仕事です。お相手によって進捗に影響が出るので、どんな人と組むかは大変重要な要素でした。
作家の髙田郁さんが「本屋の棚卸しを一度やってみたかった」ということで海文堂にアルバイトに来てくださった話は、『ほんまにvol.14』で読んでくださいね。ここでは書かれていなかったことを。髙田さんのペアが誰になるのかと、みんなドキドキしていました。私やったら緊張しすぎて間違いまくるわとか、やっぱり店長ちゃいますかとか。結局くとうてん社長のお嬢さんでアルバイトのAちゃんに決まり、ぴったりピースがはまったような店長の人選に感心したものです。髙田さんは、岩波文庫赤のあるタイトルに心を奪われたようで、
「これ、どういうこと? こんなんあり?」
と妄想をふくらませておられました。それを忘れずに、後日買ってくださいましたっけ。
10分休憩には持ち寄ったチョコや飴でリラックスします。声を出し続けるので飴とお茶は必携です。休みながら、密かに観察していたことがありました。通常の仕事着(男性はネクタイ、女性は制服)と違って、棚卸しの日は私服です。普段見られない私服姿の同僚たちは印象が違って見えるのです。特に男性諸氏。(誰がどうとは言いませんが)人柄とセンスが相まって、なかなか見ものでしたよ。
私の棚卸しの日のささやかな楽しみは、年に一度だけレジのIさん、実用Kさんと出掛けるお昼ご飯でした。行き先は海文堂から北へ2分の麺類屋さん。週刊誌を買うついでにレジIさんとお話するのを楽しみに来店されていたZさんのお店です。みんなで行くととても喜んでくださいました。
たまに行くお店に知った顔があって、ちょっと挨拶をするだけでも気持ちが和らぐことありますよね。元町からそんなお店が一つ減ってしまったけれど、顧客のみなさんが新たに知った顔のあるお店を見つけてくださっているといいのですが。
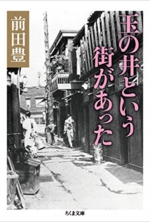 前田豊・著『玉の井という街があった』ちくま文庫 2015年7月発行
前田豊・著『玉の井という街があった』ちくま文庫 2015年7月発行
ちくま文庫でこのタイトルなら、きっと海文堂1階人文書平台ちょっと奥寄り(NHKテキスト向かいあたり)に平積みされていたはずですね。平野氏は人文担当なので、ちょっとだけ文庫担当に遠慮しつつもジンブンシールをスリップに貼りつけて、うきうき場所を空けたことでしょう。お隣は井上理津子さんの『最後の色街 飛田』でちくま文庫並びにして。『玉の井~』の解説も井上さんだしね。
本書の元本は1986年に立風書房から出ていました。30年ぶりの文庫化は『飛田』がよく売れたからかも。玉の井というのは、吉原に代表される公娼街に対して私娼街のあった場所で、現在の墨田区東向島あたり。関東大震災で被災した娼婦たちが流れついて街が形成され、東京大空襲で壊滅するまでの、わずか20数年間だけ隆盛して幻のように消えた街。細い道が迷路のように入り組んだ一角でした (なので「抜けられます」という看板があちこちに) 。
著者の前田豊さんは1912年東京生まれ。松竹ニューフェイスでデビューした俳優さんで、その後小説家となり1990年に亡くなっています。
著者は研究者ではなくて、「客」として玉の井に通った世代。けれど男性目線の過度な思い入れや郷愁は少なく、証言や写真などをまじえながら、女性が読んでもいらつかない筆致で良くも悪くもありのままの玉の井を教えてくれます。
私がいつになく、ノンフィクション、しかも「もっと奥へ~」っぽい本を選んだのには理由があります。この本の舞台、戦前の玉の井の地で義父が蕎麦屋を経営していたのです。かねてより、改正道路に面した店舗から銘酒屋(私娼を抱えている店。居酒屋ではない)へ出前に行った話、秋田や山形出身のお姐さんと話したこと、東京大空襲で店を失ったことなど聞いていました。
自分がはるかに遠くともその地にゆかりがあると思っているせいか、大変面白く読めました。永井荷風や高見順が小説に残した玉の井を掲載の地図で確認し、娼家の商いの仕方などは興味津々。馬鹿げた国策のことも初めて知りました。同じ舞台のコミック、滝田ゆう『寺島町奇譚』を読み直したら、読み飛ばしていた細部の絵の意味などがとてもよく分かり、参考書としてもお薦めです。
いつものように気になる一節を引用したいのですが…。じつは義母91歳にこの本、差し上げてしまい手もとにありません。彼女は義父の店を少女の頃から手伝っていたのです。
「懐かしいねー。ちょこっと読んだけど面白いよ」と言ってくれました!
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.8月 (16)ローテーション

(16)ローテーション
海文堂のスタッフローテーションは2週間単位で行われていました。これは週1回の平日休みと、隔週の日曜あるいは土日の休みをジャンル担当者に振り分けるためです。この休日システムを実行するために生まれたのが2チーム制です。ジャンル担当者9人をAチームとBチームに分けて、交互に日曜あるいは土日に休み、週4~5勤と6勤を繰り返すのです。祝日も交互に休みました(この説明で理解してくれる人はまずいません)。
Aチームは店長、学参Sさん、アカヘル氏に私。Bチームは児童書Tさん、文庫Hさん、平野さん、ゴットさんに実用Kさん。このメンバーはほぼ固定なので、日祝に、店長に会いに来たお客さんは児童書Тさんに会えず、平野さんに会いたい人は同時にアカヘル氏には会えないということになってしまうのでした。日曜に行ったらいっつもおんなじ顔ぶれやった、という方は、いつも同じチームの日に当たってしまっていたということなのです。
販売職なのだから日曜祝日に働くのは当たり前という環境にいたので、海文堂では隔週土日に休めると聞いて驚きました。当初はやった!という気持ちとええんかいなという気持ちが半々でしたね。
もっとも本屋は立地に大きく左右されるもの。海文堂の場合は商店街に位置していながらも土日繁盛型ではなくて、平日と週末の差があまりないタイプの店でした。つまり家族連れや若者が休みの日に多く訪れる店、ではなかったのです。海文堂の営業時間は10:30から19:00と短いのですが、それは元町商店街の夜の「引き」が早く、夜7時にはすでに人通りも少なく閑散としていたからでした。
私の属するAチームの日曜は、なぜかたびたびトラブルに見舞われました。Bチームはいつも平穏なようだったので、Aチームの混乱はやはりメンバーの人徳かと。多かったのはバイトさんの突発休。メンバーに余裕はなく、一人欠けても大打撃なのです。他のバイトさんの都合がつかない時は、この人の登場です。
ご近所在住徒歩圏内の平野さんはバイト管理をしていたこともあり、人が足りひん!という時には嫌な顔もせずに応援に来てくれました。せっかくの休みにやって来て、人の足りない時間帯だけレジや中央カウンターに入ってさっさと帰る、ということがしばしばありましたね。
私が寝過ごして店長からの電話で目を覚ましたのも、Aチームの日曜でした。平野さんには来てもらわずに済みましたが、みんなに迷惑をかけてしまい、今思い出しても焦ります。
隔週日曜、隔祝日に心置きなく休めること、営業時間が短く残業の人でも午後8時までには閉店事務を終えて店を出られること。この労働環境のおかげで海文堂スタッフは、疲れやストレスを比較的ためずに働けたのではないでしょうか。赤穂や姫路という遠方から通うスタッフが長続きした理由でもあると思うのです。店長はいつも7時閉店のことを話す時、「人間らしい生活ができる営業時間でしょ」とちょっと得意げに言っていましたっけ。
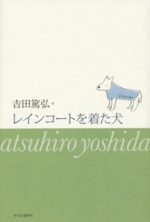 吉田篤弘・著『レインコートを着た犬』中央公論新社 2015年4月発行
吉田篤弘・著『レインコートを着た犬』中央公論新社 2015年4月発行
16回にして同じ著者が3回目。この守備範囲の狭さよ。好きな本だけ読む気ままな読書を満喫しております。もっとも本屋時代から好きな本しか読まなかったですけどね。
さて、月舟町3部作ついに完結。『つむじ風食堂の夜』2002年、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』2006年、番外編『つむじ風食堂と僕』2013年、そして本書『レインコートを着た犬』2015年。
2004年に刊行された『テーブルの上のファーブル』にはすでに映画やレコードの形でこの本の構想が登場していました。まさに待望の新刊です。
3部作とは言っても月舟町周辺が舞台というだけで、主人公はそれぞれ違います。なので、たとえば雨降りの先生とデ・ニーロの親方が、町に起こった事件を毎回解決、などというものではありませんのでご安心を。なんと今回の語り手は、月舟シネマの飼い犬であるジャンゴ。人の言葉を解する彼は映画と古本屋で学習し、思索を重ねます。
ジャンゴの住まいである月舟シネマは営業不振で主人は悩んでいる様子。シネマだけではなくて、親方の古本屋もサキさんの屋台ももうけは出ていないようだし、つむじ風食堂とシネマの売店である初美さんのパン屋は新しく出来たレストランのせいで客足が落ちてしまったようです。
ジャンゴは夢想します。映画館に犬も入店できるパン屋と喫茶店を併設し、古本屋も移転してくれば皆の顔がひとつの場所に揃う。なんと安心なことだろう。なんていい考えだろう。
登場人物それぞれが自分の足許を見つめて考え抜き、それぞれの決意表明の場にジャンゴは立ち合います。古本屋を営む親方の決意は、
「やめないこと」
目を細めてそう云った。
「本当に好きなら、やめないこと。逆に云うと、やめちまうってことは、なんだかんだ云っても、気持ちがさめたってことだ」
そしてこうも言います。
「客が来ねぇなんてぼやいてる暇があったら、宿題をちゃんとやれって話だな」
映画館も食堂もパン屋も、「あぶない」からこそ知恵を絞り、あとがないつもりで自分に宿題を課して生き残りをはかろうとします。失われてゆくものへの哀感、などというものよりも、今ここにあるものを継承してゆくことこそ、最大の勇気なのだと私には伝わりました。これはもっとも難しいこと、であろうと思います。
月舟シネマは最後の上映に向けて動き出しました。
3部作の登場人物とは別れがたい思いですが完結、なんですね。またどこかでちらりとおなじみのメンバーと再会できますように。ちなみに私は今回登場しなかったリツ君のファンです。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.7月 (15)2階

(15)2階
海文堂の建物は2階建てです。東入口から入ってすぐのところに階段があったのですが、案外上がったことのない人、多いのではないでしょうか。私も入社前に訪れた時はなんだか恐ろしくて上がれませんでした。たかが本屋といえども見えない空間に行くのってちょっと勇気が必要ですよね。
でもいったん上がったことのある人は、その後結構コアな顧客になってくださったようなのです。その中にはほとんど2階にしか立ち寄らない人たちがいて、そういう方々のことを“2階の住人”というのだそうです(これはどこかで青山絵師が書いておられたと)。船や海や港で働いておられる方、船や海や港で働きたいと思っている方、船や海や港がただただ好きな方。2階の常連さんで1階では知られていないという方が幾人もいらしたようでした。
2階売り場には、海文堂の看板とも言える海事書と港町グッズをはじめ、理工、芸術、資格、学参、語学のコーナーがありました。そして店内ショップとして、古本を扱う「古書波止場」も。
2階のレギュラースタッフは2名。休日や休憩時の交代要員として1階から1名。ほとんどの時間がこの3人だけで賄われていました。海事書というジャンルは専門性が高い上に、担当のゴットさんは直仕入に熱心です。聞いたこともない発売元の本やグッズを取り揃えていたので、普通の本屋の脳みそしかないスタッフ(私)がまれに1人でレジに入ることになった時はドキドキでした。
専門用語だったり略称だったり、尋ねられた言葉さえ理解できないことも(分かっていないからここに再現できない!)。そういう時は食堂(食事室)に内線をかけます。海事ゴットさんと学参Sさんは、私みたいにあたふたしたスタッフのために必ず食堂で休憩してくれるのです。うるさい呼び出しも厭わずにすぐ駆けつけてくれて、いとも簡単に解決してくれるのでした。
お客さまのあまりいない時はグッズを見るのが楽しみでした。アンクルトリスのバッジや船型定規や黒船ペリーのメモ帳、日本丸チョロQ、氷川丸のエコバッグ、国際信号旗の絵ハガキ、錨の刺繍のキャップ、ペーパークラフトのさんふらわあ号、文庫Hさん制作のオリジナルストラップ、各種帆船カレンダー、実際に客船で使っていた食器などもありました。
初めて来られた女性客の反応は、
「うわっ、どうしょ。はまりそうや」
「見てこれ。めっちゃええやん」
「ちょっとお、これ欲っしい」
といったもので、おおむね私の反応と同じでした。
海事書や雑貨に限らずですが、2階のオリジナリティを1階スタッフであった私が伝えるのはとても無理。“2階の住人”のみなさんなら、きっといろんな面白いポイントをご存じでしょう。貴重とも言える、2階スタッフが持っていた「つぶしの効かない知識」が、今後も活かされることがなさそうで残念です。売り場がなくなったということは、そのための知識も同時に失われたということなんですね。
 平野義昌・著『海の本屋のはなし―海文堂書店の記憶と記録』
平野義昌・著『海の本屋のはなし―海文堂書店の記憶と記録』
苦楽堂 2015年7月発行
内部の人間なので、この本のことを書くのはどうかなあと逡巡していたのですが、やっぱり書きたくなりました。
閉店翌年の100年まつりの時、海文堂の本を平野さんが書くらしいと聞いてもいったいどんな本になるのか思い描くことができませんでした。在りし日の海文堂を残しておきたいという気持ちを書籍にするとどういう構成になるのか。はたして1冊分の分量になるのか。
1年後に完成したこの本を見て感心しましたよ。そうか、こんなやり方があったのですね。一書店員が自分の目だけを頼りに書いたエッセイではないのです。取材を重ね資料にあたり、それを客観的に活かしながらも自説を忘れず、決して内輪話やお仲間話ではないレポートに仕上がりました。
著者は取材等で、自分ひとりの力で書いた本ではないと繰り返し言っています。海文堂が大勢の応援者によって成り立っていたのと同様、「海の本屋のはなし」もまた多くの方の力を借りることで完成した本といえるでしょう。本に記録することでお世話になった方々の名を残し、ささやかながらお礼に代えることができたのではないでしょうか。
実に100ページ近くを著者が入社する以前の海文堂史に充てています。以前から地元の書店史をまとめていたのが大いに役立ったと思われます。おかげで自分が働いてきた会社の(公式ではない)歴史をきちんと知ることができました。
そして同僚やОBへのインタビュー。彼ら彼女らの口調そのままのリアルな発言を読むことで、海文堂を知っている人にはより親しく、訪れたことのない人には、実際に在った書店として体温を感じてもらえるのではないでしょうか。
「閉店まで」の項は、日ごろから平野さんが書くということを習慣にしていたからこそ生まれたもの。この臨場感は日記ならではですね。ブログなので茶化している部分もあるけれど、顧客の方々への感謝と無念と美化なんてする余裕もない姿がありのままに描かれています。
多くのみなさんが閉店を惜しんでくださった理由について、著者は関係者に聞いて回ります。ラスト近くでの店長の意見、
100年になろうとする歴史の中で海文堂という本屋で働いてきた数知れない人たちが、ひたすら、そして淡々と、正直な商いをしてきたことに尽きるのではないでしょうか。
というのがきっと正しい考察なのでしょう。それは私がこの本を読み、海文堂の来し方を学んで初めて分かったことのひとつでした。
なお、最初に申し上げておきます。この本はけっして“エエ本屋の美しい閉店物語”ではありません。ウジウジグズグズした嘆き節です。
これが著者の一貫したスタンスです。平野さんは私(たち)の代わりに言いたかったことを言い、疑問を呈し、残すべきことを残してくれました。色々な感想があるでしょうが少なくとも私は、この本は私たちの本だ!と感じています。
元本屋と編集者という本を扱う2人のプロが、価値ある書籍を作ろうとして呻吟し、そして生まれた賜物をここに受け取りました。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.6月 (14)本屋の眼

(14)本屋の眼
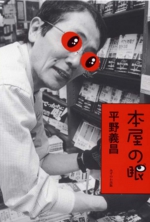 『本屋の眼』は、店内で起こったちょっとした事件や世の中の出来事に対する感想を、平野さんが面白おかしく書き綴ったサービス精神旺盛なエッセイ集です。海文堂のフリーペーパー「海会(かいえ)」に連載していた同名のコラムと、雑誌に掲載された書評などをまとめたA5判の書籍で、2006年12月に発行されました。
『本屋の眼』は、店内で起こったちょっとした事件や世の中の出来事に対する感想を、平野さんが面白おかしく書き綴ったサービス精神旺盛なエッセイ集です。海文堂のフリーペーパー「海会(かいえ)」に連載していた同名のコラムと、雑誌に掲載された書評などをまとめたA5判の書籍で、2006年12月に発行されました。
そのコラムが本になると聞いた時は驚きましたよ。みんなで、うそ!すごい!と言い合いましたよ。まださほど歴史もないA4判1枚両面のフリーペーパーから本が生まれるなんて。しかも取次経由で全国流通に乗るちゃんとした出版社だし。当人も本になることなど考えずに書いていたと思うので、さぞびっくりし、うれしかったことと想像します。
出版が決まったある日、みずのわ出版さんが本に使う写真を撮りに来られました。朝礼時に挨拶されて、平野さんを密着撮影しますとのこと。アイドルタレントの撮影さながら、立派なカメラでバシャバシャ写しまくっておられました。画家の林哲夫さんが写真を素材として使い装丁なさると聞いて期待は高まるばかり。
かくして完成した本は。うふふ、あの目ん玉。ちょっと予想とは違っていましたね。たぶん、平野さんの予想とも(聞いたわけではありませんが)。端正でかっちょいい本をたくさん作ってこられた林さん。その路線かと思いきや、意表を突く表紙。タイトルが『本屋の眼』なんだしおちゃらけた部分も多いエッセイなのだから、思えば内容にぴったりとも言えますよね。名は体を表す、の見本のような本になりました。
そののち出版されたいかにも林哲夫さんらしい装丁の別の本を、平野さんが羨望の混ざった表情で新刊紹介したことがありましたね。
当時店長が書いたキャッチフレーズは、
二日酔いにも負けず汗を流してけなげに働く本屋の店員の“現場ばなし”
というものでした。これは言い得て妙です。
さて、本ができたら出版記念パーティーとサイン会です。クリスマスに海文堂2階のギャラリーで行われました。たしかトークやギター演奏があったと思いますが、ほとんど覚えていないのです。平野夫人もトークに出られていたような。
おそらく海文堂の最後まで応援してくださった方々が、その時も大勢来てくださりパーティーを盛り上げてくれたのだと思うのですが、なにぶん当時の私は、店長や平野さんのお仲間方をほとんど存じ上げていませんでした。関係者としてお役に立ちたいものの、どなたがどなたなのかもよくわからず、身内同然のくとうてん(当時はシースペース)の方にまで本日はありがとうございますとビールを勧める始末。
「お目にかかったことがあると思うんですが、どちらの方でしたか?」
私服姿のレジ担当Iさんに、いつもレジで話していかれる常連さんがたずねる一幕があったことだけは記憶しています。同僚が本を出版することで、身近にいた私たちまでちょっとだけ外に開かれた、そんな感じがしたものでした。
本になった『本屋の眼』には、特製のしおりが付いていました。自ら選んだ紙にたしか白川静本から探した書体を使ったオリジナルはんこを押したもので、文字はそのまま「本屋の眼」。家族総出でスピンを付けたそうで、思いのこもった手作りしおりです。もともと腰の低い平野さんですが、本書をお買い上げの方にはさらに低く、サインなど所望されればもっと低くして恐縮しつつも、買って読んでいただける喜びを体現していました。
書籍化されたのは海会に連載を始めて2年余りの部分のみ。その後、2013年9月の閉店まで連載は続きました。時には硬派な一面も覗かせつつ、海会向けの”平野文体“といったものが次第に形成されて行きます。惜しむべきはそれらがまとめられなかったこと。店に来られてレジで海会を手渡されたお客さまだけが読めた、今となっては幻のコラムとなりました。
さて、平野氏は2冊目の著作『海の本屋のはなし 海文堂の記憶と記録』を7月上旬に上梓します。出版を決断したのは神戸の一人出版社苦楽堂さん。BOOKSルーエの花本さんが作ってくださったフリーペーパー「海文堂の伝言」にエッセイを寄稿された方です。その短文「それはどの街でも起きる」を涙なしに読めなかった私は、それを書いた方として苦楽堂さんのことを記憶しています。つまり、本屋を、海文堂をよくよく知っている人が版元になってくれたということです。これは著者のみならず本にとっても幸せなことだと思うのです。
今回の本はおちゃらけではなくて本気のノンフィクションです。ぜひこの”落差”を楽しんでいただきたいですね。歴史好きの平野さんが様々なつてを頼って多くの関係者を取材し、海文堂の古い話や小さなネタを聞き出しました。前を見るために後ろを見るという作業が、きっと彼には必要だったのでしょう。その感覚は私たち海文堂出身者に共通のものではないかと思います。私自身、この本の出版をとても楽しみにしているのです。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.5月 (13)自動ドア

(13)自動ドア
海文堂の閉店は一昨年の9月30日だったのですが、翌日10月1日も私たちは出勤していました。店内すべての本を返品なり処分なりして空っぽにするためです。
その朝の店内は営業最終日の混雑がうそのように静かで、フェア台や棚にはたくさんのすき間が空いていました。店長が最後まで手を振っていたシャッターはもちろん下りたままです。そのシャッターの内側にある自動ドアが開いていたので閉めようと思い手をかけました。この自動ドアは名こそ自動ですが、店の晩年にはすでにまともに動かなくなっていたのです。いつも手動で閉めなくてはならなかったのに、なぜか、まったくなぜか分かりませんが、その日はびゅーんと自分から閉まったのです。かくて私の右手はゴンとはさまれ、見る間に手の甲は真っ青になりました。閉店の恨みを、たまたまそこにいた私に晴らしたかのように。今回はその自動ドアのことを。
とにかくよく故障しました。大半は閉まらなくなる系で、ウィーンという音はするのにあと10センチのところで止まってしまったり、全開のまま閉まらなくなってしまったり。スイッチをオンオフすると思い直したように動くこともありました。
雨の日に止まり、寒い日にも止まりました。特に暑さには弱いようで、急に汗がふき出してきたと思って振り返ったら開きっぱなし、ということも。一番必要な真夏には毎日のように止まりました。レジのスタッフたちは汗を拭きながらよく耐えましたよ。
開閉の速度が遅いのでドアにぶつかるお客様も多くおられ、激しくぶつかるとドアが外れて止まるということも何度かありました。開閉の音がうるさすぎるという苦情で大叱責を受けたこともあります。
そうすると児童書Tさんが修理を依頼して、いつものおっちゃん登場です。大きな脚立を肩にやって来て、自動ドアの天井の部分を開けて頭をもぐり込ませます。まわりのお客さんにお構いなしに作業を始めるので、いつも平野さんが張り付いて警護に当たっていました。問題は、いったん直りはしてもすぐに再発することでした。もうとっくに耐用年数を超えていて、根本的な修繕が必要だったのでしょう。
路面店の本屋さんには、海文堂のようにエアコンが必要な時期はドアを閉めているお店と、年中開放しているお店がありますね。う~ん、どちらがいいのでしょうか。従業員には過酷でも、いつもドアは開いていますっていう方がやはり入りやすいかな。その分入り口付近のエアコンを強めにして。抵抗なくお店に入れて快適な温度で、しかも万引きに狙われない本屋を実現するのって難しいですね。
閉店後、右手の痛みは治まったものの内出血は痣となって、消えるまでに何か月もかかりました。見るたびに海文堂での日々を思い出さざるを得ず、少しの心の痛みとなって私の“再出発”の妨げになったかもしれませんね。ところでこの自動ドア、今現在は「自動」として役目を果たしているのでしょうか。それともとっくにお払い箱になっちゃったかな。
 吉田篤弘・著『ソラシド』
吉田篤弘・著『ソラシド』
新潮社 2015年1月発行
「Don’t Disturb, Please」起こさないでください。そっと差し出されたプレートは、これ以上近づくことを拒むものではあるけれど、静かに思いを馳せることぐらいは許されるでしょうか。
語り手の「おれ」は、妹の生まれた年に活動していたギターとダブル・ベースの女性デュオ“ソラシド“について調べていくことに。その年1986年はバブル真っ盛りであったけれど、「おれ」が浴びるように聴いていたのはビルの裏側のもの悲しい空気のような音楽。それはソラシドの目指していた、冬の空気の中にある冬の音楽、と重なり合うものでした。
資料を探し映画を見、近しい人に会い唯一の音源を聴く。これ以上は近寄れないラインがあってもどかしいものの、「おれ」の頭の中には合い間合い間に冬の音楽を奏でるソラシドのストーリーが立ちあがって行きます。
本当に手に入れたいのは街だったのかもしれない。街のさまざまな表情、時間、人、雑音、匂い、光、温度、静けさ一そういったものが染み込んだものを、自分は日記をつけるように手もとに引き寄せておきたかった。
これは語り手がなぜレコードに執着しているのかについての自問自答で、あるいは「本」と置き換えることもできますよね。
「おれ」がソラシドについて書くきっかけになったのはある原稿依頼。冬の音楽というテーマのアンソロジーを企画しているのでエッセイを書いてほしいとのこと。見知らぬ依頼者は西荻窪で一人出版社を営んでいるという。
フィクションはノンフィクション寄りに、ノンフィクションはフィクション寄りになってしまうと、篤弘さんはどこかに書いておられたと思うのですが、本書も小説ながら、至る所に著者ご本人が顔を出しておられるように見えて嬉しくなってしまいます。
この書籍内アンソロジー『冬の音楽』が完成したら、きっと青を基調にした小ぶりのかわいらしい本になることでしょう。ぜひ『おかしな本棚』のいつの日かの本棚のページに入れてほしい。
何度でも言いたい。音楽は前へ進んでゆくものだ。たった今発見したようにまたそう思う。それは時計の刻む音とは無関係にリズムを重ね、ひたすら前に進んでゆく日々に溶け込むように存在している。
「おれ」が86年当時聴いていた洋楽。この本にいっぱい出てくる曲を、全部聴きながら読みたい。まずは「ノース・マリン・ドライヴ」から。もの悲しい冬の空気をまとった音楽ってこういうのだったんですね。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.4月 (12)新刊紹介

(12)新刊紹介
毎日入荷する新刊は、自分の担当分を見るだけで手一杯。他ジャンルの新刊まで目を向ける余裕がなかなかありません。お客様からはどんな本をたずねられるか分からないし、担当者が不在のことも多々あります。パソコンを使って何とかタイトルを特定しても、そこに何番の棚、と書かれているわけではもちろんなく、店にあるか無いかは探してみるほかないのです。パソコンの検索ソフトと棚が無関係に存在していたのが海文堂でした。
少しでも他ジャンルを知るために、かどうか知りませんが、海文堂では毎週月曜日の朝礼時に新刊紹介をしていました。気になる新刊本や目立つ動きをした既刊本などをジャンル担当者が紹介するのです。
熱のこもった新刊紹介をするのは男性3氏。人文平野さんはいわゆる話題の本には目もくれず、とにかくご自分が好きな本や神戸本を熱心に紹介していました (「週刊奥の院」のラインナップを見ればわかりますよね) 。同じ著者や同じ出版社の本をたびたび取り上げて、出たばかりなのにもう読んだんかい!と思わせる詳細な紹介をして、私たちまで読んだような気にさせてくれたものです。
芸能アカヘル氏は反対にとてもクールで、それでもやはり好きな本ばかり紹介していました。古いフランス映画の監督の本や分厚い映画評論、マイナーな版元の本などが多かったですね。紹介する本を愛でる手つきが書店員のものではなくて、まさしく古本者のそれでした。
海事ゴットさんは1階にいては目にすることもない珍しい新刊が多かったです。出版社ではないところが出している船や港に関する専門書や写真集を直で仕入れ、その本を知ったいきさつや出版の裏話など、ストーリーのある新刊紹介をしていました。
私も文芸・新書担当として紹介をしなくてはならないのですが、とにかく人前で話すことが苦手でぶっつけ本番ができません。選書するだけでも毎回四苦八苦。えらそうなことは言えません。結局自分の好きな本を紹介していたのでした。自分の言葉で紹介を、と思うとどうしてもそうなってしまうのでしょうか。
私が入社した時文芸担当だった方は、7,8冊の新刊をいつも手際よく面白く紹介していました。ほどなく退社されて私が文芸を引き継いだのですが、あの紹介はとてもまねができませんでしたね。
平野さんがみんなの紹介した本をブログに書くようになってから、私の紹介本にも箔が付いたような気がします。
週に1回とは言え、この新刊紹介は他ジャンルの本を知る良い機会となったと思うのです。新刊を担当者の口から紹介されることで、聞いた者の頭にほんのちょっとでも残っていればきっと役に立つ。本屋のスタッフに必要なのはやはりたくさんの本を知ることなのでしょう。それはただ「目にする」よりは「目と耳で知る」ほうが記憶として残りやすいですよね。海文堂の新刊紹介は、書店員が立てるべきいく本ものアンテナの1本だったのだなと、今ならわかります。そして実際、結構な頻度でそれは役に立ったのでした。
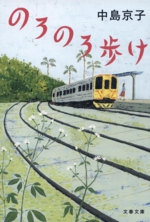 中島京子・著『のろのろ歩け』
中島京子・著『のろのろ歩け』
文春文庫 2015年3月発行
前回も書いた海文堂スタッフによる芥川賞・直木賞予想イベントですが、才能があったのは店長とレジのIさんで、私は平野さんと共に外れる筆頭でした。唯一、私が作品を読み自信を持って直木賞を当てたのが、中島京子さんの『小さいおうち』だったのです。
『イトウの恋』に圧倒されてファンに。『HUTON』も『平成大家族』もそれ以後の作品も、中島さんの小説と言えば、凝りに凝った構成と一筋縄では行かないストーリー展開が特徴かと。でもこの『のろのろ歩け』で見せてもらったちがう中島さんも、とてもよかったのです。
「ザイチェンは、シー・ユー・アゲイン。マンマン・ゾウは、そうだな、テイク・ケアかな。直訳するとのろのろ歩け、だからね。のんびり行けや、くらいの感じかな」
慢慢走。のんびり行けやー。
3つの短編が収録されています。「北京の春の白い服」は、落下傘よろしく日本から一人やって来て、中国人のベテラン編集者たちにファッション誌のありかたを説得する夏美。真冬の北京の屋外で、春の流行色白のノースリーブを着せての撮影。親しくなった人たちから教わったのは変わらない心の持ち方とめまぐるしく変化する街。どちらも本物の今の北京であること。著者の経験を活かしたお仕事小説です。
「天燈幸福」は亡くなった母の“3人のおじさん”に会うため台北に出向いた美雨の2泊3日の旅のお話。「時間の向こうの一週間」は、上海に転勤になった夫と暮らすための住まいを探しにやって来た亜矢子の、一週間の出会いと別れ。
3編ともストーリーがシンプルで混み入っていない分、いきいきした街の光景が細部まで描かれ、おいしそうな食べ物がもうもうと湯気を伴って目に浮かびます。台北、北京、上海と、主人公たちと共に都市を経験する読者。異郷の地で出会った人とは別れが付きもので、旅の時間を終わらせる時がやって来るのですが…。
たとえばここに流れている時間があるとして、それとは別の、あちらがわにあるもう一つの時間。時間の向こう側。時間の向こう岸。
なぜか主人公たちほど毅然と、「もう一つの時間」からこちら側の時間に戻ることのできない私が取り残されてしまったのでした。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.3月 (11)外商〈教科書販売編〉

(11)外商(教科書販売編)
3月は、海文堂にとってもっとも忙しくもっともテンションの高まる特別な月でした。海文堂が外商部門を持っていて、高校・大学や各種学校に教科書を納入していたからです。
ここで働き始めるまで知らなかったことですが、教科書販売ってほんとに大変なんです。外商担当だけでなく、売り場のスタッフはもちろん総務から社長まで総動員して、ほぼひと月、店の営業をしながら教科書販売のための仕事をこなします。若手のごくごく少ない海文堂なので、中高年といえども容赦なく力仕事に駆りだされるのです。特に集中する2週間は、売り場はぎりぎりの人数での営業となり、休日出勤はざら。13連勤なんてことも。教科書のメンバーを決める外商Hさんと売り場のシフトを組む平野さんが、人員のやりくりに四苦八苦しつつバトルを繰り広げていました。
準備は年明けから始まります。送られて来た段ボール箱を開けて、解答の挟み込みや点検をするのは学参SさんとバイトのK君。2月末になると広い作業場とガレージは積み上げた段ボールに占拠され、外商Hさんのデスクは迷路の終点のよう。時には箱がどどっと倒壊!
搬入の日はぎっしり詰まって重い重い段ボールをトラックに次々積み込んで、その日のメンバーみんなで学校へ。
学参Sさん曰く
「箱は腕で持ったらあかんねん。腰の骨に乗せて身体に密着させて運んだら結構持てるねんで」
なるほどー。海文堂でたくましいのはいつも女性です。
教室ではばらばらの判型の教科書を手際よくタワー状に積み上げてゆきます。このタワーの安定感が販売の質を左右するのです。最後の数年間は海事ゴットさんが、これをピシッと決める「積み師」として名を馳せていました。
販売ではとにかく声を張り上げて呼び込みします。外商Hさんから絶大な信頼を寄せられていたのが文庫Hさん。もっとも貢献度が高く、この人がいないと教科書販売は回らないというような重鎮でしたが、某大学へ行く時は学食でのデザートを楽しみにする乙女でもありました。
教科書販売は海文堂にとって一年で最大のイベントであり、スタッフそれぞれが何かしら印象に残るエピソードを持っていることと思います。某高校では卓球部諸君が手伝ってくれて助かったこと。お金が足りない児童に泣かれて困ったこと。平野さんが毎回ホットコーヒーを水筒に入れて差し入れてくれたこと。
海文堂の閉店は、店を閉じたことよりも99年間の長きに渡って続けてこられたことの方を評価すべきなのかもしれません。続いた理由のひとつは、外商部があることに依り決まった額の売上予算が立ったからだと思うのです。
海文堂の外商開始はいつだったのでしょうか。歴史の中のいつの時代かの社長が、始めるべきと判断したその先見の明に、もっと敬意を表してもいいかもしれませんね。
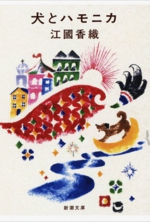 江國香織・著『犬とハモニカ』
江國香織・著『犬とハモニカ』
新潮文庫 2015年1月発行
2004年に『号泣する準備はできていた』で直木賞を受賞した江國さん。京極夏彦氏とのダブル受賞だった上に、最年少コンビ綿矢りさ・金原ひとみ両氏の芥川賞の方が大きく取り上げられたせいで扱いが小さくなってしまい、お気の毒だったのでかえって記憶に残っています。昔のことを書いたのは、海文堂スタッフ(時たま外部者も)による芥川賞・直木賞予想イベントがこの第130回から始まったからなのです。この時江國さんは一番人気で、当てる人が続出したんですよ。
そんな印象深い方なのですが、白状すると、江國香織作品を読んだことがありませんでした。もぐりちゃうかと言われそうですね。すでに人気作家だったし若い人の恋愛を描く書き手というイメージを持っていたせいかな。
さて初めて読んだこの短編集、いやー面白かった。「寝室」は、突然恋人に去られた男が、出会いから今日の別れまでを自宅で回想する話。三人称小説だけど視点は男のもの。
理恵のほめ言葉にはきりがなかった。お世辞を言う女ではなかったから、本心だったはずだ。でも、だったらなぜ、二度と会わないことに決めたなどと言えたのだろう。「たまには欠点の方も教えてもらえるとありがたいね」文彦が言うと、可笑しそうに理恵は笑った。そして、「いま教えてあげたじゃないの」と、言うのだった。
この真実。男ってなんにも分かってないねという身も蓋もない感覚を、こんな文章で書かれたら思わず膝を打ってしまいます。この男と思われる人物が、別名で「犬とハモニカ」にも出てきます。帰国した空港で恋人と電話で話すのを老婦人に聞かれる場面。ここでは他者の目から見た男。
まるわかりじゃないの、みっともない。寿美子は胸の内で断じたが、同時に、男の顔から目を離せずにいる自分に気づく。あんなに嬉しそうな顔をしてー。機内で見た仏頂面と、同じ人物だとは思えなかった。
この男が恋人に理由不明の別れを告げられて、ラスト、いつものように、かつ、まったくいつものようではなく妻の眠る寝室に入ります。最後のシーンの完成度があまりにすばらしいので、引用するのはやめておきますね。
「ピクニック」の僕も、結婚して5年の妻のことが分からない。可憐で風変わりでほんとうのことを言う妻を、魔女のようだと思う。反対に、「おそ夏のゆうぐれ」の主人公は男に夢中になりながらも、「孤独は誇りだった」し「世界に一人だけで存在していることを」知っている。誰かを理解できると思うことの不確かさを、さまざまな形で表現している短編集でした。
優れた短編に贈られる川端康成文学賞を表題作「犬とハモニカ」で受賞。若い人の恋愛、なんていう狭い読者対象では全然ないことが、これ1冊でよくわかりました。むしろ、酸いも甘いも噛み分けたおとなに読んでいただきたい。男の人たちはこれをどう読むのか、ちょっと怖いけど聞いてみたい気がします。
(三毛小熊猫・元書店員)
2015.1月 (10)お手洗い

(10)お手洗い
青木まりこ現象ってご存知ですか。「本の雑誌」が命名したこの現象、今やウィキペディアにも載っていて、要するに本屋へ行くとなぜか便意を催してしまうというもの。共感する人は多いけれど、原因については解明できていなくて都市伝説という説も。とは言え、本屋とトイレの関係にはきっと曰く言い難いものがあるのでしょう。ちなみに、書店員で私も!と表明する人は聞いたことがありませんね。
元町周辺はデパートなどの大規模小売店が少なく、大丸さんやハーバーランドまで「その」ために足を延ばすのはちょっと、という時、海文堂はずいぶん役に立ったと思うのです。なんと言っても”市民トイレ”として開放していましたからね。レジに入っていて一番多く受ける質問は、ご多分にもれず「トイレどこですか?」でした。
でもね、以前海文堂で一番人気のあったのがブックカバーだと書きましたが、反対に不評だったと思われるものの代表が、これ、お手洗いでした。特に女性と子どもとご年配の方から。何しろ最後まで和式だったのですからね。
「トイレお借りします」
と言って駆けこんでいった親子。ちびちゃんが和式トイレを前にして
「いやー、怖いー」
と泣き出す場面は何度も目にしました。こちらもごめんねーと謝るしかありません。
ご年配の方からは、
「洋式はないの。私ひざが悪くて腰かけないとだめなのよ」
申し訳ありません。ないんですよ。
女性同士の会話。
「ここのトイレきたないなあ」
「きたないんとちごて古いねやん」
そう、そうなんです。きちんと毎日、お掃除専属のスタッフが昼頃までかかって店内外をきれいにしていたのです。
土日はその人が休みなので、出勤の女性スタッフが交代でトイレ掃除をしました。当番の日、ドアを開けて問題のないことが確認できた時のほっとした気持ち。反対にぎゃっと悲鳴を上げたくなったことも数知れず。朝が大丈夫で安心していたら、午後になってお客様に汚れてるよと教えられることも。よそさまのトイレを借りる時は、絶対きれいに使おうと固く心に誓ったものです。頑張って掃除をしても、いかんせん新しい店にはかなわない。そういう意味では努力が報われないお手洗いではありました。
ひとつ気付いたのは、トイレの汚れは人心を反映しているのではないかということ。商店街の路面が舗装修理中でデコボコだった時、あるいは海文堂のスタッフ間に不穏な空気が流れていた時、さらには私がお客さまに失礼な言い方をしてしまって反省すべき時も。そんな時に、なぜか手間取るトイレ掃除の必要なことが多かったのです。この現象こそ、青木まりこ現象ならぬなんとか現象と名付けたい。こちらには共鳴してくれる人っているかしらん。
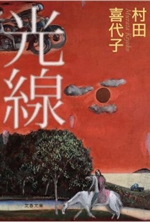 村田喜代子・著『光線』
村田喜代子・著『光線』
文春文庫 2015年1月発行
文芸書担当時に気になっていた単行本が、次々と文庫になっています。その時読めなかった本が、文庫で気安く買えるようになってありがたい。お客さまがよく、文庫になるまで待つわとおっしゃっていましたが、その気持ちわかります。読みたい本はたくさんあるので急いで手に入れる必要がないのですね。
この『光線』は、2年半で文庫化されました。単行本が出た時、朝礼の新刊紹介で読んでもいないのに取り上げた、その言葉も覚えています。震災直後にがんが発覚し、放射線治療を受けることになった主人公の妻。原発事故の放射能と関係のある放射線で治療することに違和感を覚え、云々。本の帯や注文書の説明文だけで紹介するのですからいい加減なものです。
はたして、間違ってはいないけれどそんな風に要約するべき本ではありませんでした。そもそも純文学を要約してもしょうがない。主人公はがんの当事者ではないので、医学情報や医師とのやり取り、診察の様子などを詳細に語ります。車一台分ぐらいかかる放射線治療について、特別な期待も信頼も警戒もなく淡々とありのままを記録して、読者の興味をそらしません。治療で子宮体がんの消えた妻は少し不安定で、治療に使う放射線は原発でできているのかと尋ね、松林を歩けば映像で見た福島原発付近を歩いている気になる。放射線でがんの部分が空洞になった子宮。著者自らの身体で体験した震災小説のひとつの形です。
8つの短編が収録されていて、震災と関連付けられるのは前半4つ。それ以前に書かれた4編があとに続きます。最後の「楽園」は何ともすごい。大学のゼミで発表される鍾乳洞での暗闇体験と、洞窟潜水ダイバーのルポをめぐる考察。普通の人間が経験しない恐怖を超越して見えるものは。ノンフィクションを1冊読み終えた満足感でした。
他の短編もどれも素晴らしい充実ぶり。2年半前の適当紹介は撤回して、読んだいまこそ本気でお薦めできます。これまで読まずにお客様にお薦めしたこともありました。反省!
2014. 12月 (9)新刊台帳

(9)新刊台帳
本屋には日曜祝祭日と年数回の休配日を除く毎日、何箱もの新刊書が送られてきます。その本を担当者別に分類してからそれぞれが店に出すのですが、海文堂では新刊書の処理の仕方が人によって違っていました。
新刊のタイトルや著者・出版社・冊数・日付などをノートやルーズリーフに手書きする派としない派、していたけれど途中でやめた派の3派に分かれていたのです。
人文平野さん、海事ゴットさん、文芸私の3人は書く派。店長、文庫Hさん、学参Sさんの3人は書かない派。実用Kさんと雑誌芸能アカヘルさんは途中でやめた派。(児童書Tさんだけは不明)
こうして分類してみるとなかなか興味深い法則が見つかります。まったく書かない派の3人は、すべて海文堂ネイティブの人たちなのです。伝統的に、海文堂の担当持ちたちは新刊をノートにつける習慣がなかったことが分かります。もちろんノート以外の方法で管理していたのでしょう。
途中でやめた2人はどちらも他書店経験者で、前任者(この人たちも他書店経験者)のノートを引き継いだ人たち。あんまり続ける意味を見い出せなかったのか手が回らなかったのか、やはり他の方法で管理する道を選んだようでした。
そして書く派は3人とも他書店経験者で、時期こそ違えど初めて就職した書店がみんな同じ会社だったのです。まだ頭の柔らかかった就職したての3人は、今はもう無くなってしまったその本屋で並み居る先輩にみっちり仕込まれました。入荷した新刊は新刊台帳につけて管理すべし。当時の台帳は分厚いバインダーに布の貼られた頑丈なものでした。
海文堂に拾ってもらって再会した3人は、その教えを終生変えることはありませんでした。つまり刷り込まれたということだったのですね。
では何のために新刊をノートにつけていたのでしょうか。
「ゴットさんもいつもせっせとつけてはりますけど、あれは何の効能があるんですかいな」
ある日、うずたかく積み上げた新刊を記帳していた私に、社長が尋ねました。確かに時間の無駄に見えたかもしれませんね。
私のノートに関していえば、出版社別日付順なので返品のチェックをする際に絶対必要。入荷数と週ごとの売れた冊数もつけていたので売れ行き調査やベストセラーの提出に欠かせない。月ごとの新刊予定を貼っていたので配本漏れがあると分かる。出版社別単品管理なので営業さんが来られた時に話がしやすい。とにかく記憶力のなさをカバーできる。などなどおおいに依存していて、私が移動する時はいつもバインダーごと移動していました。ただ、掛けた時間分売上を伸ばせたかというとあまり自信がないのが悲しいところです。
こんなことは今やパソコンがするべきことなのでしょう。古き良き旧式の書店の面影を背負ったままだった平野さんやゴットさんや私は、それぞれのやり方で新刊台帳をつけ続けました。うちのやり方とは違うからやめろとも言わずに、海文堂は寛大にも好きにさせてくれたのでした。中途採用者にとって、「以前」を否定することはとてもしんどいこと。そういう意味で、海文堂は海のようにゆるやかに、たいていのことを受け入れてくれたのでした。
あれ、閉店後1年あまり経過して、ちょっと美化が始まったかな?
 堀江敏幸・著『なずな』
堀江敏幸・著『なずな』
集英社文庫 2014年11月発行
書店員から見た作家さんには色々なタイプがあります。気安く君付けちゃん付けで呼んでしまう人や、現役ながら文学史上にすでに輝いていて仰ぎ見る大先生。とにかく出せば売れるありがたい作家さんに、こんなにいいのになんで売れないのと地団太踏ませる人たちも。
堀江さんはというと、「この人読んでるなんてかっこいいかも」系かな。いつもはっとするような美しい装丁で現れて、その印象そのままの深遠で繊細な言葉づかいの短編やエッセイや本の紹介。取り上げたいのはやまやまだけれど、読んではいても難しくて私には紹介不能。つまり私が堀江さんを紹介するなんて100年はやいわ!という方なのです。
「なずな」の単行本が出た時は驚きました。440ページという厚さで、しかも保育小説?今までとちゃうやん。こちらなら私が取り上げても許されるかも。
生後2か月の姪っ子を急遽預かることになった地方新聞の独身記者。彼が職場に迷惑をかけながらも、姪のなずなの面倒を見ることを生活の中心に選んだ、そのふた月足らずの記録です。
数時間おきのミルクに「爆裂」おむつにお風呂に散歩。まず手を洗うところから始まり、実用書としても役立つのではというくらい具体的で詳しい育児の様子が記されます。その背後に、なずなの周辺の人たちの機微があり、さらにその背景に記者という仕事柄生じる半径数キロ内の取材対象や町の変化や逸話が控えています。
略、なずなが大きくなって言葉を交わせるようになったら、おそらく何の記憶も残っていないだろう叔父さんとの暮らしの様子や、その暮らしを支えていた小さな町の話をしてやりたいと望んでいるだけかもしれない。そして、一緒にいた時期が過去のものになっても、彼女の記憶にはないその町が町として生きつづけていてほしいと望んでいるだけかもしれない。
なずなというセリフのないヒロインはむくむく大きくなるこの時期を、他ならぬこの町で過ごしたのです。乳児がいることで周りの大人たちに及ぼす影響がいかに大きいか。それを当人だけが知らないという不思議。
壊れやすく大事な預かりものである赤ちゃんと、今だけの代替父である主人公の距離がもたらす過剰でなさにも惹かれます。主人公の微妙な心の動きをあいまいな部分も含めて的確に書く、やはりかっこいい堀江文学でした。
(三毛小熊猫・元書店員)
2014.11月 (8)ブックカバー

(8)ブックカバー
どこの本屋さんにもブックカバー折りが得意な「折り師」や「名人」と言われる人がいるのではないでしょうか。手の切れるようなカバー紙をばっさばっさといわせて数十枚を一気に折り上げる人。忙しいお店だと、常に誰かが折っていないと間に合わなくなるほどカバーはよく減るものなのです。ここ数年こそ書店員が「カバーお掛けしましょうか」と尋ねるようになりましたが、以前はカバーを掛けられるものはカバーを掛け、掛けられないもの(函入りとか)は包装するのが当たり前だったように思います。(これは相当古い話ですね)
海文堂のブックカバー紙は2種類。文庫新書用は紺地に4艘の白い帆船の絵で、単行本用は白地に12艘の黒い帆船の絵です。これがなかなかいいデザインだったのです。もし、海文堂のすべての中で何が一番好きでしたかとお客様に尋ねたら、棚より人より雰囲気より、ブックカバーと答える人が圧倒的でしょう。それほど人気がありました。このカバー紙を、本のサイズ別に上下と左側をあらかじめ折って、買われた本にすぐに装着できるように準備しておくのです。
1階レジでは文庫新書用はアルバイトさんが、単行本用はレジ坦当のIさんが折っていました。レジのIさんは厚紙で作った型紙を上手に使って丁寧に折っていましたが、中央カウンターのYさんや2階のSさんが折るぴったりのカバーに較べると上下がやや大きめで、なるほどカバー折りひとつとっても人柄が反映されるのだなあと思って見ていました。彼女曰く、
「何ごとも遊びの部分が必要なんですよ」
とのこと。随所に見られるIさんの、いい意味でのゆるさにはいろんな場面でずいぶん助けられました。そんな彼女と話をするために来られるお客様もたくさんおられました。
海文堂の閉店が決まってカバーを望まれるお客様が急激に増えてからは、YさんやSさんにも応援をお願いして1階レジの分もたくさん折ってもらいました。でも最後の数日は、折り師はいるのにカバー紙が不足してしまい、ご希望の本すべてに掛けることができなくなってしまいました。余ると捨てるしかないものだからか、発注してくれないのです。現場で考えた苦しまぎれの手立てが、
「単行本カバーが不足しております。最終日までもちそうにありませんので、申し訳ありませんがこの中の一冊だけ掛けさせていただきます。どの本にお掛けいたしましょうか」
というものでした。
カバーを目的に遠くから来てくださった方々がいることを思えば、足りないので掛けられませんなどという事態はまったく恥ずかしく申し訳ないことで、レジに入っている者は痛恨の思いでお詫びしたものです。来てくださったみなさま。ほんっとうに、あの時は申し訳ありませんでした。海文堂は最後の最後まで、完璧や洗練とは程遠い街の本屋でしたね。
 伊藤礼・著『大東京ぐるぐる自転車』
伊藤礼・著『大東京ぐるぐる自転車』
ちくま文庫 2014年10月発行
なにげない文章で笑わせる人っていますよね。受けを狙っているとは思えないし文章家というのとも違う。本業が作家ではないのに、身辺雑記を面白く読ませてぐいぐい読者をひきつける。伊藤礼さんがそういう方なのです。
礼さんは1933年生まれ。作家伊藤整の息子で、長く大学で先生をしていましたが、今はリタイアして自転車と野菜作りに精を出しておられる様子。
本書は自転車エッセイの3作目で、タイトル通り大東京をぐるぐるするのだけれど、とにかくなかなか目的地にたどり着かない。自転車が進まないのではなくて、著者の筆が進まない、というより、進みすぎて話が目的地を失念するというべきか。
いますよね、本当は○○の話がしたいのに途中の話が長々と続き横道に逸れてはあらぬ方へ行ってしまい、目的地を思い出せばいい方で、あれ何の話してたっけ、となる人。私の周辺にはそんな人がたくさんいます。得てしてそういう人のお話は横道も含めて聞かせますよね。だからか、決められた紙数で予定の半分も書けず、次回に、さらに次回にと先送りされる礼先生の紆余紆余曲折話には、こちらも先が気になって付いて行くほかありません。
興味深かったのは自転車に乗っている最中に心臓が止まった話や数々の転倒話。学者らしいちょっと回りくどい言い回しで飄々と事実を述べるその語り口。
すなわち、他の移動手段を廃し自転車専一に暮すことにも大きな利点がある、といまわたくしは言いたいのである。一定期間俗塵から遠ざかっていたためにわたくしは世相の大きな転換点を痛烈に感じることを得たのであり、その痛烈さには他では味わうことの出来ない新鮮さもあったのである。これは分かりやすく言えば、一週間断食したあと栗饅頭を食べるときの感動と同じである。
かつて「エッセイを愉しむ 手に職ある人編」というフェアを企画して、作家以外の本職を持っている方のエッセイを選んだことがありました。今ならぜひ礼先生を選びたい。どうかお怪我なさらずに、楽しいエッセイを書き続けてくださいませ。
(三毛小熊猫・元書店員)
2014.10月 (7)店内放送

(7)店内放送
全国チェーンの大書店で立ち読みしていると、イベント開催のお知らせが天井から聞こえてくることがあります。また、新刊が出たことをアピールするコメントが、著者ご本人の声でアナウンスされることもあります。時計を見るとだいたい30分おきに放送されているような。
何時間立ち読みしてんねんと言われそうですがそれは置いといて、その放送は、録音されたものを時間通りに流しているってことですよね、どう考えても。そう、絶対それが普通だと思う。
ところが海文堂は、すべて「生」で放送していたのです。
海文堂のイベントは、2階のギャラリーで開催される古本市や著者によるトーク、中央カウンターで行われるサイン会、店頭でのワゴン販売や、貸しギャラリーなど、結構な頻度で開催されていました。そういったイベントの告知は、レジで手渡しする月刊PR誌のカイエやホームページ、店内ポスターなどで行い、当日には店内放送で案内するのです。放送を聞いてイベント会場に足を運んだり参加されたりする方は結構多くおられるようで、関係者からは放送してねコールをたびたびいただいていました。
放送原稿は店長が作成します。そのイベントに、店長が入れ込んでいればいるほど、原稿は長く、念入りな文章になります。それを、中央カウンターに入っているスタッフが、30分おきに朗読するのです。生で!
店長は自分で書いた原稿をよどみなく読み上げ、おおかたのスタッフも「舌噛みそう」などと言いつつも上手に朗読をこなしていました。でも私は、何かトラウマがあるのかもしれませんが、このアナウンスという仕事が大の苦手でした。
誰かが録音してそれを流せばいいのに、普通そうやろ、と呪いの言葉をはきながらも、いよいよ私しか放送する者がいない、となった時には覚悟を決めてマイクを持ちました。誰も聞いてませんようにと祈りながら。マイク苦手なのが私だけというのが不思議です。なんでみんなへっちゃらなんですか?
放送といえばもう一つ、閉店放送です。
「本日はご来店くださいましてありがとうございました。まもなく閉店時間でございます……」
っていうあれです。もちろんこれも生放送でした。
これなんて全く同じ内容をずっと使っていてもいいのだから、まさしく録音に適していると思うのですが、でも生なのです。録音されたものを一度聞いたことがあって、あるんやんと思ったのですが、しばらく前から使っていないようでした。
確かに人によって微妙に言い回しが違うし、声でも個性が表現できるでしょう。生で放送することによって店長の目指したのは「ライブ感」や「手作り感」だったのでしょうか。私は苦手です、と表明したことはあるけれど、なんで生なんですかと追求したことはありませんでした。今となっては生放送にした理由は謎です。
あと、海文堂にBGMはありませんでした。私が入社したころはあったのです。当時はニューエイジ系のオカリナ曲が流れていました。お客様から、眠たなるという指摘を受けて、いっそ音楽は止めようという画期的な判断がなされました。この時の店長の言葉は覚えています。
「どこの本屋も音楽を流しているけれど、思えば本を選ぶのにBGMはいらない。無音の中で選んでいただくのもいいと思います。静かならお客様の動向に我々も気を配れるし、万引きの気配にも気がつきやすくなるでしょう」
かくして海文堂は無音になりました。常連のお客様とスタッフの話し声はいつも大きくてにぎやかで、けっして静かにはなりませんでした。それでも、BGMが必ず本屋に必要なものとは言えないと、証明できたのではないかと思っています。
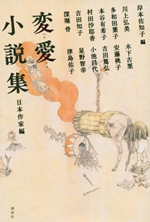 岸本佐知子・編『変愛小説集 日本作家編』
岸本佐知子・編『変愛小説集 日本作家編』
講談社 2014年9月発行
変愛小説。変な愛の小説集。看板に偽りなし。どれもとっても変でした。「ヘンアイ」なのに、作家たちは「愛」のことなんて忘れて「変」にかかりっきりで、ほとんど「変な小説」としか言えないものもあるような。
川上弘美、多和田葉子、本谷有希子、村田沙耶香、吉田知子、深堀骨、木下古栗、安藤桃子、吉田篤弘、小池昌代、星野智幸、津島佑子の各氏が、編者の岸本佐知子さんの依頼によって書き下ろした短編集です。好きな作家や読んでみたかった作家がたくさん選ばれていてうれしい。
冒頭の川上弘美「形見」は、さすがに風格がある。前から変な恋愛を多く書いてきた川上さんの変愛小説はとても安心して読めますね。人間だけでは人類を残せなくなって、哺乳類から人間を製造するようになった時代のおはなし。ふわふわとして切ないです。
一番好きなのは吉田知子「ほくろ毛」。なんだか誰かに恋されているような昂揚感。以前もあったこんな時は、あごの下のほくろに毛が生えていた。全体に明るくて登場人物もいかにもいそうな変な人たち。最も「変な愛」というお題に正しく応えている作品と思うのですが。
深堀骨「逆毛のトメ」は、からくりとワインの栓抜きを仕込まれた美少女人形トメの、出自と経歴とあたま抜き。岸本さんの「世の恋愛大好きなみなさんの眉をひそめさせてやりたい」という期待は、この作品こそ思惑通りなのでは。
惜しむらくは、岸本佐知子さん自身の作品がなかったこと。『ねにもつタイプ』他のエッセイが抜群に変で面白い岸本さんのこと。絶対すごいのを書いてくれると思うのです。小説書いて!
この本に先立って刊行された、海外作家が書いた変愛小説集。当時とても評判がよかったですよね。いよいよ10月に文庫になります。絶対買うぞ!
(三毛小熊猫・元書店員)
2014.9月 (6)大雨

(6)大雨
台風でもないのに大雨による被害が続出しています。たしかにゲリラ豪雨という言い方がぴったりする強烈な雨の降り方で、夕立や通り雨、にわか雨、驟雨といった風情のある言葉は過去のものになってしまったかとも思われる今日この頃です。
このような強い雨が深夜に降った翌日、海文堂に出勤するのはちょっとした緊張をはらむものでした。今朝は無事だろうか。どこかの棚が、あるいは床がやられていないだろうか。
海文堂は雨漏りがしたのです。本屋に雨漏りなんてまずいですよね。時には一滴ずつ、時にはじゃばじゃばと。
海文堂の建物は閉店時でほぼ築30年でした。震災を経験しているし、多少のガタは無理からぬことです。不思議だったのは、2階建ての建物なのに、なぜか1階に多く雨漏りがしたことです。しかも店の真ん中あたりに。中央カウンター東側の、ブルーバックスの棚の上が雨漏りするなんて変じゃないですか?
私の単純な理解とは根本的に違うメカニズムで雨漏りが起こっているのでしょう。それでも、なんでこんなところに!とよく腹を立てたものでした。
ただ、私よりはるかに早く出勤する方々(お掃除のNさん、児童書Tさん、文庫Hさん、平野さんなど)がいち早く気付いて、既に応急処置をしてくれていました。だからその棚の担当者である私は、ぼやくだけぼやいて平台を片付け、原因箇所にポリ袋を貼り付けるだけでよかったのですが。みなさん、その節は本当にお世話になりました…。それにしてもせっかく平積みしている大切な本が濡れて、撤収しなくてはならない悲しさったら。
いつも同じ場所から水が落ちてくるわけではなくて、児童書コーナーのストッカーの下から、地図旅行書の天井と壁の境目から、中央カウンターのまさにカウンターの上から、2階の海事書の天井付近から、といくつかの雨漏り定番地帯があり、それぞれの担当者がバケツや新聞やポリ袋を持って始末に追われていました。
営業時間中に大雨が降ってきた時に困ったのは、店外に出している週刊誌に雨の飛沫が飛ぶことでした。海文堂は元町商店街のアーケードの中にあるのですが、ちょうど路地に入る角地に立っているため、横なぐりの雨は店外の棚に降りかかって来るのです。
ある日、すごい雨音が始まって、週刊誌を守らんとシートを掛けに店を出ました。突然の雨でアーケードに飛び込んでくる人たち。急に人口密度の高くなった商店街は騒然としています。滑りやすくなった地面に足を取られ、転んで起き上がれなくなったお年寄り。通りがかりの外国人の方が助け起こして、近くの店が用意した椅子に座らせて救急車を待つ、という状況を目の当たりにしました。さすがジェントルマン!と称賛しつつ、私はそのお年寄りの傘を持ってうろうろしていただけでしたが。
台風による大雨の時は、雨漏りの心配もさることながら、今どこまで来ているのか、電車は止まっていないか、早めに店を閉めて帰ることができるのか、と小学生のようにワクワクしていました。
ある年、早く店を閉めたのはいいけれどすでにJRは止まっていて、何人かのスタッフと県庁前から地下鉄に乗り、名谷駅のタクシーのりばでずいぶん並んで何とか垂水まで帰ったことがありました。台風の話題が出てくるたびに、その日外商Hさんの担当車に乗って三木市まで送ってもらった文庫Hさんのことが、ずっと語り草になっていましたね。
そして今、安全地帯の部屋からベランダ越しに大雨を眺めつつ、あれはあれで楽しかったのかも、とため息などついてしまうのでした。
 絲山秋子『末裔』
絲山秋子『末裔』
河出文庫 2014年4月発行
富井省三58歳。妻に先立たれ、ごみ屋敷と化した家で一人暮らしの公務員。犬嫌い。この前提で果たして主人公に共感できるかしらとちらり。
読み進みながら、共感どころかこれってまるで私のことやんと思わせてしまったのが絲山さんのすごいところ。自身を顧みずにいられない至言名言にグサグサ刺されました。
省三の異常事態に手を差し伸べたのはこの世ならぬものたちでした。そもそもその異常事態さえ、この世のこととは思えない出来事。仕事から帰ってみれば部屋の鍵穴が無くなっていたなんて。
この世ならぬものたちは省三を導きながら、次々と役目を終えて退場して行きます。訳の分からぬまま従っていた彼が、やがて自らの過去や父母、祖父母、曽祖父母を辿ることで、いくつもの発見をします。
「生きるのに必死」と「死」はぞっとするほど近い、境界線が複雑に入り組んだ場所にある。ある時は生きる方に傾き、ある時は一瞬にして死に傾いてしまう。
ある日、もう息子を認識できなくなった母を見舞います。母が眠りながら「みず」とつぶやいた時、省三は母の見ている夢を想像します。しなやかなけものに、あるいは鮮やかなダリアに生まれ変わりつつある母の姿。そのシーンの文章の美しさ! 絲山さんの文章ってほんとかっこいい。
荒っぽくまとめるならば「鍵穴喪失」から始まったひと月足らずの心の旅を経て、省三は見事「突破」することができたのです。このラストの気持ちよさ。あり得なくても構わない。じっくり読んでいただきたい、あなた自身の一族の物語です。
(三毛小熊猫・元書店員)
2014.8月 (5)食堂

(5)食堂
食堂という題ならば、社員食堂のようなものを思い浮かべますよね。カウンターの中に食事を作ってくれる人がいて、従業員が割安のお値段で定食やカレーを注文するスタイルの。そんなのあったらいいですねえ。でも全員合わせても20名ほどの海文堂にそんなものはもちろんありません。ここでいう食堂はダイニングルームつまり食事室のことなのです。
海文堂の2階は売り場とギャラリーとバックヤードに分かれていて、その中に食堂と呼ばれる部屋がありました。トントンとノックして入ると黒い木のテーブルがあり、周りには6脚の椅子。部屋の隅には臨時で使う椅子が何脚か。壁には新聞の切り抜きやお客様からの手紙が、店長によってこまめに張り替えられていました。ドアが2つあってひとつは給湯室。もうひとつはなぜか男子更衣室。男性方は誰が食事をしていようとも、いったん食堂に入らないとロッカーにたどり着けないのでした。
外食派の、たばこを吸いたい店長と窓の無いのが苦手な児童書Tさん以外は、みなさんここで昼食を摂っていました。完全弁当派は3人。平野さんとアカヘルさんはお2人とも、お土産などのお菓子には手をつけず、うるわしいお弁当でちょうど満ち足りる愛妻家でありました。もう1人、レジ担当のIさんは10年間欠かさずご自分のお弁当を作り続け、持ってきたおやつ(時にはお手製の)をみんなに分けたりする、海文堂を代表する主婦、というにふさわしい人でありました。
食後の過ごし方はまあ普通。本を読む、雑誌に目を通す、ケータイやスマホのチェック、寝る、スリップを分類する、もちろんおしゃべりも。社長室が通路を隔ててすぐ前にあったので、時にはひそひそと情報交換をしたものです。
この食堂は、会議室にもバイト君たちの休憩室にも、イベントの控室や大事なお客様をお通しする部屋としても使われました。私が入社の面接を受けたのもここです。夕方やって来た男子バイト君が更衣室に入ろうとして、小難しい話の真っ最中と知らずに侵入してしまったり、図らずも作家さんとご挨拶できてしまったり、ということもありました。
なんと言っても、髙田郁さんがサイン本をせっせと作ってくださったのはこの部屋なのです。『みをつくし料理帖』シリーズが出るたびに、200冊もの新刊に署名をして澪ちゃんスタンプと落款を押すのがいかに大変か。しかも髙田さんは書きながら私たちと話をしてくださる上に、面白いこと、まで言われるのです。まったく手を休めずに! そんなことで感心されても髙田さんは嬉しくないでしょうが、すごい集中力とくだけたお人柄と結構辛辣な批評精神と私たちに対する誠実なお気遣い(これは付け足しではありませんよ)が同居するっていうのは、ただものでないことの証です。営業中はもちろん、閉店後も含めてのあまたのご厚意にはいくら感謝しても足りません。
髙田さんにとっても、一番記憶に残っている海文堂はこの食堂ではないでしょうか。窓のない狭い部屋に閉じ込められて、テーブルに山と積まれた新刊に、時にはたった1人で署名したこと。完成後には児童書Tさんの淹れた美味しいお茶にほっとしたこと。
店長!髙田さんが食堂のストーブの横に描いてくださった、火の用心の澪ちゃんイラストは、持って帰ってくれましたよね?
 長嶋 有『祝福』
長嶋 有『祝福』
河出文庫 2014年4月発行
この短編集、とってもいいんです。有さんの短編は、冒頭の「丹下」をはじめとして日常の短い時間を切り取ったものがほとんどです。すっと読み飛ばせばあっという間に読み終えてしまうような。でもそんなもったいないことはせず、最初は慎重に、手がかりになる言葉を見つけたら一旦振り返って、そうしたら気持ちいいぐらいすっきりと、長嶋世界が見えてくる。有さん独特の細部に宿る神が見えてくるのです。
「嚙みながら」は、銀行強盗に遭ってしまった頼子がその最中に思い出す高校時代の理不尽な出来事。唯一ドラマティックでスリリングで、泣かせさえする好短編。
「海の男」は男2人がなぜか釣りに出かける話で、さえない会話の本当らしさにぐっときます。これ一番好きかも。
私にとって好きな作家の小説は、なんとかその意を汲みたくて、その歩み寄った距離の分、評価が下駄を履いているかもしれないな。でもファンの履く下駄ってけっして軽くてカラコロしたものではないのですよ。
有さんの最新刊はかっこいい俳句集『春のお辞儀』。かつて一度だけお目にかかった時に(役得!)、句集のお話もしたのですが実現しましたね。ふらんす堂というのがまたしぶい。
記憶って面白い。それを忘れていたっていうことと、実はそれを忘れていなかったということが両立してしまう。
言い回しの妙とこれしかないやろ的描写に、してやったり顔の有さんを思い描きつつ、ファンはこれからも読んでいくのでありました。
(三毛小熊猫・元書店員)
2014. 7月 (4)仕分け棚

(4)仕分け棚
本屋にお勤めの皆さん。御社では検品した新刊や補充を、まずどこに仕分けされていますか。私が以前勤めていた本屋では、台車やブックトラックに分類して載せて、そのまま担当者が売り場に運んでいました。それ以外に方法がないほどバックヤードが狭かったのです。そういうものだと思っていたのですが、海文堂には、仕分け棚というものがありました。
大きなスチールの5段のラックが2台。1段ずつジャンル名が貼ってあり、10分類できるようになっているのを見た時は、すごい、と思いましたよ。
担当者が休みでも、急ぎでないものはそのまま残しておけたし、フェアや小さいセットなどの保管にも役立ちました。時たま朝礼で、仕分け棚は当日中に片付けて帰るようにという訓示があったりして、その後しばらくはしっかり守るのですが、すぐに物置に戻っていました。
ここでも「担当デスク」の時に書いた担当者の個性そのままで、お昼には完璧に空っぽになっている棚と、いつも何かしら載っている棚、返品不能品をこっそり保管している棚(私です)など、さまざまでした。
新刊を開けるのは店長の役目で、仕分け棚に次々と分類して行きます。「あれ?今日発売のはずやのになあ」とか「1冊足りひん!」という時は、店長が面白そうと思った本を自分用に取り置きした時でした。たいてい買ってくれず、チェックだけして戻していました。でも山田風太郎関係の本は、「高いなあ、○○回飲みに行ける」などと言いながらもすべてお買い上げくださいましたよ。
仕分け棚の配置は、最初に置かれた時の力関係や重要度によって決められたのでしょう。文芸・新書・文庫・児童書は一番作業しやすい高さにありましたが、芸能・雑誌の棚は一番下段にあり、最も長身のアカヘル氏がからだを折り曲げて取り出すのは見ていて気の毒でした。また一番上段は2階売り場の棚だったのですが、学参のSさんには高すぎて、ジャンプして確認したり、よじ登って奥の本を取ったりしていました。平野さんの人文・政経棚は下の2段で、ここではたびたび棚内なだれが発生していましたね。
一番気合が入ったのは文芸書の新刊がまとまって発売される日でした。さまざまな本たちが意匠を競うように仕分け棚に積まれています。好きな作家やきれいな装丁の本を見つけると、売り場に出すことよりも本を眺めていたい誘惑にかられたものでした。
本屋で働いてよかったと思うことのひとつが、こんなにもたくさんの新刊書を、お客様に先立って目にし、手に取れることでした。発売日の朝に、いの一番に、出来たてほやほやぴかぴかの本たちに触れることのできる幸せ。これって絶対本屋の仕事の醍醐味ですよね。
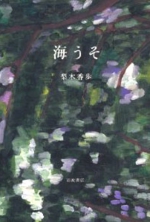 梨木香歩『海うそ』
梨木香歩『海うそ』
岩波書店 2014年4月発行
文芸書の新刊を、発売日の朝一番に手に取れる幸せを失って早や9か月。でも好きな作家の待望の新刊を、ゆっくりゆっくり味わって読んでゆく幸せは失っていませんでした。
梨木香歩さんの新刊は「海うそ」。川にいるのがカワウソで、海にいるのがウミウソと呼ばれるニホンアシカ。でもその意味だけではなくて、はるか海の彼方に見える蜃気楼のことでもあり、ぼんやり虚ろな気持ちの時にうそ越えをして、と使うこともあり…。
恩師の遺した研究を引き継ごうと、若き学者が民俗学的な調査をするために南九州のある島を訪れます。描かれるのは、かつて大規模な寺院が立ち並び、修験の地として信仰を集めた山がちなその島での、ほんの10日間ほどの出来事と、その50年後のすがた。
決定的な何かが過ぎ去ったあとの、沈黙する光景の中にいたい。そうすれば人の営みや、時間というものの本質が、少しでも感じられるような気がした。
廃仏毀釈の嵐に巻き込まれた結果の、偲ぶ物すら失われた無惨な風景があり、その50年後には信仰の跡かたさえ剥ぎ取られようとしている島。自身の心象風景と照応することで深まる主人公の寂莫。
主人公が深い森を歩きながら思索するというスタイルは、前作『冬虫夏草』でも見られましたね。私の眼前にも、かつて在った、物や人の幻が、層を成して立ち現れてくるようです。島の青年や二階家の主人ほか、人や動物や伝承などのエピソードが深く心に残り、有機的なつながりに間然するところがありません。
深い内省から生まれた選び抜かれた言葉は、地名や会話文に至るまでまったく無駄のない美しさで、むしろ言葉少なであることの豊かさを感じます。
喪失とは、私のなかに降り積もる時間が、増えていくことなのだった。
立体模型図のように、私の遅島は、時間の陰影を重ねて私のなかに新しく存在し始めていた。これは、驚くべきことだった。喪失が、実在の輪郭の片鱗を帯びて輝き始めていた。
ラストで、主人公のその後を形成した決定的な出来事が明かされます。気配だけを残して佇む遺跡に惹かれる、彼の気持ちに少し近づけた思いがしました。そして「時間」に立ち向かう彼の姿勢の穏やかな変化が救いとなり、安堵に似た感動とともに本を置くことができました。
ただ私のまぶたには、海に投げ込まれた夥しい数の仏像や仏具の姿が、今も残されたままです。
(三毛小熊猫・元書店員)
2014. 6月 (3)制服

(3)制服
衣替えのシーズンになりました。6月と10月の初日きっかりに季節の変わったことを知らせてくれるのが「制服」です。同僚の女性たちの制服が一斉に夏物になった時、非制服の方は何らかの反応を示されますか?海文堂の男性諸氏は、まったく何とも思わないかそもそも気付かない人たちでしたが、平野さんだけはいつも、ごくごく控えめに「涼しそうですね」などと発言してくれて、その表情が何とも嬉しそうなので我々としても「衣替え甲斐」がありました。
海文堂女子の閉店時の制服は黒ストライプのベストとスカートでした。閉店時、と断ったのは、厳密には制服というよりは標準服というべきものだったからです。消耗しやすいので数年に一回買い替えるのですが、ベストスーツというくくりがあるだけなので毎回その年の幹事が通販カタログを見て適当なものを選んでいました。私が知っているだけでも黒、紺、茶、柄も無地、ストライプ、チェックなど、いつも違っていました。海文堂は99年という長い歴史がありながら決まった制服は無く、「とりあえず制服」だったのです。
最後となった制服は、いつもより長く着たせいで(実は閉店の可能性があったから買い控えていたのですね。今気付きましたよ)、裏地はほころび、ペン差しポケットは名札を付けるために穴だらけ、擦れやすい部分は生地が毛羽立ち白っぽくなっていました。その部分が目立たないようにマジックで塗る!という裏ワザを使う人もいたぐらい、ぼろっちいものでした。8月に閉店が発表されて、もう着ることのない冬の制服を、即捨ててしまったスタッフがいたのも、私たちにとってあまり愛着を感じない制服だったということなのでしょう。
本の詰まった段ボール箱を抱きかかえて運んだり、ヒモかけしたり、脚立の上で棚整理したり。タイトなスカートでよくできたと思います。女子スタッフみんなが人目など気にせず、仕事に没頭していたからですよね、きっと。ベストのポケットは小さくスカートにも一か所だけ。七つ道具をいつも手元に置いておきたい私は、手製のポシェットを着用していたほど。ジーンズにエプロンがいいのにねとよく嘆いたものです。
絵描きの方が描く書店員って、たいてい男女ともエプロン姿ですよね。ジュンクさんの緑のエプロンが目に浮かびます。そのせいか、雑誌を立ち読み中のご近所のショップ店員さんが、よく間違えて声をかけられていました。
私が以前いた本屋では、それぞれが好き勝手なエプロンを着用していました。若奥様風からバーテンダー風、園芸家風と、個性を発揮してはいましたが、お客様からすればさぞ見分けがつかなかったことでしょう。
ここまで書いて、そうそう新刊『本屋の雑誌』(本の雑誌社)に制服のことが載っていたはず、と徒歩20分のK書店でパラパラ。あれ、私ったらT頭S子さんと似た様なことを書いている!
そうなんです。本屋女子が思うことは同じ。なのに上の人は分かってくれないんですよねー。海文堂の「上の人」によると、女子の制服を(お金もかかるのに)止めない理由は、女性の私服は乱れやすいから、なのだそうです…。
全国の本屋女子!がんばって闘って理想の作業衣を手に入れてください!
 柴田元幸『死んでいるかしら』
柴田元幸『死んでいるかしら』
日経文芸文庫 2014年4月発行
(略)、いつの時代でも、薄めの文庫本は普通の醤油ラーメンあたりと、厚めのやつはチャーシューメンあたりと、価格的にもだいたい対応しているように思う。ラーメンをすする気安さで、文庫本を読む、これが一番である。
いきなり引用しましたが、この本の面白さは読まなくちゃわからない。柴田訳の英米文学なら間違いないという信頼感を、全国の外文担当者はほぼ全員持っていると思いますが、ご本人のエッセイもしかり。
海外文学を紹介しつつ、次々と別の本に話は移り、思いがけないコメントが続きます。飲みすぎてアルコールが体内に蓄積した人間が自然発火する話や、人生のうちの多くの時間を自転車に乗って過ごしたために、自転車化しつつある警官の話。生まれ育った蒲田の町の話も好き。
でもこれ、単行本が出たのは17年前なのです。本書に登場する柴田先生はまだ40歳前後。ついに今年東大を退官して自由の身となった先生ですが、エッセイの軽さ、お気楽さ、もったいぶらなさ(すべて完璧に褒め言葉です)、は今も変わっていないような。「柴田君退官!フェア」やりたいな。きたむらさとしさんの絵をふんだんに使って。
(三毛小熊猫・元書店員)
2014. 5月 (2)担当デスク

(2)担当デスク
ジャンルの担当を任されている書店員の持ち物は、思いのほかたくさんあります。他の担当者と共用するものを除けば、まずは前日売れた本のスリップと、それを千切った報奨券。スリップの束を手に持った時の感触で、その日のモチベーションがぐっと上がったり逆に下がったりするほど、これは重要なアイテムなのです。
そして毎日届けられる、出版社からの夥しい枚数の営業ファクス。冊数を書いて番線印を押せばそのまま送り返せる注文書です。着いたばかりのファクスと、考え中のファクスと、返信済みのファクスと、3種類のクリアファイルが常に分厚く手元にありました。
あとはPOP作成一式、出版社の目録、頻繁に更新される注文一覧表、新聞の切り抜き、版元から送られてきたけど使い切れていないポスターや掲示物、過去に行ったフェアのリストと結果報告書。郵便やメール便で届く新刊案内に既刊注文書に常備申込書の控えも保管しなくちゃいけないし、それから直仕入管理台帳と、これは人によるけれど新刊台帳と単品管理ノートも。
こんなにたくさんあっても大丈夫なんです。なぜなら海文堂にはひとりひとり専用のデスクがあったから。
1981年、改装オープン当時の島田社長は、各ジャンルに担当者用の机を持たせることで「専門書店の集合としての総合書店」を目指していたそうです。そんな高邁な理想があるとも知らず、ほとんど物置にしていた私(汗)。
その担当デスクを他のスタッフはどんなふうに使っていたか。
実用書のKさんのデスクはいつも片付いてファイルの分類も見やすく、私も見習わなあかんなと思っていました。文庫のHさんの持ち物は整頓された上完璧に角々が揃っていて、メモの位置は寸分たがわず同じ場所にありました。平野さんのデスクは雑然としていて、なぜか小さい本の上に大きい本が積み上げられていることが多く、触ったら崩れ落ちそう。アカヘル氏の机はハンコを押す平らな面がないくらいいろんなものが載っていたのに、病欠が決まった日、すべて片づけて帰ったのがちょっとショックでした。これじゃ戻って来いひんみたいやん! でも大丈夫。ちゃんと復帰してくれましたよ。
店長は意外にも几帳面で、引き出しを開けると文房具は区画整理されてきれいに収まっていました。よく勝手に修正液を借りました。
一番使い込まれたデスクはというと、間違いなく児童書のTさんのものでした。店内で最も長い年月同じ担当者によって使われた風格漂うデスクには、他の人に解読できない備忘カードがいくつも貼り付けられていて、その場で完結しない仕事の多さを物語っていました。
子どもたちへの読み聞かせの会や、幼稚園、図書室等への少なからざる予算に合わせての選書や、私には測り知れない児童書関連のことごと。顧客からの絶大なる支持によって、ただの担当持ちとは違う仕事も抱えていたTさんの、たぶん家の机よりも長きに渡って働きを支えてきたデスク。そのデスクの気持ちを代弁すれば、きっと担当デスク名利に尽きると感謝の気持ちでいたことでしょう。
 町田純『新装版ヤンとシメの物語』
町田純『新装版ヤンとシメの物語』
未知谷 2014年1月発行
ヤンにもう一度会えるとは思っていませんでした。ネコのヤンのシリーズの最終章である本書は長い間品切れになっていたのです。やっと新装版で読めるようになりました!
主人公のヤンはお腹の白い薄茶のトラ猫で、2本足で歩き詩を書き哲学もします。だけど子供向けではないのです。このシリーズは分類しにくいせいか置いている本屋さんは多くはないようですね。
ちょっと昔の中央アジアあたりの草原を舞台に、ヤンとアトリ科の鳥であるシメとの出会い、クマのおじいさんや行商のミヤマガラスとの交流が描かれます。でも中心になるのはひとりでいる時のヤンの思索。めぐる季節の中での、孤独であることの豊穣と寂寥です。
ボクらが描こうとしていたものはこれから思い出となるものの痕跡なのかもしれない。
そう、これが思い出となる、というのはあらかじめわかるものだ。
ヤンの日常はこのまま続くけれど、連作はこれでおしまい。舞台を見終わった読者は気球に乗って飛んで行き、私自身がどこへ向かうのかも考えなあかんねとそっと促してくれるようです。
著者によるたくさんの挿絵といつもながら丁寧な未知谷の造本。手に取るだけで嬉しくなる美しい本です。
(三毛小熊猫・元書店員)
2014. 4月 (1)レジスター

(1)レジスター
海文堂書店のレジカウンターの風景を覚えておられますか?
大型書店とはずいぶん違っていましたでしょ?
昨年9月30日の営業最終日、大勢並んでくださったお客様が閉店時間を過ぎてもなかなか減らなかったのは、レジスターが各階1台ずつ(!)しかなく、しかもそれが手打ちのレジ(!)、だったからなのです。
あの日、店内放送で店長が説明していました。
「海文堂はあえてポスレジを入れていません。すべて手打ちです。お待ちいただいているお客様には申し訳ありませんが、レジ要員フル回転しておりますのでどうかご理解ください」
そうなんです。海文堂はポスレジを導入していませんでした。
コードをレーザー光で読み取るポスレジにはいろいろな役立つ機能があって、そこそこの規模の書店ではたいてい使っていますよね。
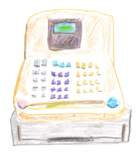 今どき手打ち?と驚かれることも多く、ある大手出版社からはポスでないならデータは要らないと、売り上げスリップの送付を断られたこともありました。
今どき手打ち?と驚かれることも多く、ある大手出版社からはポスでないならデータは要らないと、売り上げスリップの送付を断られたこともありました。
ただ、海文堂がどういう理由で「あえて」導入しなかったのかは、私たちスタッフも知らされていません。
「高いからちゃうか」という説もありました。
先代のレジは、レシートが出てくる際に店名のロゴがスタンプで押される仕組みのもので、追加するインクの量の微妙な差で薄すぎたり手に付くほど濃かったり手間のかかるものでした。
お客様から「あんたんとこのレシート、薄うて見えへんがな」と叱られては、平野さんがせっせとインクを注入していました。
ついにロゴが読めなくなり、いよいよポスレジに変更かと期待したのですが、やってきたのはさほど新型とも見えないレジスターでした。
このレジは出てきたレシートを手動で切らなくてはならず、慣れるまでは何度か悪態をついたものですが、それまでと違って領収書を発行できるタイプだったので、その意味では進化したと言えるでしょう。
あんまり褒めてあげなくてかわいそうなレジではありましたが、最終日には(たぶん能力を超えて)ずいぶん頑張ってくれました。
私自身は「ヨキミセサカエル」のレジ(こんなん皆さん知らんでしょ)からいくつものレジを経験してきましたが、ポスも含めて、ボタンの位置やトレイの大きさ、表示画面など、これぞ本屋のレジ!というものには巡り会えませんでした。
ここまで書いて気がついたのですが、海文堂のレジカウンターの風景が大型書店と違っていたのは、必ずしも手打ちのレジのせいではなかったのかもしれません。
何台も並ぶポスレジと、お金をやり取りしカバーをかける大勢の人。
いっぽう海文堂の平日昼間の1階レジは、レジ担当者1名を中心に、交代で入る数人のスタッフのみ。
いつ行っても同じ顔が並んでいるレジカウンターは、好き嫌いや良し悪しは別として文字どおり本屋の「顔」となり、それは海文堂がいくつか持っていた「顔」のひとつであったのかもしれません。
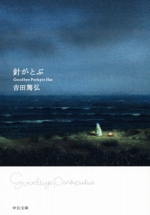 吉田篤弘『針がとぶ』
吉田篤弘『針がとぶ』
中公文庫 2013年11月発行
文庫の広告を見て思い出し、持っていた単行本を再読したくなることってありませんか。この本がそうでした。
冒頭を読んでみたら、あーこれ好きだったなあと。実に10年ぶりの文庫化です。
表題作『針がとぶ』は、詩人で翻訳家だった伯母が亡くなって、日記や思い出をたどりつつ部屋を片付けることになった姪のユイ。遺品であるビートルズの「ホワイト・アルバム」に針がとぶ箇所があることに気づき、聴くことができない音楽と伯母の知らない一面が重なる。
ゆるやかにつながったり離れたりする7つの短編は、ここ10年間に枝葉を広げ実を結んだ、篤弘さんの新作のために蒔いた種のよう。
もし私が小説家やったらこんな短編を書きたいな、というのが当時の感想だったことを思い出しました。(赤面)そして今回もちらりと同じことを思ったのでした…(さらに赤面)にんげん変わらないものです…
そこで出会った、知り合いとは言えないけれどとても親しい感じを与えてくれる人たちの体温が、いつまでも消えずに残っている。
これは、登場人物たちに対して寄せられた解説の一部です。
小川洋子さんが解説だなんてあまりにも絶妙で、文庫も欲しい!と思ったけど断念。本屋さんごめんなさい。
(三毛小熊猫・元書店員)